職場によく早退する人がいると困りますよね。
予定していた業務が滞ってしまうし、チーム全体のパフォーマンスに影響が出てしまいます。
なるべくなら早退を避け、予定通り働いてほしいですよね。
実は、仕事をよく相対する人には固有の特徴があります。
早退の背景にある本質的な課題が明確になれば、一方的な指導や叱責に頼る必要はありません。
そこで今回は、「仕事をよく早退する人の特徴や対処法」をご紹介します。
早退する人に困っているのであれば、まずはその理由を理解し、建設的な解決策を見出していきましょう。
- 早退する社員の行動パターンと心理状態の理解
- 早退が職場に与える具体的な影響とリスク
- 早退問題に対する効果的な対処法と解決策
仕事をよく早退する人の特徴

職場で頻繁に早退する人には、共通する特徴やパターンが存在します。
早退の背景には、個人の健康状態や生活環境、職場環境など、様々な要因が複雑に絡み合っているためです。
まずは、仕事をよく早退する人の特徴を見ていきましょう。
- 体調が悪い
- 家庭の事情が影響している
- モチベーションが低下している
- タイムマネジメントが苦手
- 人間関係がうまくいっていない
- 精神的な疲れが溜まっている
- 生活習慣の乱れ
体調が悪い
慢性的な体調不良により、定時まで勤務を続けることが困難な状態に陥っています。
度重なる通院や体調管理の必要性から、やむを得ず早退を繰り返すようになるのです。
たとえば、持病の悪化や定期的な通院のために、午後になると体力が持たずに早退せざるを得ない状況が発生します。
頻繁な早退の背景には、深刻な健康上の問題が隠れている可能性が高いです。
家庭の事情が影響している
家族の介護や育児など、避けられない家庭の事情を抱えている状況にあります。
家庭での役割や責任が仕事と両立できないほど、重くのしかかっているためです。
具体的には、子どもの急な発熱や家族の通院の付き添いなど、予期せぬ事態が発生して早退せざるを得ない状況に追い込まれます。
仕事と家庭の両立に苦心している実態が、頻繁な早退という形で表れているのです。
モチベーションが低下している
仕事への意欲が著しく低下し、できるだけ早く職場を離れたいと考えています。
業務内容や将来のキャリアに対する不安が、遅刻という形で顕在化するからです。
たとえば、自分の成長を実感できない業務の繰り返しや、評価への不満から、少しでも早く帰宅しようとする傾向が強まります。
職場での存在意義や目標を見失っている状況が、早退行動の根底にあるといえるでしょう。
タイムマネジメントが苦手
業務の優先順位付けや時間配分が適切にできず、効率的な仕事の進め方ができません。
時間管理のスキルが不足しており、一日の業務を計画的にこなすことができないためです。
具体的には、午前中は余裕を持って仕事をしているにもかかわらず、午後になって焦って作業を進め、結局時間内に終わらない事態が頻発します。
計画性の欠如と時間管理の未熟さが、恒常的な早退の要因となっているのです。
人間関係がうまくいっていない
早退しがちな人は、職場での人間関係に問題を抱え、できるだけ早く職場を離れたいと考えます。
同僚や上司とのコミュニケーションがうまくいかず、職場にいることにストレスを感じているためです。
たとえば、仕事上の意見の相違や人間関係のトラブルを避けるために、必要最低限の時間だけ職場にいるような行動をとります。
職場の人間関係における不調和が、早退という形で表面化しているのです。
精神的な疲れが溜まっている
心理的なストレスや精神的な疲労が限界に達していると、早退につながります。
過度な業務負担やプレッシャーにより、心身の状態が著しく低下しているためです。
仮に、些細なトラブルでも極度に落ち込んだり、パニック症状が出たりして、職場にいることができなくなる状況が発生します。
メンタルヘルスの悪化が、頻繁な早退という形で表れるのです。
生活習慣の乱れ
日常生活のリズムが崩れ、早退につながっている場合もあります。
睡眠時間の不足や不規則な食事など、基本的な生活習慣が乱れているためです。
たとえば、深夜まで起きていて朝型の勤務に体が対応できず、午後になると極度の眠気や体調不良に見舞われる状態が続きます。
不規則な生活習慣が、慢性的な早退の根本的な原因となっているのです。
仕事のストレスで早退するサイン

職場でのストレスは、様々な形で私たちの心身に影響を及ぼします。
早期発見と適切な対応が重要となりますが、多くの場合、ストレスの蓄積は徐々に進行し、気づいたときには深刻な状態に陥っていることがあります。
一緒に働いているのであれば、早退につながるストレスのサインを見逃さないことが大切です。
- 疲れが取れない
- 集中力が続かない
- イライラが増える
- 体調が不安定になる
- 仕事が楽しくない
- 人と関わるのが億劫
- 休憩を頻繁に取る
疲れが取れない
慢性的な疲労感が継続し、休息を十分にとっても回復が見られない場合があります。
心身の疲労が蓄積され、通常の休息では回復できないほどストレスが溜まっているためです。
たとえば、週末にしっかり休養を取ったにもかかわらず、月曜日の朝には既に疲労感を感じ、午後になると強い眠気に襲われる状況が続きます。
慢性的な疲労の蓄積が、心身の機能低下を引き起こしているのです。
集中力が続かない
業務中に注意力が散漫になり、簡単な作業にも時間がかかる状態に陥っています。
過度なストレスにより、脳が正常に機能できないほど疲弊しているためです。
具体的には、普段なら30分で終わる資料作成に2時間以上かかったり、同じミスを何度も繰り返したりする状況が頻発します。
ストレスによる認知機能の低下が、業務効率を著しく落とすのです。
イライラが増える
些細なことで感情が大きく揺れ動き、自分でも制御できないほどの焦りやイライラを感じています。
ストレスホルモンの分泌が過剰になり、感情のコントロールが難しくなっているためです。
たとえば、同僚の話し声や機械の音など、普段なら気にならない音にも過剰に反応し、強いストレスを感じるようになります。
イライラが増えることから、職場にいるのが嫌になっているのです。
体調が不安定になる
頭痛や胃の不調、めまいなど、様々な身体症状が突発的に出現する状況です。
ストレスによる自律神経の乱れが、身体の様々な部分に悪影響を及ぼしているためです。
仮に、重要な会議の直前に激しい頭痛が起きたり、締め切り間際になると胃痛に見舞われたりするなど、体調の変調が業務に支障をきたします。
心理的なストレスが身体症状として表れ、早退につながるといえるでしょう。
仕事が楽しくない
以前は興味を持って取り組めていた業務にも、まったくやる気が起きない状態もサインです。
ストレスにより、仕事本来の面白さや達成感を感じられなくなっているためです。
具体的には、新しいプロジェクトの話を聞いても何の興味も湧かず、日々の業務をただこなすだけの機械的な作業になってしまっています。
仕事への意欲が完全に失われている状況にあるため、早退してしまうのです。
人と関わるのが億劫
ストレスの影響で、職場でのコミュニケーションを避けようとする行動が目立っています。
対人関係にエネルギーを使うことができないほど、精神的に疲弊しているためです。
たとえば、昼食を一人で取るようになったり、必要最低限の会話しかしなくなったりと、周囲との関わりを意識的に減らしています。
社会的な交流を避けたい気持ちが強くなっているため、早退につながってしまうのです。
休憩を頻繁に取る
通常以上に休憩を取る頻度が増え、業務に集中できない時間が増加しています。
心身の疲労により、連続して仕事に取り組むことが困難な状態になっているためです。
具体的には、1時間に1回はトイレに立ったり、度々喫煙所に向かったりと、職場を離れる機会を無意識のうちに作り出しています。
休憩を繰り返すことで、ストレスフルな環境から一時的に逃避しようとしている状態です。
早退が与える仕事への影響やリスク

頻繁な早退は、個人の業務遂行能力だけでなく、組織全体のパフォーマンスにも大きな影響を及ぼします。
一時的な対応で済むように見える早退も、継続することで深刻な問題に発展する可能性があるのです。
- 信頼されなくなる
- チームの負担が増える
- キャリアに悪影響が出る
- 業務の遅れが生じる
- 職場の雰囲気が悪化する
信頼されなくなる
周囲からの信頼が徐々に失われ、重要な仕事を任せてもらえない状況に陥ります。
約束した業務時間を守れないことで、仕事に対する姿勢そのものを疑問視されているためです。
たとえば、重要なプロジェクトのメンバー選定から外されたり、締切の厳しい業務を他の社員に回されたりするような状況が発生します。
職場での信用失墜が、キャリアの大きな障壁となるでしょう。
チームの負担が増える
早退する社員の未完了業務が他のメンバーに振り分けられ、チーム全体の業務負担が増大します。
予定されていた業務の遂行が困難になり、他のメンバーが突発的に対応せざるを得ない状況が発生するためです。
具体的には、急な早退により対応できなくなった顧客からの問い合わせや、未完了の書類作成を他のメンバーが残業して処理する事態が起きています。
相対する人がいることで、チーム全体の士気低下を招くでしょう。
キャリアに悪影響が出る
昇進や昇給の機会を逃し、キャリアの成長が停滞している状態に陥ります。
勤務態度の問題として人事評価に反映され、将来的なキャリアの選択肢が狭まっているためです。
仮に、同期入社の社員が次々と昇進していく中、自分だけが現職位に据え置かれ、責任ある立場への登用機会を失っていく状況が発生します。
早退の頻発は、キャリアに悪影響が出るでしょう。
業務の遅れが生じる
定時内に完了すべき業務が次々と先送りされ、深刻な進捗の遅れが発生しています。
早退により実質的な業務時間が短くなり、計画通りの業務遂行が困難になっているためです。
たとえば、月末の締切に間に合わない報告書が溜まっていったり、重要な案件の対応が後回しになったりして、業務の停滞が常態化します。
早退の影響は、組織全体の生産性低下を引き起こしているのです。
職場の雰囲気が悪化する
頻繁な早退により、職場の人間関係に軋轢が生じ、チームの雰囲気が険悪になります。
一部の社員の勤務態度に対する不満が蓄積され、チーム内の協力関係が崩れ始めているためです。
具体的には、早退する社員への陰口が増えたり、必要最低限のコミュニケーションしか取らなくなったりと、職場の一体感が失われていきます。
チームワークが低下することで、組織の健全性が脅かされるでしょう。
仕事をよく早退する人への適切な対処法

頻繁な早退問題に対しては、表面的な対処だけでなく、根本的な原因の特定と解決が必要です。
早退する社員の状況を正確に把握し、適切なサポートを提供することで、職場全体の生産性と働きやすさを向上させることができます。
- 理由を確認する
- 仕事の負担を調整する
- 柔軟な勤務形態を提案する
- コミュニケーションを強化する
- 改善策を一緒に考える
理由を確認する
早退の背景にある本質的な課題を明確にするため、丁寧な状況確認が必要になります。
表面的な理由だけでなく、その根底にある真の原因を理解することが、問題解決の第一歩となるためです。
たとえば、定期的な面談の機会を設けて、業務上の悩みや職場環境に関する率直な意見を聞き出すことで、問題の本質が見えてきます。
早退の真の理由を把握することで、より効果的な対応が可能となるでしょう。
仕事の負担を調整する
業務量や責任の範囲が個人の能力や状況に適していない可能性が高いです。
過度な負担やプレッシャーが、早退を誘発する要因となっているためです。
具体的には、期限に余裕を持たせたり、難易度の高い業務を分散させたりすることで、一人にかかる負担を軽減することができます。
業務負担の適切な調整が、早退問題の改善につながるでしょう。
柔軟な勤務形態を提案する
従来の固定的な勤務時間が、個人の生活事情と合わなくなっている状況が見られます。
家庭の事情や健康上の理由により、標準的な勤務形態での就業が困難になっているためです。
たとえば、フレックスタイム制やテレワークなど、個人の状況に合わせた働き方の選択肢を提供することで、無理のない勤務が可能になります。
柔軟な勤務形態の導入が、早退問題の解決の糸口になるでしょう。
コミュニケーションを強化する
上司や同僚との意思疎通が不足し、適切なサポートを受けられていない状態にあります。
日常的なコミュニケーション不足により、問題が深刻化する前に対処できていないためです。
仮に、週次のチームミーティングや定期的な個別面談を実施することで、早期に問題を発見し、適切な対応を取ることができます。
オープンなコミュニケーション環境の構築が、問題解決の鍵となるでしょう。
改善策を一緒に考える
一方的な指導や改善要求ではなく、双方向の対話を通じた解決策の模索が必要な状況です。
当事者の主体的な参加なしには、持続的な改善を実現することが困難であるためです。
具体的には、本人の意見を尊重しながら実現可能な目標を設定し、段階的な改善計画を立てることで、前向きな変化を促すことができます。
協力的なアプローチが、長期的な問題解決につながるでしょう。
早退を防ぐための実践的な解決策

早退の問題を根本的に解決するためには、個人と組織の双方が協力して取り組む必要があります。
職場環境の改善や個人の意識改革を通じて、持続可能な働き方を実現することが重要です。
早期発見と予防的な対策が、健全な職場づくりの基盤となっています。
- 健康管理を徹底する
- タイムマネジメントを見直す
- 上司とコミュニケーションを取る
- 仕事環境を改善する
- ストレス管理を意識する
健康管理を徹底する
心身の健康状態が業務パフォーマンスに直接影響を与えている現状が見られます。
不規則な生活習慣や運動不足により、体力や免疫力が低下するためです。
たとえば、定期的な健康診断の受診や適度な運動習慣の確立、十分な睡眠時間の確保など、基本的な健康管理を意識的に行うことが重要です。
適切な健康管理が、安定した勤務の実現につながるでしょう。
タイムマネジメントを見直す
早退が多い人には、タイムマネジメントを見直すように伝えてください。
優先順位の設定や時間配分のスキルが不足しているため、計画的な業務遂行が困難になっているためです。
具体的には、ToDoリストの活用や時間ブロッキング、集中タイムの設定など、効率的な時間管理の手法を積極的に取り入れることができます。
効果的なタイムマネジメントが、業務効率の向上につながるでしょう。
上司とコミュニケーションを取る
職場の悩みが早退につながっているのであれば、上司とコミュニケーションを取るようにしてください。
上司との定期的なコミュニケーションが不足していると、問題が表面化する前に対処できていないためです。
仮に、週次の進捗報告や定期的な面談を通じて、業務の状況や課題を共有し、必要なサポートを受けることができます。
適切なコミュニケーションが、問題の早期解決につながるでしょう。
仕事環境を改善する
仕事環境が原因で遅刻につながっているのであれば、改善の余地があります。
作業効率を低下させる環境要因が、不必要なストレスや疲労を引き起こすためです。
たとえば、適切な照明や温度管理、効率的なデスクレイアウト、必要な業務ツールの整備など、働きやすい環境づくりを進めることができます。
快適な職場環境の整備が、業務効率の向上につながるでしょう。
ストレス管理を意識する
業務上のストレスが適切にコントロールされないと、心身の健康に影響を及ぼします。
ストレス解消の機会や方法が不足しているため、疲労やストレスが蓄積しやすい状態になっているためです。
具体的には、定期的なリフレッシュ時間の確保や、趣味や運動を通じたストレス発散、必要に応じて専門家に相談するなどの対策を取ることができます。
効果的なストレス管理が、安定した勤務の実現につながるでしょう。
仕事をよく早退する人への疑問
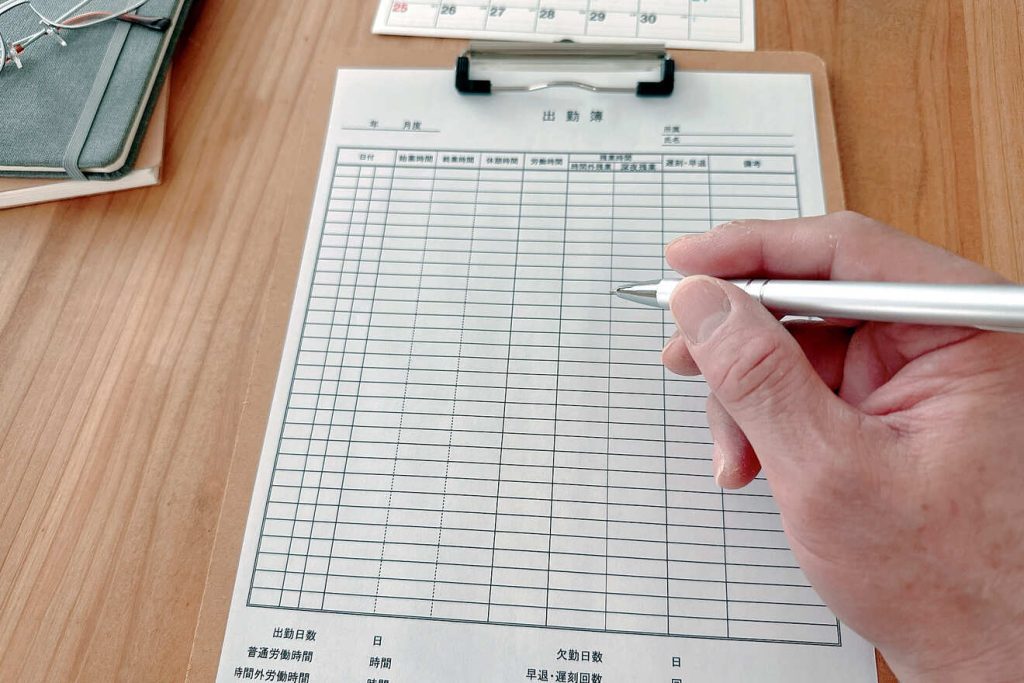
早退に関する法的な扱いや会社の対応について、多くの人が不安や疑問を抱えています。
早退は単なる勤務態度の問題ではなく、労働法規や就業規則、さらには職場環境や個人の事情など、様々な要素が絡み合う複雑な問題です。
正しい理解と適切な対応が求められています。
- 会社を早退するのは違法?
- 早退が多い社員はクビになる?
- 仕事を休みすぎとはどのくらいから?
- 仕事を無断で早退するとどうなる?
- 会社を毎日早退する人は何が原因?
会社を早退するのは違法?
正当な理由があり、適切な手続きを経て行われる早退は、法律違反には該当しません。
労働基準法上、労働時間は労使の合意に基づいて定められ、正当な理由がある場合の早退は認められているためです。
たとえば、体調不良や家族の急病など、やむを得ない事情による早退は、就業規則に則って適切に申請することで認められる場合がほとんどです。
早退の法的な取り扱いは、その理由と手続きの適切性によって判断される要素が大きいです。
早退が多い社員はクビになる?
頻繁な早退が懲戒解雇の直接的な理由となることは、一般的には稀な状況となっています。
労働契約法により、正当な理由のない解雇は無効とされ、早退だけを理由とした解雇は困難とされているためです。
具体的には、改善の機会を与えず突然解雇することは違法とされ、まずは警告や指導などの段階的な対応が必要とされます。
早退問題は、まず改善に向けた取り組みが優先されるでしょう。
仕事を休みすぎとはどのくらいから?
一概に「休みすぎ」を定義することは難しく、業界や職場の特性によって判断基準が異なります。
休暇や早退の適正な頻度は、業務の性質や職場の体制、個人の状況など、多くの要因を考慮して判断する必要があるためです。
仮に、月間の労働時間が所定時間の8割を下回る状態が続いたり、他の社員の業務に著しい支障が出始めたりした場合は、注意が必要な水準とされます。
休暇の適正範囲は、個別の状況を総合的に考慮して判断されるべき問題です。
仕事を無断で早退するとどうなる?
無断早退は重大な服務規律違反として扱われ、厳しい処分の対象となる可能性が高いです。
事前の連絡や承認なく職場を離れることは、業務運営に支障をきたし、職場の信頼関係を損なうためです。
たとえば、始末書の提出を求められたり、給与の減額や昇給・昇進の機会を逃したりするなど、様々な不利益が生じる可能性があります。
無断早退は、職場での信用を大きく損なう行為として認識されるでしょう。
会社を毎日早退する人は何が原因?
慢性的な早退の背景には、複数の要因が重なり合って深刻な状況を作り出しています。
個人の健康状態や家庭環境、職場での人間関係など、様々な問題が複合的に影響を及ぼしているためです。
たとえば、持病の管理や育児・介護の必要性、過度な業務負担によるストレス、職場での人間関係の悪化など、多岐にわたる原因が存在します。
毎日の早退には、個人と職場の双方に関わる根本的な問題が潜んでいるのです。
仕事をよく早退する人に困った体験談

筆者は以前、5人のチームリーダーを任されていました。
その中に、ほぼ毎日のように早退する社員がいたときの体験談をお話します。
最初は体調不良を理由に早退していましたが、次第に「用事がある」「気分が優れない」など、様々な理由で帰ってしまうようになりました。
他のメンバーは、彼の未完了の業務をフォローせざるを得ず、不満が募っていきます。
筆者自身も、どのように対応すべきか悩む日々が続きました。叱責すべきか、それとも優しく接するべきか。
苦悩の末、まずは彼の話をじっくりと聞くことにしたのです。
すると、家庭での介護の問題や、業務に対する不安、さらには人間関係のストレスなど、複数の問題を抱えていることがわかりました。
これらの問題に一つずつ向き合い、フレックスタイム制の活用や業務の再分配、定期的な面談の実施など、できる範囲でサポートを行いました。
この経験から、早退問題は表面的な対応だけでは解決できず、根本的な原因への理解と適切なサポートが不可欠だと学びました。
時には厳しい対応も必要ですが、まずは相手の立場に立って考えることが、問題解決の第一歩なのです。
まとめ
仕事をよく早退する人への対応は、慎重かつ建設的なアプローチが必要です。
早退の背景には、体調不良や家庭の事情、モチベーションの低下、人間関係の問題など、様々な要因が存在します。
また、疲れが取れない、集中力が続かない、イライラが増えるといったストレスのサインを見逃さないことも重要です。
確かに早退は、信頼関係の低下やチームの負担増加、業務の遅れなど、職場全体に影響を及ぼす深刻な問題です。
しかし、これらの課題に対しては、丁寧な状況確認と適切なサポートを通じて、必ず改善の道筋を見出すことができます。
健康管理の徹底やタイムマネジメントの見直し、コミュニケーションの強化など、具体的な解決策を一つずつ実践していくことで、働きやすい職場環境を築くことができます。
早退は決して違法ではありませんが、適切な手続きと相互理解が不可欠です。
一人ひとりの状況に寄り添い、個人と組織が協力しながら、持続可能な働き方を実現していくことが必要になるでしょう。



