管理職の仕事は、誰もが不安を抱えるものですよね。
昇進したばかりだと自信が持てないし、周囲から「勘違いしているのではないか」と言われたらショックです。
できることなら、もう一度基礎から管理職の仕事を学び直したいですよね。
実は、管理職の勘違いは正しい知識と適切な行動で改善することができます。
管理職の役割が明確になれば、周囲からの信頼を失うことにはなりません。
そこで今回は、「管理職の勘違いやすい仕事内容と、成功する管理職に必要な考え方」をご紹介します。
あなたが不安を感じているなら、自信を持って仕事ができるようにしていきましょう。
- 管理職としての自分の課題を客観的に把握できる
- 理想の管理職像と必要なスキルが明確になる
- 信頼される管理職になるための具体的な行動指針を得られる
管理職によくある勘違いとは

管理職に昇進すると、それまでのプレイヤーとしての仕事との違いに戸惑うことが少なくありません。
経験不足から生じる思い込みや、過去の成功体験への固執が、マネジメントの効果を低下させる原因となっているのです。
- すべて自分でやらなければならない
- 指示だけで部下は動くと思っている
- 結果がすべてだと思いがち
- 部下の問題に介入しようとする
- リーダーシップとマネジメントを混同
- 部下との距離を縮めすぎる
- 会議ばかりに時間を費やす
すべて自分でやらなければならない
仕事は部下に任せるのではなく、自分で完璧にこなすべきだと思い込んでいます。
これは、プレイヤー時代の「自分で確実に仕事をこなす」という成功体験から抜け出せていないためです。
たとえば、部下に任せた仕事に不安を感じ、休日に自分で資料を作り直したり、部下の仕事を毎日細かくチェックしたりしてしまいます。
マネジメントの本質は仕事を抱え込むことではなく、チーム全体のパフォーマンスを最大化することです。
指示だけで部下は動くと思っている
部下は指示さえ出せば自分の意図通りに動いてくれると思い込んでいます。
この考え方は、部下一人一人の理解力や経験値の違いを考慮に入れていないためです。
具体的には、「これは簡単な作業だから説明不要だろう」と思い込み、部下が戸惑っているのに気づかず、作業が滞ってしまう状況が発生します。
マネジメントにおいて、指示は必要な情報伝達の一つに過ぎないということです。
結果がすべてだと思いがち
数字で測れる成果だけを重視し、プロセスや人材育成の価値を見落としています。
これは、短期的な成果を求められるプレッシャーから、長期的な視点を失ってしまうためです。
たとえば、月次の売上目標達成のために無理な受注を取り、結果としてチームの疲弊や品質低下を招いてしまいます。
数値化できない価値も含めて、総合的に成果を評価する視点が必要になるでしょう。
部下の問題に介入しようとする
部下が抱える問題はすべて自分が解決しなければならないと考えています。
これは、管理職の役割を「問題解決者」と誤って認識していることが原因です。
具体的には、部下同士の些細な対立に過剰に介入し、かえって状況を複雑化させたり、部下の成長機会を奪ってしまったりします。
部下の問題に介入しようとすると、成長を妨げる可能性があるということです。
リーダーシップとマネジメントを混同
強いリーダーシップを発揮することが、イコール優れたマネジメントだと思い込んでいます。
これは、リーダーシップとマネジメントの本質的な違いを理解できていないためです。
たとえば、自分の考えを一方的に押し付けることで「強いリーダーシップ」を示そうとし、部下との建設的な対話の機会を失っています。
両者は異なる能力であり、状況に応じて使い分ける必要があるでしょう。
部下との距離を縮めすぎる
フレンドリーな関係性が良好なマネジメントにつながると考えています。
これは、部下との良好な人間関係と適切な距離感を取ることの違いを理解していないためです。
たとえば、業務時間外に頻繁に食事に誘ったり、プライベートな相談に深く関与したりすることで、却って部下に負担をかけています。
部下との距離を縮めすぎると、トラブルになりかねません。
会議ばかりに時間を費やす
会議の数が多いほど、組織のコミュニケーションが活性化すると信じています。
これは、形式的なコミュニケーションと実質的な情報共有を混同しているためです。
具体的には、議題や目的が不明確な会議を定期的に開催し、チームメンバーの実務時間を圧迫してしまっています。
会議の量ではなく、一つ一つの会議の質を高めることが重要になるでしょう。
管理職になる人の特徴

管理職として成功を収めている人々には、共通する特徴や資質が見られます。
これらの特徴は生まれながらのものではなく、日々の業務や様々な経験を通じて培われたものであり、意識的な努力によって強化することが可能です。
- コミュニケーション能力が高い
- 責任感が強い
- 問題解決力がある
- チームをまとめる力がある
- 柔軟な思考を持っている
- 他人の成長を支援できる
- プレッシャーに強い
コミュニケーション能力が高い
相手の立場や感情を理解しながら、適切な情報伝達ができる人材が管理職に選ばれています。
組織の円滑な運営には、正確な情報共有と良好な人間関係の構築が不可欠だからです。
たとえば、部下一人一人の性格や理解度に合わせて説明方法を変えたり、上司や他部署とのやり取りでも建設的な対話を心がけたりしています。
効果的なコミュニケーションが、組織の成功を左右する重要な要素なのです。
責任感が強い
自分の判断や行動に対して、結果を最後まで引き受ける覚悟を持っています。
管理職には組織やチームの成果に対する説明責任が伴うためです。
具体的には、プロジェクトが上手くいかない場合でも逃げ出さず、原因分析と対策立案に率先して取り組み、必要に応じて関係者への説明も自ら行います。
責任を全うする姿勢が、周囲からの信頼を築いていくでしょう。
問題解決力がある
困難な状況に直面しても、冷静に対処方法を見出すことができます。
日々の業務で直面する様々な課題に対して、粘り強く解決策を模索してきた経験があるためです。
たとえば、予期せぬトラブルが発生した際も、まず状況を正確に把握し、利用可能なリソースを確認した上で、最適な解決策を導き出していきます。
問題解決のプロセスを体系的に実行できる力が求められます。
チームをまとめる力がある
異なる個性や価値観を持つメンバーを、一つの方向に導くことができます。
組織の目標達成には、多様な人材の協力が不可欠だと理解しているからです。
具体的には、チーム内の意見の相違を調整したり、各メンバーの強みを活かした役割分担を行ったり、モチベーションを高める声かけを行ったりしています。
多様性を活かしながら、チームの一体感を醸成できる能力が重要でしょう。
柔軟な思考を持っている
状況の変化に応じて、考え方や対応を柔軟に変更することができます。
ビジネス環境の急速な変化に対応するには、固定観念にとらわれない思考が必要だからです。
たとえば、従来のやり方が通用しない場面でも、新しいアプローチを積極的に検討したり、他部署の成功事例を自部署に応用したりする姿勢があります。
変化を恐れず、常に最適な選択肢を探る姿勢が大切です。
他人の成長を支援できる
部下の成長に喜びを感じ、適切なサポートを提供することができます。
組織の持続的な発展には、メンバー一人一人の成長が不可欠だと理解しているためです。
たとえば、部下の興味や適性を見極めながら適切な業務を任せたり、失敗しても学びに変換できるようなフィードバックを行ったりしています。
他者の成長を自分の喜びとできる姿勢が求められるでしょう。
プレッシャーに強い
重圧がかかる状況下でも、冷静な判断と行動を維持できます。
管理職には常に結果や責任が求められ、様々なステークホルダーからの期待に応える必要があるためです。
具体的には、締切が迫る重要プロジェクトの遅延や、予期せぬクレーム対応など、緊急事態が発生しても感情的にならず、建設的な対応を続けられます。
プレッシャーを適切にコントロールする能力が、管理職には不可欠なのです。
ダメな管理職の特徴

管理職として不適切な言動や態度は、チームの士気低下や業績悪化を引き起こす原因となります。
これらの特徴は、管理職としての経験や学びが不足していることに起因しており、組織全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
- 部下を信頼しない
- コミュニケーション不足
- 責任を取らない
- 感情的に反応する
- 目標設定が曖昧
- 指示するだけ
- 変化に対応できない
部下を信頼しない
常に部下の行動を疑い、些細な作業まで確認や指示を繰り返しています。
自身の経験や価値観を絶対的な基準として、異なる方法や考え方を受け入れられないためです。
たとえば、部下が提出した企画書を一方的に否定したり、事前承認なしでは些細な判断も許可しなかったり、部下の行動をすべて報告させたりします。
過度の不信感は、部下の自主性や創造性を著しく損なうでしょう。
コミュニケーション不足
必要な情報共有を怠り、部下との対話の機会を積極的に設けていません。
日々の業務に追われて、部下とのコミュニケーションの重要性を軽視しているためです。
具体的には、重要な方針変更を口頭で一度伝えただけにしたり、部下からの相談や報告を後回しにしたり、定期的な面談さえ実施しなかったりします。
情報共有の不足が、組織全体の生産性低下を招いているのです。
責任を取らない
失敗や問題が発生した際に、部下や他部署に責任を転嫁します。
自身の立場や評価を守ることを優先し、管理職としての責任を理解していないためです。
たとえば、プロジェクトの遅延を部下の能力不足のせいにしたり、予算超過を他部署の非協力的な態度のせいにしたりして、自身の責任を回避しようとします。
責任逃れの姿勢が、組織の信頼関係を著しく損なうでしょう。
感情的に反応する
ストレスや焦りから感情的になり、部下に対して攻撃的な態度を取ってしまいます。
自身の感情をコントロールする能力が不足しており、プレッシャーを適切に処理できていないためです。
具体的には、締切直前のミスに大声で叱責したり、予想外の事態に激高したり、気分次第で態度を急激に変えたりする行動が見られます。
感情的な言動が、チームの心理的安全性を脅かしているということです。
目標設定が曖昧
チームや個人に対して、具体性に欠ける不明確な目標しか示せていません。
組織の方向性を明確に理解していない、もしくは部下に対する期待値を適切に言語化できていないためです。
たとえば、「もっと頑張って」「できるだけ早く」といった抽象的な指示を出したり、達成基準や期限を明確にしないまま業務を進めさせたりしています。
曖昧な目標設定が、チーム全体の方向性の混乱を招いているでしょう。
指示するだけ
一方的に指示を出すばかりで、部下の意見や提案に耳を傾けていません。
古い管理スタイルに固執し、双方向のコミュニケーションの価値を理解していないためです。
具体的には、部下からの改善提案を聞き流したり、問題提起を無視したり、経験者からの助言さえも受け入れなかったりする態度が見られます。
一方通行の指示は、組織の創造性や革新性を阻害しているのです。
変化に対応できない
従来の方法や慣習に固執し、新しい取り組みや変化を受け入れられません。
過去の成功体験に縛られ、環境の変化に適応する必要性を理解していないためです。
たとえば、デジタル化への移行を頑なに拒否したり、新しい業務プロセスの導入に反対したり、若手の革新的なアイデアを一蹴したりする行動が目立ちます。
変化に対応できないことで、組織の成長と発展の妨げになるでしょう。
管理職に求められる7つの仕事

管理職の役割は、組織の目標達成とチームの成長を両立させることにあります。
そのためには、戦略的な思考と実践的なスキルの両方が必要となり、これらの要素をバランスよく実行することで、組織全体のパフォーマンス向上につながっていきます。
- チームの目標設定
- 部下の育成と指導
- 業務の進捗管理
- 意思決定と問題解決
- コミュニケーションの促進
- 評価とフィードバック
- 組織全体との連携
チームの目標設定
組織の方針に基づいて、具体的で達成可能な目標を設定する役割を担っています。
明確な目標がなければチームの方向性が定まらず、メンバーの力を最大限に引き出せないためです。
たとえば、会社の年間目標を部門やチームレベルにブレイクダウンし、各メンバーの役割や期待値を明確にした上で、定期的な進捗確認の機会を設けています。
適切な目標設定が、チームの成功を左右する重要な要素となるでしょう。
部下の育成と指導
メンバー一人一人の成長をサポートし、組織全体の能力向上を図っています。
チームの持続的な成長には、メンバーの専門性や経験値の向上が不可欠だからです。
具体的には、個々の強みや弱みを把握した上で育成計画を立て、適切な業務アサインと実践的なフィードバックを通じて、段階的にスキルアップを図っていきます。
部下の育成と指導は、組織の未来への投資となるでしょう。
業務の進捗管理
チーム全体の業務状況を把握し、必要に応じて軌道修正を行っています。
限られた時間とリソースを最適に活用し、期待される成果を確実に達成する必要があるためです。
たとえば、定期的な進捗会議でボトルネックを特定し、リソースの再配分や期限の調整を行ったり、予期せぬ問題に対して迅速な対応策を講じたりしています。
効果的な進捗管理が、プロジェクトの成功確率を高めてくれるのです。
意思決定と問題解決
状況を適切に判断し、最適な解決策を選択する責任を負っています。
組織の方向性や成果に大きな影響を与える判断を、責任者が主体的に行う必要があるためです。
具体的には、複数の選択肢がある場合に利害関係を整理して判断を下したり、緊急事態の際に迅速な意思決定を行ったり、部門間の調整が必要な案件で合意形成を図ったりしています。
適切な判断力が、管理職には求められるでしょう。
コミュニケーションの促進
チーム内外の円滑な情報共有と相互理解を促進する役割があります。
効果的なコミュニケーションが、業務の効率化と良好な職場環境の構築につながるためです。
たとえば、定期的な1on1ミーティングでメンバーの状況を把握したり、他部署との連携会議で情報共有を図ったり、経営層の意図を分かりやすく伝達したりする機会を設けています。
コミュニケーションの質が、チームの成果を大きく左右するでしょう。
評価とフィードバック
メンバーの貢献度を適切に評価し、建設的なフィードバックを提供しています。
公平な評価と効果的なフィードバックが、メンバーの成長とモチベーション維持に不可欠だからです。
具体的には、定期的な評価面談で具体的な事実に基づいてフィードバックを行い、今後の期待値を明確に伝えた上で、必要なサポートについても話し合いの機会を設けています。
適切な評価とフィードバックが、組織の健全な発展を支えてくれるでしょう。
組織全体との連携
自チームと他部門や経営層との橋渡し役として、組織全体の最適化を図っています。
部分最適ではなく全体最適の視点で、組織の目標達成に貢献する必要があるためです。
たとえば、他部門との協業プロジェクトでリーダーシップを発揮したり、経営層への提案や報告を適切に行ったり、組織横断的な課題解決に積極的に参画したりしています。
組織全体を見据えた行動が、真の成果につながっていくのです。
管理職の器じゃない人の末路
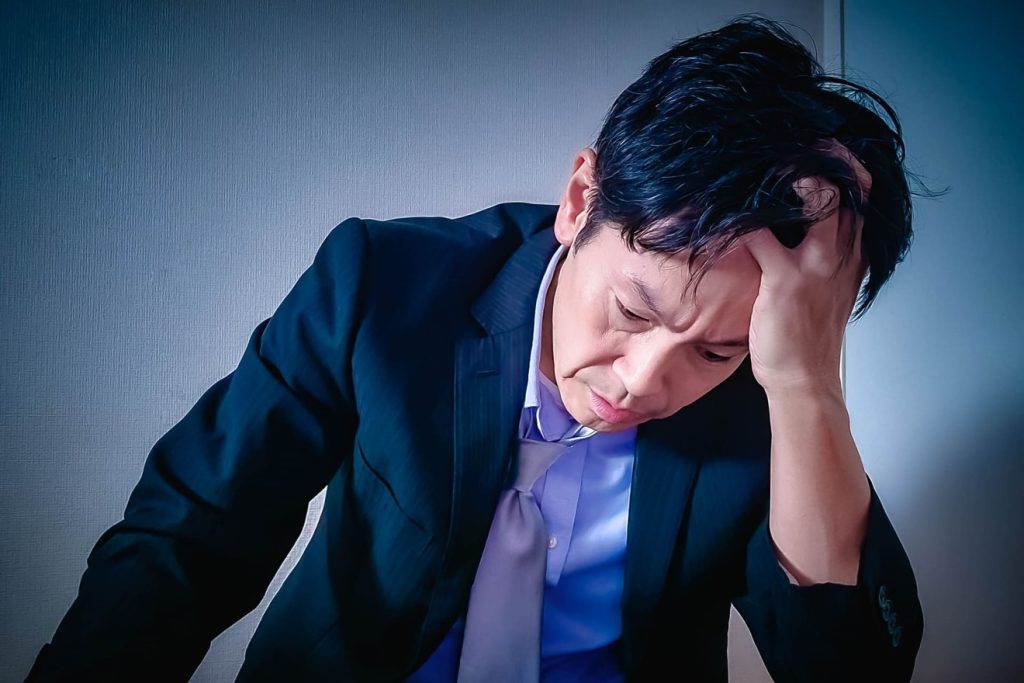
管理職としての適性に欠ける人が、その立場に留まり続けることは、個人にとっても組織にとっても大きなリスクとなります。
早期に課題を認識し対処しなければ、取り返しのつかない事態を招く可能性があり、結果として深刻な事態に発展することも少なくありません。
- 信頼を失い孤立する
- 成果が出せずに降格する
- チームが機能しなくなる
- ストレスで体調を崩す
- 転職を余儀なくされる
信頼を失い孤立する
部下からの信頼を完全に失い、上司や同僚からも避けられる存在となっています。
管理職としての基本的な振る舞いができず、周囲との関係性を適切に構築できていないためです。
たとえば、約束を守らない、責任を転嫁する、感情的な言動を繰り返すといった行動により、次第に重要な情報が入ってこなくなり、会議での発言も無視されるようになります。
信頼の欠如は、修復が極めて困難な事態を引き起こすでしょう。
成果が出せずに降格する
継続的な業績不振により、最終的に管理職の地位を失うことになります。
マネジメント能力の不足により、チームの生産性が著しく低下し、期待される成果を上げられないためです。
具体的には、案件の納期遅延が常態化する、予算管理が杜撰になる、重要顧客を失うといった事態が続き、最終的に降格という形で管理職から外されてしまいます。
成果を出せない管理職は、組織から退場を余儀なくされるのです。
チームが機能しなくなる
部下の退職が相次ぎ、残ったメンバーも意欲を失って組織が崩壊状態に陥ります。
不適切なマネジメントにより、チームの一体感が失われ、職場環境が著しく悪化しているためです。
たとえば、優秀な人材から次々と退職し、残されたメンバーも最低限の業務をこなすだけの状態となり、新しい施策を打ち出してもまったく機能しない状況に陥っています。
組織の機能不全は、取り返しのつかない損失を生むでしょう。
ストレスで体調を崩す
過度なプレッシャーにより、メンタルヘルスや身体的な不調を訴えるようになります。
管理職としての重圧と自身の能力のギャップに苦しみ、心身ともに限界を超えた状態が続いているためです。
具体的には、不眠や胃腸の不調が慢性化する、突然のパニック発作に見舞われる、出社することに強い不安を感じるといった症状が現れ、長期の休職を余儀なくされます。
心身の不調は、個人の人生に深刻な影響を及ぼすでしょう。
転職を余儀なくされる
最終的に現在の職場に居場所を失い、退職せざるを得ない状況に追い込まれます。
管理職としての失態が組織内で周知の事実となり、挽回の機会さえ与えられない状況に陥っているためです。
たとえば、部下からのハラスメント告発を受ける、重大な判断ミスで会社に損害を与える、上司からの改善命令に従えないといった事態により、自主的な退職を促されてしまいます。
不適切な管理職は、最終的に組織からの退出を迫られるのです。
管理職の仕事に関する疑問

管理職の仕事に関して、多くの人が疑問や誤解を抱えています。
その背景には、組織や立場によって管理職の役割が異なることや、時代とともにマネジメントの在り方が変化していることがあります。
これらの疑問を解消することは、より効果的な組織運営につながります。
- 管理職は実務をしないのが当たり前?
- 管理職は指示だけすればいい?
- 管理者が口を出すとうざいと思われる?
- 管理職が一番やってはいけないことは?
- 管理職じゃないのに管理職の仕事をするのはなぜ?
管理職は実務をしないのが当たり前?
実務から完全に離れることは、マネジメントの質を低下させる可能性があります。
現場の実態を把握し、適切な判断を下すためには、ある程度の実務への関与が必要だからです。
たとえば、重要プロジェクトの要所では自ら作業を担当したり、部下が困っている際には実務的なアドバイスを提供したり、技術革新に対応するため自己研鑽を続けたりしています。
管理職の実務との関わり方は、組織の規模や状況に応じて適切に判断する必要があるでしょう。
管理職は指示だけすればいい?
指示を出すだけでは、組織の目標達成は困難な状況に陥ります。
現代の複雑なビジネス環境では、双方向のコミュニケーションと協働的な問題解決が不可欠だからです。
具体的には、部下の意見を積極的に取り入れたり、チーム全体で課題解決に取り組んだり、必要に応じて自ら率先して行動したりする姿勢が求められています。
一方通行の指示だけでは、組織の潜在能力を引き出すことはできないでしょう。
管理者が口を出すとうざいと思われる?
適切なタイミングと方法での介入は、むしろチームの成長に不可欠な要素となります。
管理職の経験や知見を活かした助言が、問題解決や業務効率の向上につながる場合が多いです。
たとえば、部下が行き詰まっている際に建設的な提案を行ったり、重要な判断の前に経験に基づくアドバイスを提供したり、危機的状況で具体的な対応策を示したりしています。
介入の質とタイミングが、その効果を決定づける重要な要素となるでしょう。
管理職が一番やってはいけないことは?
組織の信頼関係を損なう行動は、取り返しのつかない事態を招きます。
信頼関係が一度失われると、いかに優れた施策を打ち出しても、その効果が著しく低下してしまうためです。
具体的には、部下の努力を認めない、約束を守らない、責任を転嫁する、感情的な態度を取る、えこひいきをするといった行動により、チーム全体のモチベーションが低下し、組織の機能が著しく損なわれます。
信頼を裏切る行為は、管理職として最も避けるべき過ちだと言えるでしょう。
管理職じゃないのに管理職の仕事をするのはなぜ?
組織の成長に伴い、マネジメント的な役割が自然と発生してきます。
チームの規模拡大や業務の複雑化により、正式な管理職以外にも調整役やリーダー的な存在が必要となるためです。
たとえば、プロジェクトリーダーとして他メンバーの業務を取りまとめたり、新入社員の教育係として指導的な立場に立ったり、専門分野のエキスパートとして他部署との調整を担ったりする機会が増えています。
役職に関わらず、状況に応じてマネジメント能力を発揮することが求められるでしょう。
管理職の仕事を勘違いしていた体験談

筆者が初めて管理職になった1年目も、大きな勘違いをしていました。
それは「すべての判断と責任を自分で抱え込まなければならない」という思い込みです。
部下からの相談には即座に解決策を示し、重要な案件は全て自分でチェックし、休日も常にメールをチェックする日々。
「部下に全部任せるのは心配。自分でやらないと!」と思っていたのです。
しかし、そんな姿を見かねた社長から一言。
「マネジメントとは、チーム全体のパフォーマンスを最大化することだ」と言われました。
その言葉を聞いて、今までのやり方では部下の成長機会を奪い、チームの潜在能力を活かせていないことに気づいたのです。
それからは何かあっても我慢し、部下と一緒に考えるようにしました。
最終チェックは筆者が行うものの、事前に部下同士でレビューする仕組みを導入したのです。
その結果、チームメンバーの主体性が高まり、より質の高い成果が出せるようになりました。
管理職の本当の仕事とは、「答えを出すこと」ではなく、「チームで答えを導き出せる環境をつくること」なのだと気づいた体験です。
まとめ
管理職の仕事で勘違いしやすい点について、詳しく解説してきました。
すべてを自分でやろうとしたり、指示だけで部下が動くと思い込んだり、結果だけにこだわりすぎたりする傾向は、多くの管理職が経験する課題です。
しかし、優れた管理職には共通する特徴があります。
高いコミュニケーション能力と責任感を持ち、問題解決力とチームをまとめる力を備え、柔軟な思考で部下の成長を支援し、プレッシャーにも強い人材です。
これらの能力は、日々の努力で必ず身につけることができます。
チームの目標設定、部下の育成、業務の進捗管理、適切な意思決定、効果的なコミュニケーション、公平な評価、組織全体との連携など、一つ一つの役割を着実にこなしていくことで、管理職としての器は確実に大きくなっていきます。
自信が持てないときは、この記事で解説した内容に立ち返ってください。
管理職の仕事を正しく理解し、適切に実践することで、必ずや信頼される管理職へと成長できるはずです。



