倉庫内作業は簡単に見えるけど、体力的にはきつそうですよね。
倉庫内を動き回ると疲れそうだし、単調な作業に飽きるのではないかと思う気持ちわかります。
なるべくなら、仕事でしんどい思いはしたくないですよね。
実は、倉庫内作業にも向き・不向きがあり、慎重に判断する必要があります。
自分の特性が職場環境に合っていれば、早期離職のリスクにはなりません。
そこで今回の記事では、「倉庫内作業の向き・不向き」を深堀り解説します。
倉庫内作業で後悔する前に、仕事内容について把握しておきましょう。
- 倉庫内作業の具体的な仕事内容と職場環境がわかる
- 自分に向いているか、向いていないかの判断基準が得られる
- 女性が働く際の具体的な注意点と対策がわかる
倉庫内作業はきついと言われる理由

倉庫内作業は多くの人が「きつい」と感じる職種の一つです。
肉体労働としての側面が強く、長時間の立ち仕事や重量物の取り扱いなど、身体への負担が避けられません。
就職や転職を検討する際は、自身の適性を慎重に見極める必要があるでしょう。
- 体力的な負担が大きい
- 高温・低温の環境
- 単調な作業が多い
- 安全面でのリスク
- 生活リズムが乱れやすい
体力的な負担が大きい
倉庫内作業では、1日の作業で平均して約10キロメートルの歩行距離があり、立ち仕事が8時間以上続きます。
商品の仕分けや在庫管理、出荷作業など、人の手による作業が必要不可欠だからです。
たとえば、20キロを超える重い荷物を台車で運んだり、脚立に上って高い棚から商品を取り出したりする作業が、休憩を挟みながらも1日中続きます。
体力的な負担の大きさは、倉庫内作業における最も重要な検討ポイントです。
高温・低温の環境
倉庫内の温度管理は商品の保管状態を重視するため、人が快適に感じる室温とは大きく異なります。
これは倉庫が商品の品質維持を最優先する施設であり、作業者の快適性よりも保管環境の適切な管理が重視されるためです。
具体的には、夏場は35度を超える暑さの中での作業が求められ、冷蔵・冷凍倉庫では氷点下での作業も発生します。
気温による身体的負担は、作業効率と健康状態に大きな影響を与えるでしょう。
単調な作業が多い
倉庫内作業の仕事は、商品のピッキング、検品、梱包という3つの作業を繰り返し行うことです。
倉庫業務の効率化と正確性を重視するため、作業手順が標準化され、同じ動作を継続して行う必要があるためです。
具体的には、ハンディターミナルで商品のバーコードを読み取り、指定された数量を確認し、段ボールに詰めるという作業を、1日に数百回も繰り返すことになります。
単調な作業の継続は、精神的な疲労を引き起こす可能性が高いです。
安全面でのリスク
倉庫内では、フォークリフトや自動搬送機との接触事故、商品の落下、転倒など、様々な事故のリスクが存在します。
これは大量の商品を効率的に保管・運搬するために、人と機械が同じ空間で作業を行う環境であることが原因です。
たとえば、通路を歩いている際にフォークリフトが急に出てくることや、高所作業時に足を踏み外してしまうなど、常に事故の危険と隣り合わせの環境で作業を行います。
安全管理の徹底は、倉庫内作業における最重要課題です。
生活リズムが乱れやすい
倉庫内作業では、24時間稼働体制をとる施設が多く、深夜勤務やシフト制が一般的な勤務形態となっています。
これは通販需要の増加や物流の効率化により、夜間も含めた継続的な作業が必要とされるためです。
仮に夜勤シフトに入った場合、日中は睡眠を取る必要があり、家族や友人との時間が合わせづらく、休日の予定も立てにくい状況に陥ります。
不規則な勤務時間による生活リズムの乱れは、心身の健康に大きな影響を与えるでしょう。
倉庫内作業が向いている人の特徴

倉庫内作業は、特定の資格や専門知識がなくても始められる職種として人気があります。
しかし、誰にでも向いているわけではなく、いくつかの適性が求められます。
自分の特徴と照らし合わせることで、長く働ける可能性が高まります。
- 体力に自信がある
- 集中力が高い
- 協力的な姿勢がある
- 柔軟な対応ができる
- 短期的な成果を求める
体力に自信がある
倉庫内作業者の中で長期間働き続けている人の多くは、スポーツ経験者や体力に自信のある人です。
日常的な重労働や長時間の立ち仕事に耐えられる体力が、業務を継続する上で最も重要な要素となるためです。
具体的には、10kg以上の荷物を一日中扱ったり、休憩時間以外はほぼ立ちっぱなしで作業したりすることに、身体的な不安を感じない人が向いています。
倉庫内作業に適応するためには、体力が重要な要素と言えるでしょう。
集中力が高い
倉庫内作業では、商品の個数確認やバーコードスキャン、ラベル貼りなど、細かな作業への集中力が求められます。
これは作業ミスが出荷の遅延や顧客クレームにつながるため、単調な作業でも確実な処理が必要とされるからです。
たとえば、似たような商品の中から正確に必要な商品を選び出したり、注文数量と実際の数量を何度も照合したりする作業を、集中力を切らさずに続けることができます。
高い集中力は、ミスのない作業を実現する鍵となるでしょう。
協力的な姿勢がある
倉庫内では、チームワークを重視した作業が多く、同僚との協力が不可欠な環境です。
これは大量の商品を効率的に処理するために、複数の作業者が連携して作業を進める必要があるためです。
具体的には、重い荷物を一緒に運んだり、混雑時には他のエリアの作業を手伝ったり、急な残業依頼にも前向きに対応したりできる姿勢が求められます。
協力的な態度は、職場全体の作業効率向上に貢献するでしょう。
柔軟な対応ができる
倉庫内作業では、突発的な注文の増加や機器のトラブル、人員の急な欠勤など、予期せぬ事態が頻繁に発生します。
物流業界特有の需要変動や、多くの人や機械が関わる作業環境であることが原因です。
仮に通常とは異なる作業への従事を求められても、新しい作業手順をすぐに習得し、臨機応変に対応できる人が、この職場では重宝されます。
柔軟な対応力は、安定した業務遂行の基盤と言えるでしょう。
短期的な成果を求める
倉庫内作業では、1日の作業量や処理スピード、ミス率など、数値で評価される明確な成果が存在します。
物流業界が効率性と生産性を重視し、日々の業績が可視化されやすい職種であるためです。
具体的には、1時間あたりの処理個数や作業完了までの時間など、具体的な数値目標を立てて、それを達成することに喜びを感じられる人が向いています。
短期的な成果を実感できることは、モチベーション維持の重要な要素となるでしょう。
倉庫内作業が向いてない人の特徴

倉庫内作業は、誰もが長く続けられる仕事ではありません。
特に、体力面や精神面で不安を抱える人にとっては、大きなリスクとなる可能性があります。
自分の特徴をよく理解し、慎重に判断することが重要です。
- 体力に自信がない
- 単調な作業が苦手
- コミュニケーションが苦手
- 健康面で不安がある
- ストレス耐性が低い
体力に自信がない
長時間の立ち仕事や重量物の運搬など、倉庫内作業では高い体力が要求されるため、体力に自信がない人は業務についていけません。
これは倉庫内作業が基本的に肉体労働であり、機械化が進んでいても人力での作業が多く必要とされるためです。
たとえば、10kgを超える荷物を何度も持ち上げたり、1日10km以上歩いたりする作業が日常的にあり、体力に自信がない人には過度な負担となります。
体力不足は作業効率の低下だけでなく、怪我や体調不良のリスクも高めるのです。
単調な作業が苦手
倉庫内作業の大半は、同じ動作を繰り返す単調な作業であり、新しい刺激や変化を求める人には向いていません。
効率性と正確性を重視する物流業務の特性上、作業の種類が限られており、毎日似たような仕事の繰り返しとなるためです。
具体的には、商品のピッキングや仕分け、梱包といった作業を数時間にわたって繰り返すため、単調な作業に飽きやすい人はすぐにモチベーションを失ってしまいます。
単調な作業への苦手意識は、仕事の継続を難しくする大きな要因となるでしょう。
コミュニケーションが苦手
倉庫内では常に他の作業者と連携しながら仕事を進める必要があり、コミュニケーションが苦手な人には大きなストレスとなります。
複数人での共同作業や、急な指示変更への対応など、頻繁なコミュニケーションが業務の円滑な遂行に不可欠だからです。
たとえば、作業の進捗状況を随時報告したり、トラブル発生時に周囲に協力を求めたり、シフト調整の相談をしたりする場面が日常的に発生します。
コミュニケーションの苦手意識は、職場での孤立や業務効率の低下を招くでしょう。
健康面で不安がある
倉庫内作業は身体的な負担が大きく、持病や体調管理に不安がある人にとっては危険な職種となります。
これは気温差の大きい環境での作業や、重量物の取り扱い、不規則な勤務シフトなど、健康面での負担が大きいからです。
具体的には、腰痛持ちの人が重い荷物を扱うことで症状が悪化したり、アレルギー体質の人が埃の多い環境で体調を崩したりするリスクが高まります。
健康面での不安は、長期的な就労を困難にする重大な要素です。
ストレス耐性が低い
倉庫内作業では、納期プレッシャーや作業ミスへの責任、人間関係など、様々なストレス要因が存在し、ストレス耐性の低い人には過度な負担となります。
物流業界特有の短納期要求や、ミスが許されない正確性の要求、チームワークを重視する職場環境が原因です。
仮に繁忙期に入ると、作業量が通常の2倍以上に増えたり、急な残業を求められたり、厳しい叱責を受けたりする状況に直面することもあります。
ストレス耐性の低さは、早期離職につながる可能性があるでしょう。
倉庫は辞める人が多いと言われるワケ
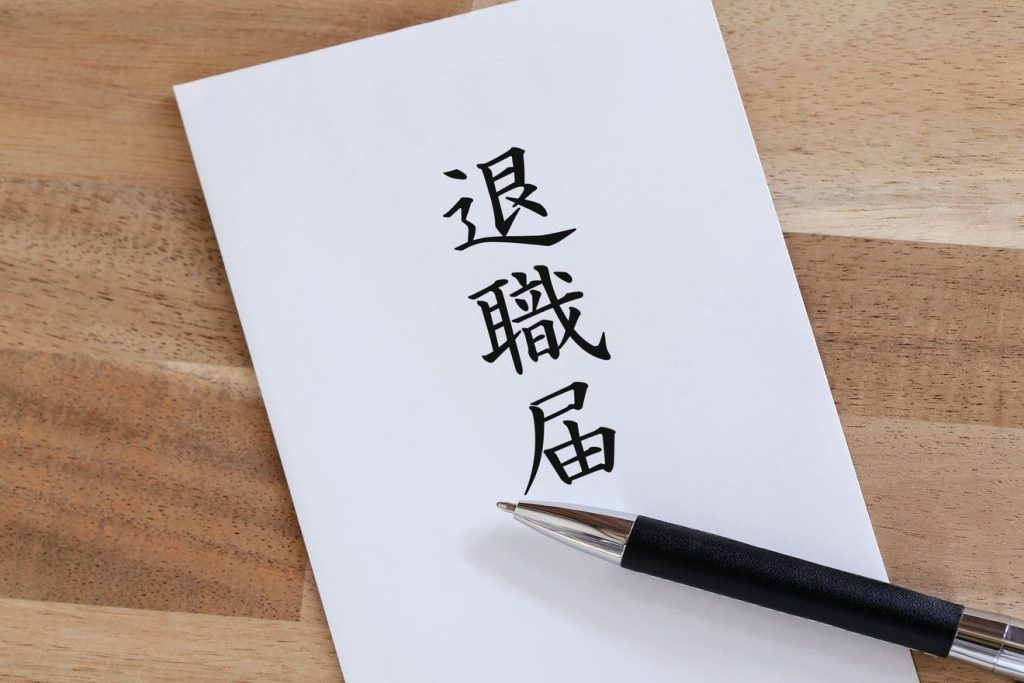
倉庫内作業の現場では、高い離職率が大きな課題となっています。
特に入社後3ヶ月以内の早期離職が目立ち、人手不足が慢性化している状況です。
現場の実態を知ることで、より良い職場選びにつながります。
- 体力的に限界を迎える
- 単調な作業に飽きる
- 収入に満足できない
- ストレスが溜まりやすい
- 成長が感じられない
体力的に限界を迎える
倉庫内作業者の多くが、入社から半年以内に体力的な限界を感じ始め、継続が困難になるケースが報告されています。
これは多くの人が自身の体力を過大評価したまま入社し、実際の業務負荷に適応できないことが原因です。
たとえば、最初の1週間は気合いで乗り切れても、毎日8時間以上の立ち仕事と重量物の運搬を続けることで、腰痛や膝の痛みなどの体調不良が慢性化していきます。
体力的な限界は、離職を決断する最も一般的な理由となるのです。
単調な作業に飽きる
倉庫内作業の単調さは、多くの従業員のモチベーション低下を引き起こし、3ヶ月から6ヶ月で仕事への興味を失う現象が見られます。
毎日同じ作業の繰り返しによって、仕事の新鮮さや達成感が徐々に失われていくためです。
具体的には、商品のピッキングや梱包作業を1日中繰り返すことで精神的な疲労が蓄積し、「このまま何年も続けられない」という思いが強くなっていきます。
単調な作業への耐性は、個人差が大きく影響するでしょう。
収入に満足できない
倉庫内作業の給与水準は、業界平均と比較して決して高くなく、多くの従業員が収入面での不満を抱えています。
物流業界の競争激化によるコスト削減圧力が、人件費に大きく影響を与えているためです。
具体的には、時給制の場合、最低賃金に数百円程度上乗せされた程度の賃金設定が一般的で、正社員でも月給20万円前後からのスタートとなる職場が多くあります。
給与面での不満は、より条件の良い職場への転職を促す要因です。
ストレスが溜まりやすい
倉庫内作業は、様々なストレス要因が複合的に存在し、多くの従業員が精神的な疲労を訴えて退職していきます。
厳しいノルマ、人間関係の軋轢、不規則な勤務形態など、複数のストレス要因が日常的に存在するためです。
たとえば、作業スピードを上げるよう常にプレッシャーを受けたり、ミスを厳しく叱責されたり、急な残業を強いられたりする状況が頻繁に発生します。
ストレス過多の環境は、メンタルヘルスの悪化を招くでしょう。
成長が感じられない
倉庫内作業では、キャリアアップの機会が限られており、多くの従業員が将来的な成長の見通しを持てずに離職していきます。
作業内容が定型化されており、新しいスキルを習得したり、より高度な業務に挑戦したりする機会が少ないためです。
仮に数年働いても、基本的な作業内容は入社時とほとんど変わらず、給与面でも大きな上昇が期待できないため、将来への不安を感じる人が多くなります。
キャリアの先行きが見えない状況は、若い世代の離職を加速させるでしょう。
女性が倉庫内作業をする時の注意点

倉庫業界は男性が多い職場ですが、近年は女性の採用も増加しています。
しかし、体力差や職場環境など、女性特有の課題も存在します。
安全で快適な就労のためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があるでしょう。
- 安全対策を徹底する
- 適切な作業服と靴を選ぶ
- ストレス解消法を見つける
- 体力に合った作業を選ぶ
- 女性に理解のある職場を選ぶ
安全対策を徹底する
倉庫内の事故は女性の場合、より重大なケースとなりやすく、十分な安全対策が不可欠です。
男性と比較して筋力や瞬発力で劣る傾向があり、危険な状況での対応力に差が出やすいためです。
具体的には、フォークリフトとの接触を避けるため通路の左側を歩く、重い荷物は必ず台車を使用する、高所作業時は命綱を着用するなど、基本的な安全ルールを必ず守る必要があります。
安全対策の徹底は、快適な職場生活の基盤です。
適切な作業服と靴を選ぶ
倉庫内作業では、動きやすく安全性の高い作業服と靴の選択が、女性にとって特に重要となります。
作業効率と安全性の確保に加えて、女性特有の体型や体調管理に配慮する必要があるためです。
たとえば、伸縮性のある作業服を選んで動きやすさを確保したり、足首をしっかりサポートする安全靴を選んで転倒を防いだり、暑さ対策として吸汗速乾素材を活用したりします。
作業服と靴の適切な選択は、業務効率と安全性を高めるでしょう。
ストレス解消法を見つける
女性は倉庫内の男性中心の環境でストレスを感じやすく、効果的なストレス解消法の確立が必要です。
これは少数派としての孤立感や、男性との体力差によるプレッシャー、セクハラなどのリスクにさらされやすい環境にあるためです。
具体的には、休憩時間に同じ女性社員との交流を持ったり、プライベートでのリフレッシュ活動を充実させたり、悩みを相談できる信頼できる上司を見つけたりすることが重要となります。
ストレス解消法の確立は、長期的な就労継続の鍵となるでしょう。
体力に合った作業を選ぶ
女性が倉庫内で働く際は、自身の体力に合った作業を選択することが、長く働き続けるための重要なポイントとなります。
無理な作業を続けることで、怪我や体調不良のリスクが高まり、早期離職につながる可能性があるためです。
仮に面接時には、重量物の運搬頻度や立ち仕事の時間など、具体的な作業内容を詳しく確認し、自分の体力で継続可能かどうかを慎重に判断することが必要です。
体力に合った作業選びは、安全で継続的な就労を可能にするでしょう。
女性に理解のある職場を選ぶ
倉庫内作業では、女性社員への配慮や理解がある職場を選ぶことが、快適な労働環境を確保する上で重要です。
更衣室やトイレなどの施設面での整備や、妊娠・出産後のキャリア継続支援など、女性特有のニーズへの対応が必要となるためです。
具体的には、女性専用の休憩スペースが確保されている、女性社員の意見が運営に反映されている、育児との両立支援制度が整っているなど、女性が働きやすい環境が整備されているかを確認します。
女性への理解度は、長期的な就労環境の質を左右するでしょう。
倉庫内作業に関するよくある疑問

倉庫業界には様々な噂や疑問が存在し、就職や転職を考える際の判断材料として重要です。
業界の実態を正しく理解することで、より良い選択につながります。
- 倉庫業界は将来性がある?
- 倉庫業界が抱える問題は?
- 倉庫内作業はパワハラが蔓延してる?
- 倉庫で働く人はどんな性格が多い?
- 倉庫は底辺だらけと言われるのはなぜ?
倉庫業界は将来性がある?
倉庫業界は、EC市場の成長に伴って需要が拡大し続けており、今後も安定した成長が見込まれています。
これはネット通販の普及により、商品の保管・配送拠点としての倉庫の重要性が高まっているためです。
たとえば、人手不足を補うためにAIやロボットの導入が進み、従来の単純作業から、より専門的なスキルを必要とする業務へと仕事内容が変化しつつあります。
倉庫業界の将来性は、物流の高度化とともに拡大していくでしょう。
倉庫業界が抱える問題は?
倉庫業界は、深刻な人手不足、設備の老朽化、利益率の低下など、複数の構造的な問題を抱えています。
労働条件の厳しさによる若手の就職離れや、価格競争の激化による収益性の悪化が主な原因です。
具体的には、必要な人員の確保が困難で残業が常態化したり、設備投資の費用捻出が難しく効率化が進まなかったり、取引先からの値下げ要請に応じざるを得ない状況が続いています。
業界全体の構造改革は、避けられない課題です。
倉庫内作業はパワハラが蔓延してる?
倉庫内作業では、納期や作業効率へのプレッシャーから、パワハラと受け取られかねない指導が発生しやすい環境にあります。
短納期での処理要求や厳しいノルマ設定により、現場の管理者がストレスを部下に転嫁してしまう傾向があるためです。
たとえば、作業の遅れを厳しく叱責されたり、ミスを大声で注意されたり、休憩時間を削って作業を強要されたりするケースが報告されています。
パワハラの発生頻度は、職場の管理体制によって大きく異なります。
倉庫で働く人はどんな性格が多い?
倉庫内作業者には、黙々と作業をこなす真面目さと、チームワークを重視する協調性を持つ人が多く見られます。
個人の作業スピードが全体の効率に影響を与え、かつ同僚との連携が必須となる職場環境であるためです。
具体的には、決められた手順を正確に守る几帳面さがある人、困っている同僚を自然とサポートできる思いやりのある人、黙々と作業を続けられる忍耐強い人などが、職場に馴染みやすい傾向にあります。
性格の相性は、職場での定着率に大きく影響するでしょう。
倉庫は底辺だらけと言われるのはなぜ?
倉庫業界が「底辺」と評される背景には、低賃金、重労働、単調な作業内容など、労働条件の厳しさが存在します。
物流業界全体のコスト削減圧力が、労働環境の改善を遅らせている現状があるためです。
仮に正社員として働いても、年収300万円程度が一般的であり、重労働の割に給与が低いことや、キャリアアップの機会が限られていることから、「誰でもできる仕事」という偏見を生んでいます。
このようなネガティブなイメージは、業界の発展を妨げる要因となっているのです。
倉庫内作業をしている人の体験
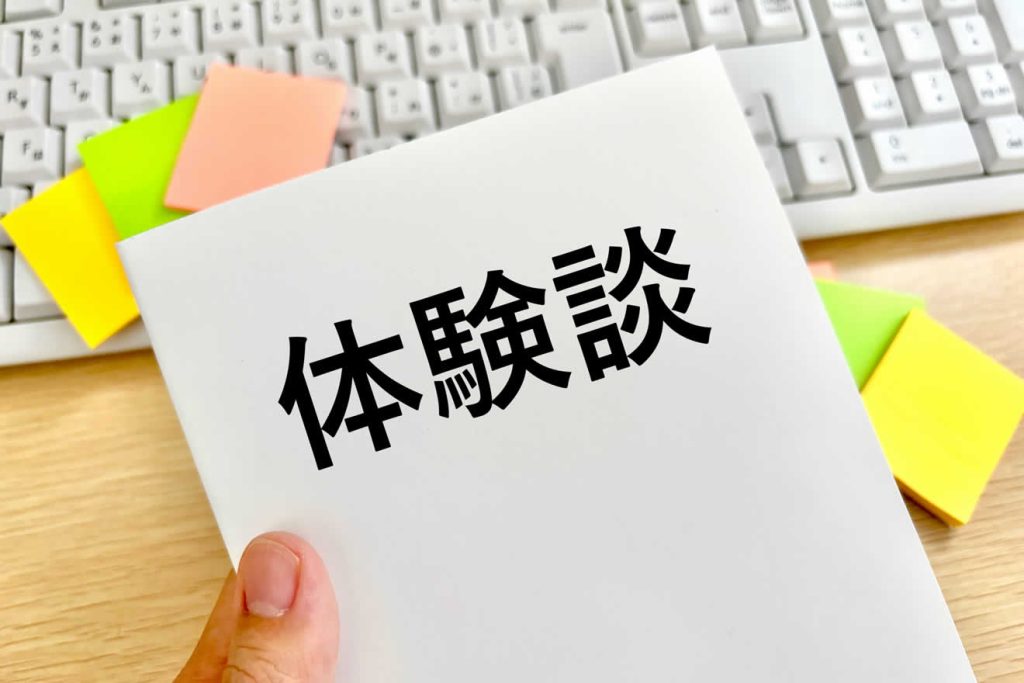
採用支援の仕事をしている中で、倉庫内作業者の方々から様々な体験談を聞く機会がありました。
特に印象的だったのは、入社2年目の女性Aさん(26歳)の話です。
「最初の1ヶ月は本当に大変でした。立ち仕事の疲れで帰宅後はすぐ眠ってしまい、休日は体を休めることしかできませんでした。でも、徐々に体が慣れてきて、今では仕事を楽しめています」
Aさんが続けられた理由は、職場環境の良さだったそうです。
女性専用の休憩室があり、重い荷物は必ず二人で運ぶルールが徹底されていました。
また、先輩社員が丁寧に指導してくれる環境も、大きな支えになったとのこと。
一方で、3ヶ月で退職したBさん(28歳)は、「工場のような暑さと単調な作業の繰り返しに耐えられなかった」と話していました。
特に夏場は室温が35度を超え、エアコンも効かない環境での作業は想像以上にきつかったそうです。
このように、同じ倉庫内作業でも、職場環境や個人の適性によって、継続できるかどうかが大きく分かれます。
事前の職場見学や労働条件の確認が、ミスマッチを防ぐ重要なポイントだと言えるでしょう。
まとめ
倉庫内作業は確かに、体力的な負担や単調な作業、不規則な勤務形態など、様々な課題を抱える職種です。
しかし、ECの発展とともに需要は拡大しており、将来性のある業界でもあります。
職場選びのポイントは、自分の体力や性格との相性を見極めることです。
体力に自信があり、集中力が高く、協調性のある方であれば、やりがいを持って働ける可能性は十分にあります。
特に女性の場合は、安全対策の徹底や適切な作業服の選択、体力に合った作業内容の確認が重要です。
また、職場環境もしっかりチェックしてください。
女性への理解がある職場、パワハラのない職場、ストレス解消できる環境があるかどうかは、長く働き続けるための重要な要素となります。
倉庫内作業を始める前に、これらのポイントをしっかりと確認することで、後悔のない選択ができます。
自分に合った職場で、安全に働ける環境を見つけることができれば、倉庫内作業は十分に検討する価値があるでしょう。



