退職願を提出したのに、本当に受理されたかわかるまで不安ですよね。
会社を辞められる確証がもてないと、転職活動ができないと思う気持ちわかります。
できることなら、スムーズに退職の準備を進めて次のステップに進みたいですよね。
実は、適切な確認方法を知っておくことで、退職願の状況を明確にすることができます。
退職願の処理状況がはっきりすれば、不必要な不安を抱えることにはなりません。
そこで今回は、「退職願が受理されたかわからない原因と対処法」をご紹介します。
退職願の状況が不明確なら、適切な方法で確認して次のステップに進めるようにしましょう。
- 退職願が受理されない原因を把握できる
- 退職願の受理確認方法を具体的に学べる
- 退職後の円満な職場離脱のコツがわかる
退職願が受理されたかわからない原因
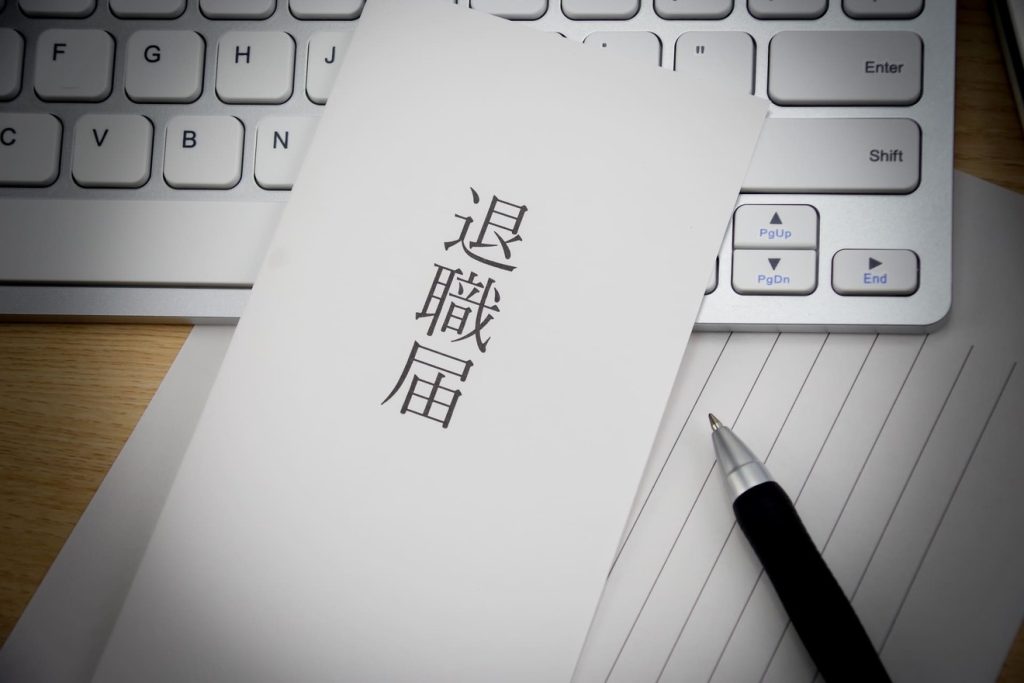
退職願を提出しても受理されたか不安になるケースは意外と多いものです。
会社によって手続きが異なるため、明確な返答がないと不安になってしまうでしょう。
- 上司が忙しい
- 確認のタイミングが遅い
- 書類に不備がある
- 伝達ミスが発生した
- 人事部門の対応が遅い
上司が忙しい
上司が多忙で、退職願の処理が後回しになっている可能性があります。
業務過多の上司は書類処理よりも目の前の仕事を優先させることが多く、退職願が机の上や引き出しに置きっぱなしになっているかもしれません。
たとえば、月末の締め作業や重要なプロジェクトが進行中の場合、上司は退職願の処理に時間を割けない状況に陥っていることがあります。
そのような場合は、上司が落ち着いたタイミングで改めて確認することが大切です。
確認のタイミングが遅い
提出から確認までの期間が空きすぎると、受理状況がわからなくなります。
退職願を提出してから早めに確認しないと、書類が社内のどこかで止まっていても気づけないからです。
具体的には、提出から1週間以上経過しても何の連絡もない状態では、手続きが進んでいるのか不明瞭になってしまいます。
早めに確認することで不安を解消し、必要に応じて再度アクションを起こせるようにしましょう。
書類に不備がある
退職願の書式や記載内容に不備があると、受理されずに保留になることがあります。
会社の規定に合わない書き方や必要事項の記入漏れがあると、人事部門で処理が止まってしまう可能性があるからです。
たとえば、退職理由の記載がない、退職予定日が就業規則に沿っていない、押印が必要なのに押されていないなどの不備があると処理が進みません。
提出前に会社の退職手続きのルールを確認しておくことが重要です。
伝達ミスが発生した
上司から人事部門への伝達過程でミスが生じている可能性もあります。
組織内のコミュニケーションエラーにより、退職願が適切に処理されていないからです。
具体的には、上司が受け取ったものの人事部門に転送するのを忘れている、または書類が社内メールで紛れてしまうなどのケースが考えられます。
伝達経路を把握し、必要に応じて上司と人事部門の両方に確認することが有効です。
人事部門の対応が遅い
人事部門の業務過多により、退職願の処理が遅れている場合があります。
退職シーズンや人事異動の時期は特に人事部門が忙しく、個別の退職願の処理に時間がかかるからです。
たとえば、年度末や大型連休前などの繁忙期には、通常より処理に時間がかかることが予想されます。
一般的な処理期間を考慮し、それを過ぎても連絡がなければ積極的に問い合わせてみましょう。
退職願が受理されたか確認する方法

退職願の受理状況を確認することは、安心して退職準備を進めるために重要です。
不安を解消するためにも、以下の方法で確実に確認しておきましょう。
- 上司に直接確認
- 人事部門に問い合わせ
- 受領印を確認
- メールで確認
- 再提出を検討
上司に直接確認
最も確実なのは、退職願を提出した上司に直接確認することです。
遠回しな言い方をするよりも、直接聞けば現状がハッキリするからです。
たとえば、「先週お渡しした退職願ですが、その後の進捗を確認したくてお声がけしました」といった形で、業務の合間に質問すると自然です。
上司との関係性を損なわないよう、丁寧な姿勢で確認するようにしましょう。
人事部門に問い合わせ
人事部門に直接問い合わせることで、処理状況を正確に把握できます。
上司を通さずに確認できるため、上司との関係に気を使う必要がないからです。
具体的には、「○月○日に退職願を○○部長に提出したのですが、人事部で手続きが進んでいるか確認したいです」といった形で問い合わせると良いでしょう。
人事部門は手続きの最終責任者なので、最も正確な情報を得ることができます。
受領印を確認
退職願のコピーに受領印や署名をもらっておくと確実です。
多くの会社では、重要書類の受領時に印や署名を押す慣行があり、これが受理の証明になります。
たとえば、退職願を2部用意して1部は会社提出用、もう1部は受領印をもらって手元に保管するという方法が効果的です。
後々のトラブル防止のためにも、この証拠を残しておくことをお勧めします。
メールで確認
書面に残る形で確認するなら、メールでの問い合わせが適しています。
メールは記録として残るため、「いつ確認したか」の証拠になるからです。
具体的には、「先日○月○日に退職願を提出させていただきましたが、正式に受理されたかご確認いただけますでしょうか」というシンプルな文面で問い合わせるとよいでしょう。
返信をもらうことで公式な回答となるため、安心して退職準備を進められます。
再提出を検討
長期間返答がない場合は、退職願の再提出を検討してください。
最初の退職願が何らかの理由で処理されていない可能性があるため、改めて提出することで確実に手続きを進められます。
たとえば、「以前提出した退職願の処理状況が不明なため、改めて提出させていただきます」と一言添えて再提出すれば、先方も対応せざるを得ない状況になります。
再提出の際には必ず日付を記録し、受領の確認を取るようにしてください。
退職願が受理された後の過ごし方

退職願が受理されたら、残りの期間を有意義に過ごすことが大切です。
円満退社のために計画的に行動し、周囲との良好な関係を維持しましょう。
- 退職日までの計画を立てる
- 丁寧に引き継ぎする
- 業務の整理を行う
- 感謝の気持ちを伝える
- 退職手続きを把握する
退職日までの計画を立てる
退職日が確定したら、残りの期間の業務スケジュールを具体的に立ててください。
計画的に業務を進めることで、退職までにすべきことを漏れなくこなせ、周囲に迷惑をかけることなく退職できます。
具体的には、カレンダーに引き継ぎの日程、書類の整理日、挨拶回りの時間などを明確に記入し、逆算して進めていくことをおすすめします。
無理のないスケジュールを組み、最後まで責任を持って仕事に取り組む姿勢を示しましょう。
丁寧に引き継ぎする
後任者や同僚への引き継ぎは、できるだけ詳細かつ丁寧に行ってください。
業務の混乱を防ぐために、担当していた業務の流れやコツ、注意点を明確に説明することが重要です。
たとえば、業務マニュアルを作成したり、よくある質問とその対処法をリスト化したり、重要な連絡先や参照資料をまとめたりすると、後任者が困ることなく業務を引き継げます。
自分の不在後も業務が滞りなく進むよう、責任を持って引き継ぎを完了させてください。
業務の整理を行う
自分の手がけてきた業務資料やデータを整理してください。
整理された状態で業務を引き継ぐことで、退職後に会社から問い合わせが来るリスクを減らせます。
具体的には、メールのフォルダ整理、共有サーバー上のファイル整理、デスク周りの書類の片付けなどを計画的に進めておくことが大切です。
個人的な資料と会社の資料をしっかり区別し、会社の情報は適切に残すようにしましょう。
感謝の気持ちを伝える
一緒に働いた同僚や上司に感謝の気持ちを伝えることで、良い印象を残せます。
円満な退社は将来のキャリアにも良い影響を与えるため、最後まで良好な人間関係を維持することが大切です。
たとえば、お世話になった方には直接挨拶に行ったり、感謝の言葉を書いたメールやカードを送ったりすることで、誠意を示すことができます。
退職後も良好なネットワークを維持できるよう、最後まで誠実な対応を心がけてください。
退職手続きを把握する
退職に伴う各種手続きを確認し、必要書類を期限内に提出してください。
健康保険や年金の切り替え、有給休暇の消化、退職金の受け取りなど、様々な手続きを遅滞なく行うことが重要です。
具体的には、人事部から提供される退職チェックリストに従って、必要書類を準備したり、社会保険関連の手続きについて確認したりすることが必要です。
漏れがないよう、早めに人事部に相談して手続きの全体像を把握することをお勧めします。
退職願が受理されない場合の対処法

退職願が受理されず、そのままにしておくと退職プロセスが進まない可能性があります。
スムーズに退職するために、計画的に対処しましょう。
- 再確認をお願いする
- 書類の不備を確認
- 書面で再提出
- 人事部門に相談
- 労働基準監督署に相談
再確認をお願いする
退職願が受理されなくても、礼儀正しく再確認することが重要です。
長期間返答がない場合は、自分から積極的に確認することで手続きが進む可能性があります。
具体的には、「先日提出した退職願の処理状況を確認させていただきたいのですが」と穏やかな口調で尋ねると、相手も対応しやすくなります。
相手の立場を尊重しながらも、自分の退職意思は明確に伝えるようにしましょう。
書類の不備を確認
退職願に必要な情報が不足していないか、書類の不備を確認してください。
書式や内容に不備があると、処理が進まない原因になるからです。
たとえば、退職日の記載漏れ、署名・捺印の欠如、必要事項の記入ミスなどがないか再度チェックしてみましょう。
会社の規定に沿った正しい書類を提出することで、スムーズな受理につながります。
書面で再提出
口頭だけでなく、書面で再度退職願を提出することも効果的です。
書面での提出は記録に残るため、退職の意思を明確に示すことができます。
具体的には、前回提出した日付に触れながら「○月○日に提出した退職願について再度提出いたします」と記載し、内容証明郵便で送ることも一つの手段です。
受領印をもらうか、メールの場合は開封確認設定をするなど、確実に相手に届いたことを確認できる方法を選びましょう。
人事部門に相談
直属の上司だけでなく、人事部門に相談することも検討してください。
組織のルールを熟知している人事部門は、適切なアドバイスや対応をしてくれる可能性があります。
たとえば、「退職願を提出したものの処理状況がわからないため、正式な手続きの流れを教えていただけないでしょうか」と相談することで、状況が改善するかもしれません。
会社の規模によっては、上司を介さずに人事部門と直接やり取りできる場合もあります。
労働基準監督署に相談
どうしても会社内で解決しない場合は、労働基準監督署に相談することも選択肢です。
退職の自由は法律で保障されており、会社が不当に退職を妨げることは認められていません。
具体的には、労働基準監督署の窓口や電話相談で「退職願を提出したが受理されない状況が続いている」と相談すれば、専門的なアドバイスが得られます。
ただし、この選択肢は会社との関係が悪化する可能性もあるため、他の方法を試した後の最終手段として検討することをお勧めします。
退職願が拒否された場合のNG行動

退職願が拒否されると不満を感じるのは当然ですが、感情に任せた行動は状況を悪化させます。
スムーズな退職のために避けるべき行動を把握しておきましょう。
- 感情的に反発する
- 無断欠勤する
- 退職を強硬に主張する
- 退職届を勝手に提出する
- 会社の規定を無視する
感情的に反発する
退職願が受理されないからといって、感情的に反応するのは避けるべきです。
冷静さを失うと、職場の人間関係を損ない、円満退社の可能性が低くなってしまいます。
たとえば、上司や人事担当者に対して声を荒げたり、他の社員の前で不満をぶつけたりすると、あなた自身の評判を下げることになります。
どんな状況でも冷静さを保ち、建設的な対話を心がけることが重要です。
無断欠勤する
退職願が受理されないからといって、無断欠勤は駄目です。
無断欠勤は就業規則違反になる可能性があり、退職金の減額や今後の転職に悪影響を及ぼすことがあります。
具体的には、退職願が受理されないストレスから「もう出社したくない」と無断欠勤すると、懲戒処分の対象となる可能性があります。
最後まで責任ある行動を取り、正式な手続きを踏んで退職することが大切です。
退職を強硬に主張する
一方的に強い態度で退職を主張するのは、状況改善につながりません。
強硬な態度は相手の反発を招き、かえって手続きが遅れる原因になることがあります。
たとえば、「絶対に○月○日に辞める」と一方的に宣言するよりも、「業務の引き継ぎも考慮した上で○月○日の退職を希望しています」と伝える方が相手も受け入れやすくなります。
対話を通じて互いに納得できる解決策を見つけることが重要です。
退職届を勝手に提出する
正規のルートを経ずに退職届を提出することは避けるべきです。
会社のルールや手続きを無視すると、無用なトラブルを引き起こす可能性があります。
具体的には、直属の上司を飛ばして社長や役員に直接退職届を提出したり、人事部に無断で書類を送りつけたりする行為は避けるべきです。
会社のルールに従って、適切なルートで退職願を提出し処理してもらうことが重要です。
会社の規定を無視する
会社の退職に関する規定を無視するのはトラブルの元です。
就業規則で定められた退職の手続きや期間を守らないと、法的な問題に発展する可能性があります。
たとえば、就業規則で「退職の1ヶ月前までに届け出ること」と定められているにもかかわらず、2週間前に退職を申し出て強行しようとすると、損害賠償を請求される可能性もあります。
退職はあなたの権利ですが、会社のルールを尊重しながら進めることが円満な退職への近道です。
退職願の受理に関するよくある疑問

退職願の提出から受理までのプロセスには不明点も多いものです。
スムーズな退職のために、よくある疑問とその回答を確認しておきましょう。
- 退職願はいつ受理されるのが一般的?
- 退職届を上司が受け取ったら受理になる?
- 退職願が受理されないのは違法?
- 退職届の受理を通知する会社もある?
- 退職願が受理されないのはパワハラ?
退職願はいつ受理されるのが一般的?
退職願は提出から1週間程度で受理されるのが一般的です。
会社のサイズや繁忙期によって異なりますが、基本的には提出後すぐに受理の手続きが始まります。
たとえば、中小企業では上司が確認した後すぐに人事部門に回され、数日以内に処理されることが多いです。一方、大企業では承認フローが複数あり、1〜2週間かかることもあります。
2週間以上経過しても何の連絡もない場合は、積極的に確認することをお勧めします。
退職届を上司が受け取ったら受理になる?
上司が受け取っただけでは正式な受理とはならないケースが多いです。
多くの会社では、上司の受領後、人事部門での処理を経て初めて正式な受理となります。
具体的には、上司が受け取った後、部門長の承認、人事部門での確認、社内システムへの登録などのステップを経て完了するのが一般的です。
確実に受理されたかどうかは、人事部門まで書類が回っているかを確認するとよいでしょう。
退職願が受理されないのは違法?
基本的に、会社は従業員の退職の意思を尊重する義務があります。
民法では「期間の定めのない雇用契約は、労働者からの申し入れにより2週間後に終了する」と定められています。
たとえば、会社が退職願を受け取らない、または処理しないといった行為は、労働者の退職の自由を侵害する可能性があります。
ただし、引き継ぎや業務都合による退職日の調整は合理的な範囲で認められているため、話し合いで解決することが望ましいでしょう。
退職届の受理を通知する会社もある?
きちんと整備された会社では、退職届の受理を正式に通知する場合もあります。
受理の証明として書面やメールで通知することで、双方のトラブルを防ぐ効果があります。
具体的には、「○月○日付けで提出された退職願について、正式に受理しましたのでお知らせします」といった通知を人事部から受け取ることがあります。
通知がない場合でも、自分から確認の連絡をすることで安心して退職準備を進められます。
退職願が受理されないのはパワハラ?
状況によっては、退職願を不当に拒否する行為がパワハラと判断される可能性があります。
正当な理由なく退職願の受理を拒否したり、退職を申し出たことで嫌がらせをしたりする行為は、職場のパワーハラスメントに該当するからです。
たとえば、「辞めるなら今後の評価に影響する」と脅したり、退職願を破り捨てたりするような行為は明らかに不適切です。
こうした状況に直面した場合は、会社の相談窓口や外部の労働相談機関に相談することをお勧めします。
退職願が受理されたかわからなかった体験談

筆者が学生時代にアルバイトをしていたお店では、学生でも退職届を出すルールでした。
しかし、退職届を出しても退職日の話はされず、ズルズル引き延ばしされたのです。
そのため、辞めるのに苦労したし、嫌な思いもしてきました。
このときの経験から、退職は難しい印象があり、気を使ったものです。
実際、初めて入社した会社を退職する際も、似たような状況に直面しました。
上司に退職願を提出したものの、「考えておく」と言われただけで、その後何の連絡もありません。
2週間経過して不安になったので、上司に直接確認したところ、「忙しくて処理できていなかった」と言われました。
その後上司と揉めて辞めることになったので、信頼関係が壊れる要因になったと思います。
これ以降、短期の仕事を含め何度か退職を経験しましたが、必ず言質を取るようにし、記録に残すようにしました。
引き止められたときもありましたが、退職意思を明確にしていたので、トラブルにはなりづらかったです。
やはり、退職という一大決心をする際は、証拠を残すのが大事だと思いました。
まとめ
退職願が受理されたかわからない状況は不安を感じますが、適切な対応で解決できます。
受理されない原因には、上司の多忙さ、確認のタイミング、書類の不備、伝達ミス、人事部門の対応遅れなどがあります。
確認方法としては、上司への直接確認、人事部門への問い合わせ、受領印の確認、メールでの確認、そして必要に応じた再提出が効果的です。
受理された後は、退職日までの計画立案、丁寧な引き継ぎ、業務の整理、感謝の気持ちの表明、そして退職手続きの把握が重要です。
受理されない場合は、再確認、書類不備のチェック、書面での再提出、人事部門への相談、最終手段としての労働基準監督署への相談を検討しましょう。
ただし、感情的な反発や無断欠勤、強硬な主張は避け、会社のルールを尊重した対応が円満退社への近道です。
退職は労働者の権利であり、誰にでも訪れる重要なライフイベントです。
適切な手続きと冷静な対応で、次のキャリアへの一歩を前向きに踏み出しましょう。



