メカニカルキーボードは、打鍵感が良くて仕事が捗る最高の入力デバイスですよね。
しかし、同僚から「うるさい」と言われたら気になるし、使わない方が良いのではないか思います。
できることなら、メカニカルキーボードを使い続けながら、周囲への迷惑も避けたいですよね。
実は、適切な対策と工夫を組み合わせることで、キーボードの音を大幅に抑えることができます。
メカニカルキーボードが問題にならなければ、職場での人間関係に悩む必要はありません。
そこで今回は、「メカニカルキーボードを静かに使うためのコツ」について解説します。
キーボードの音が気になるなら、周囲に配慮しながら使えるように改善していきましょう。
- メカニカルキーボードの音がうるさいと言われる理由がわかる
- メカニカルキーボードがうるさいと言われたときの対処法を学ぶ
- 静音性を保ちながら快適に使うためのコツを知る
メカニカルキーボードの音がうるさい理由

メカニカルキーボードは、打鍵感と耐久性に優れた入力デバイスですが、その構造的な特徴から必然的に通常のキーボードより大きな音が発生します。
まずは、メカニカルキーボードの音がうるさい理由を見ていきましょう。
- キーの構造が音を生む
- スイッチの種類による音の差
- 反発力と戻り音
- キーキャップの素材と形状
- タイピングの力加減
キーの構造が音を生む
メカニカルスイッチには複数の金属パーツが組み込まれており、キーを押すたびに独特のカチカチという音が鳴ります。
これは、スイッチ内部の金属板や金属接点が物理的に接触して音を発生させるためです。
たとえば、キーを押し込むときのカチッという音は、金属板がカチカチと接触する際に生じます。
メカニカルキーボードの音は、その構造上完全になくすことは難しいでしょう。
スイッチの種類による音の差
メカニカルキーボードのスイッチには、青軸や茶軸、赤軸など様々な種類があり、それぞれ特徴的な音を発生させます。
音の大きさや特徴が異なるのは、各スイッチの内部構造や動作方式が異なるためです。
具体的には、青軸は意図的にカチカチ音を出す設計になっているのに対し、赤軸は比較的静かな設計になっています。
スイッチの種類によって、オフィスでの使用に適しているかどうかが変わってくるでしょう。
反発力と戻り音
キーを離した際の戻り音は、スイッチのバネの反発力によって引き起こされる物理的な現象です。
これは、バネの強さと戻りの速さが音の大きさに直接影響を与えるためです。
たとえば、強いバネを使用しているスイッチでは、キーが元の位置に戻る際により大きな音が発生します。
キーの戻り音は、タイピング音全体の中で無視できない要素です。
キーキャップの素材と形状
キーキャップの材質や形状は、タイピング時の音質や音量に大きな影響を与える重要な要素となっています。
プラスチックの硬さや厚みによって振動の伝わり方が変化するためです。
例として、薄いABSプラスチック製のキーキャップは、PBT製のものと比べて高めの音が出やすい傾向にあります。
キーキャップの選択は、キーボードの音質を決定する重要な要素なのです。
タイピングの力加減
タイピング時の力の入れ具合は、キーボードの発する音量を大きく左右する重要な要因です。
必要以上の力でキーを叩くと、スイッチの底打ち音が大きくなってしまうためです。
具体的には、通常3~4グラムの力で入力できるキーを、50グラム以上の力で打鍵すると不必要に大きな音が発生します。
タイピングの力加減は、キーボードの音量に直接的な影響を与えるのです。
キーボードがうるさいと言われたときの対処法

職場でキーボードの音が問題になった場合、ハードウェアの改善やタイピング方法の調整など、様々なアプローチで音を軽減することができます。
ここからは、キーボードがうるさいと言われたときの対処法をご紹介します。
- 静音スイッチを選ぶ
- ダンパーリングを使う
- 静音キーキャップに交換する
- デスクマットを敷く
- タイピングの力を調整する
静音スイッチを選ぶ
メカニカルキーボードの音を効果的に抑えるには、サイレントスイッチへの交換が最も確実な解決策となります。
スイッチ内部に衝撃吸収材が組み込まれており、打鍵音を大幅に低減できるためです。
たとえば、Cherry MX silentredやSilent Alpacaなどのスイッチは、通常のスイッチと比べて50%以上静かになります。
オフィス環境での使用には、静音性を重視したスイッチ選びが重要です。
ダンパーリングを使う
キーボードの音を手軽に抑える方法として、ダンパーリングの装着が効果的な選択肢となります。
これは、スイッチの動きを制限し、衝突音を吸収する特殊なゴム製リングだからです。
具体的には、キーキャップの下部にOリングを取り付けることで、底打ち時の衝撃音を大幅に軽減できます。
ダンパーリングは、比較的安価で取り付けも簡単な静音化対策なのです。
静音キーキャップに交換する
静音性を重視したキーキャップに交換することで、タイピング音を効果的に抑制することができます。
特殊な素材や構造によって振動が抑えられ、音の伝播を軽減できるためです。
例として、二重構造の静音キーキャップや、高密度PBT素材を使用したキーキャップは、通常のものより明らかに静かです。
キーキャップの選択は、キーボードの音質改善に大きな影響を与えるでしょう。
デスクマットを敷く
デスクマットの使用は、キーボードの振動と音の伝播を効果的に抑制する簡単な対策です。
マットの素材が振動を吸収し、机への音の伝わりを軽減するためです。
具体的には、厚さ3mm以上のデスクマットを使用することで、キーボードの打鍵音が机を伝って響くのを防ぐことができます。
デスクマットは、見た目の改善と静音化を両立できる解決策です。
タイピングの力を調整する
過度な力でキーを押さないよう意識することで、キーボードの音を大幅に低減することができます。
これは、強い力での打鍵が不必要な衝撃音を生み出す主な原因となるためです。
たとえば、キーが反応する最小限の力(通常45g程度)でタイピングすることで、音を最小限に抑えることができます。
適切な力加減でのタイピングは、長時間の作業でも疲れにくい利点があるのです。
静音性を保ちながら快適に使うためのコツ

メカニカルキーボードは、適切な使用方法と環境への配慮を組み合わせることで、快適な入力体験と周囲への配慮を両立することができます。
ここでは、静音性を保ちながら快適に使うためのコツをご紹介します。
- 軽いタッチで打つ
- タイピングスピードを調整する
- 静音キーボードを選ぶ
- 正しい姿勢で使う
- 職場の環境に配慮する
軽いタッチで打つ
キーボードを軽いタッチで操作することは、入力精度を維持しながら音を抑える効果的な方法です。
必要以上の力でキーを押すと、スイッチの寿命を縮めるだけでなく、不快な音が発生するからです。
たとえば、キーが作動するアクチュエーションポイントを意識し、そこまでの最小限の力で押すことで、音を大幅に抑えることができます。
軽いタッチでのタイピングは、長時間の作業でも疲れにくいでしょう。
タイピングスピードを調整する
適度なスピードでタイピングすることで、音を抑えながら効率的な入力が可能になります。
過度な速さでタイピングすると、キーの戻りを待たずに次のキーを押してしまい、余計な音が発生するからです。
具体的には、1分間に200~300文字程度の速度を目安にタイピングすることで、音を抑えながら十分な作業効率を維持できます。
快適なタイピングスピードは、個人の熟練度に応じて調整することが大切です。
静音キーボードを選ぶ
最初から静音設計されたメカニカルキーボードを選ぶことで、快適な打鍵感と静音性を両立できます。
部品の選定から組み立てまで、静音性を重視して設計されているため、うるさくなりません。
例として、静電容量無接点方式のスイッチを採用したキーボードや、サイレントスイッチを標準装備したモデルは、通常のメカニカルキーボードより明らかに静かです。
静音キーボードは、オフィス環境での使用に最適な選択肢となるでしょう。
正しい姿勢で使う
適切な姿勢でタイピングすることで、不必要な力が入るのを防ぎ、結果として音も抑えられます。
肩や手首に余計な力が入ると、自然とキーを強く叩いてしまう傾向が生まれるためです。
たとえば、肘を90度に保ち、手首をデスクに置かずに浮かせた状態でタイピングすることで、自然と力が抜けて静かなタイピングができるようになります。
正しい姿勢は、タイピング音の低減と作業効率の向上につながるでしょう。
職場の環境に配慮する
オフィスの特性や周囲の作業スタイルを考慮して、キーボードの使用方法を調整してください。
同じ音量でも、環境によって感じ方が大きく異なるためです。
具体的には、静かな環境では特に音に気を配り、周りが集中している時間帯はより慎重にタイピングを行うといった配慮が必要です。
職場での快適なキーボード使用には、環境への適切な配慮が不可欠と言えるでしょう。
おすすめの静音メカニカルキーボード5選
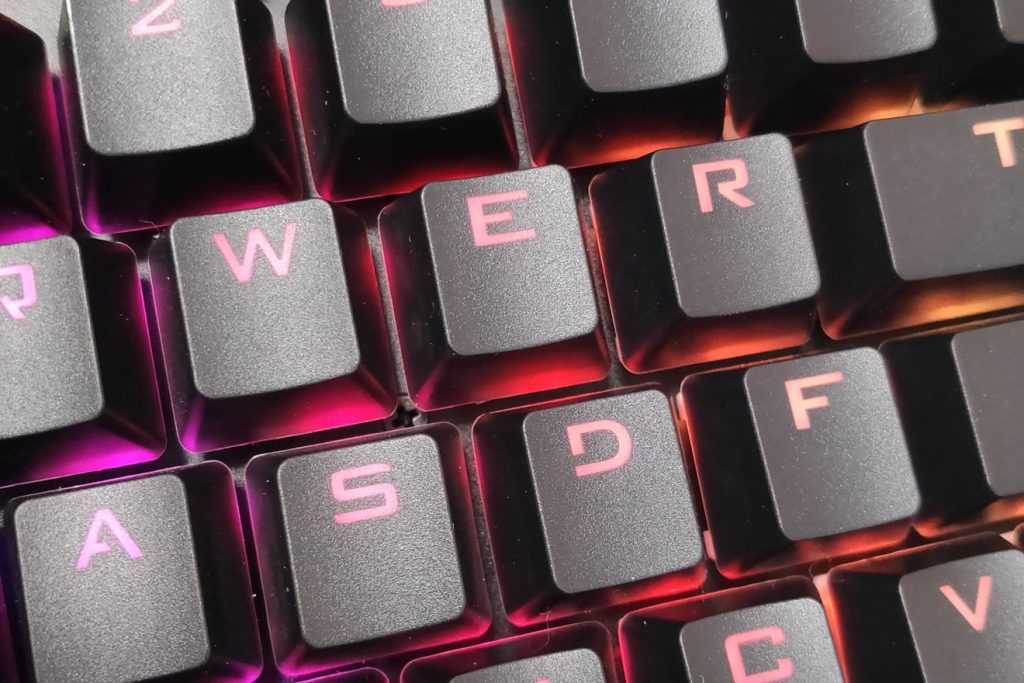
メカニカルキーボードには多くの選択肢がありますが、特に職場での使用を考えた場合、静音性と打鍵感のバランスが優れた製品を選ぶことが重要です。
そこで、おすすめの静音メカニカルキーボードを紹介します。
- Keychron K3 Pro
- Razer BlackWidow V3
- Logicool G PRO X TKL
- FILCO Majestouch 2S Silent
- Anne Pro 2
Keychron K3 Pro
Keychron K3 Proは、薄型設計とワイヤレス接続に対応した静音メカニカルキーボードとして高い評価を得ています。
独自の低姿勢スイッチを採用し、従来のメカニカルキーボードと比べて大幅な静音化を実現しているためです。
たとえば、静音赤軸搭載モデルは、一般的な赤軸と比べて打鍵音が大幅に低減されています
薄型設計、ワイヤレス接続、静音性を求めるユーザー、特にオフィスや共有スペースでの使用におすすめです。
Razer BlackWidow V3
Razer BlackWidow V3は、ゲーミングキーボードの技術を活かした高性能な静音キーボードです。
これは、Razer独自のサイレントスイッチと吸音材の組み合わせにより、優れた打鍵感と静音性を両立しているためです。
具体的には、静音リニアスイッチは滑らかなキーストロークを実現し、通常のメカニカルキーボードと比べて静音性を強化しています。
プロフェッショナルな作業環境に調和する洗練された外観も特徴です。
Logicool G PRO X TKL
Logicool G PRO X TKLは、優れたカスタマイズ性を備えた高機能ゲーミングキーボードです。
最大の特徴は、キースイッチを交換できるホットスワップ対応である点です。
様々なキースイッチに交換可能で、好みに合わせた打鍵感や静音性を実現できます。
たとえば、別売りのGX Silent Tactileスイッチに交換すれば、通常のタクタイルスイッチと比較して最大約70%の騒音低減効果が得られます。
ビジネス用途でも違和感のない、シンプルなデザインが特徴です。
FILCO Majestouch 2S Silent
FILCO Majestouch 2S Silentは、高い耐久性と静音性を兼ね備えた信頼性の高いキーボードです。
Cherry MXサイレントスイッチと高品質な日本製の部品を組み合わせることで、長期使用でも安定した性能を維持できるためです。
たとえば、特殊な静音構造により、キーの下降時と上昇時の両方で発生する音を効果的に抑制しています。
タイピング音の静かさを重視するユーザー、特に静かなオフィス環境で作業するプロフェッショナルにとって最適なキーボードです。
Anne Pro 2
Anne Pro 2は、コンパクトな60%サイズながら高い静音性と機能性を備えたキーボードです。
様々なサイレントスイッチに対応し、独自のソフトウェアによる詳細なカスタマイズが可能なためです。
具体的には、Gateron Silent BrownやKailh Box Silentなど、複数の静音スイッチオプションから選択でき、自分好みの打鍵感と静音性を実現できます。
省スペース性と静音性を両立した、デスクスペースを有効活用したい人向けのキーボードです。
職場のキーボード音に関するよくある疑問
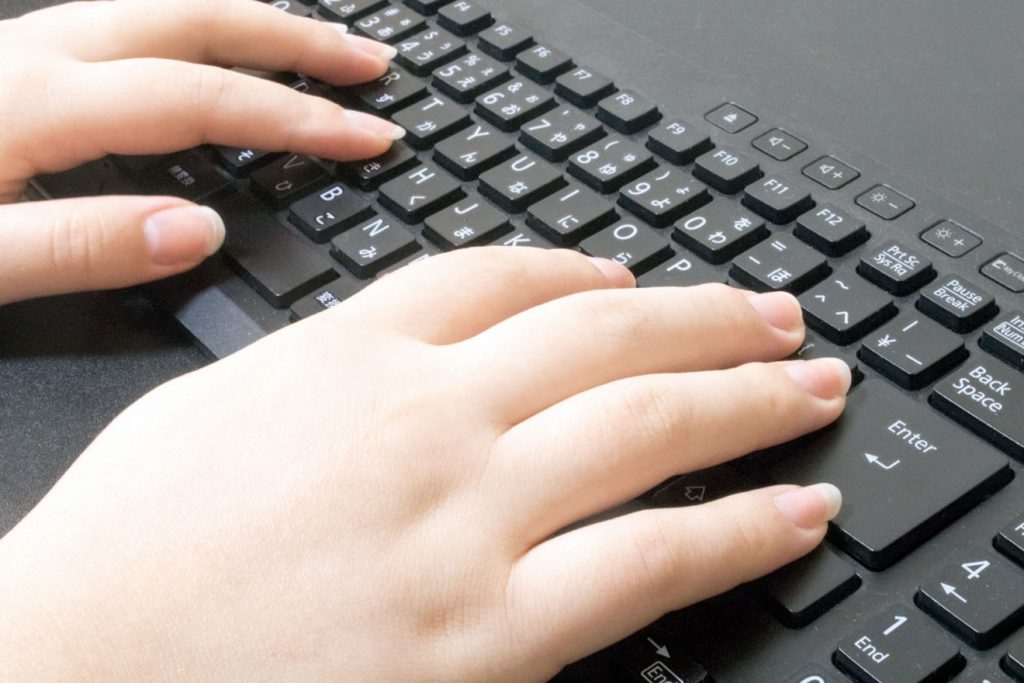
キーボードの音は、職場環境において様々な心理的・社会的な問題を引き起こす可能性があり、適切な理解と対処が必要な課題となっています。
ここでは、職場のキーボード音に関するよくある疑問について回答します。
キーボードがうるさいとノイローゼになる?
継続的なキーボード音のストレスは、実際に心身の健康に影響を与える可能性のある深刻な問題です。
不快な音の持続的な暴露が、ストレスホルモンの分泌を促進し、精神的な疲労を蓄積させるためです。
たとえば、1日8時間以上のキーボード音にさらされ続けると、集中力の低下や不眠、イライラなどの症状が現れることがあります。
職場のストレス要因として、キーボード音は軽視できない問題です。
キーボード音がうるさいとハラスメントになる?
過度なキーボード音を放置することは、職場環境配慮義務違反としてハラスメントに該当する可能性があります。
周囲の業務遂行を妨げる騒音が、心理的な苦痛を与える行為として認識されるためです。
具体的には、改善要求を無視して大きな音を出し続けることは、パワーハラスメントの一形態として扱われることがあります。
職場の音環境への配慮は、法的な義務の側面も持つのです。
キーボードがうるさい人は無能の証?
キーボード音の大きさと業務能力には、科学的な相関関係は認められていません。
タイピングの音量が、作業効率や成果の質を直接的に反映するものではないためです。
例として、プログラミングの熟練者でも、打鍵の音が大きい人もいれば、静かにタイピングする人もいます。
キーボードの音量は、個人の作業能力を判断する基準とはならないでしょう。
キーボードがうるさい人は病気?
キーボードを強く打つ傾向は、特定の病気や障害との直接的な関連性は認められていません。
タイピングの特徴が、個人の習慣や作業スタイルによって形成されることが多いためです。
たとえば、以前使用していたキーボードの特性や、独学でタイピングを習得した経緯など、様々な要因が影響している可能性があります。
キーボードの使用方法は、個人の特性の一つとして理解しましょう。
キーボードがうるさいから退職するのはあり?
キーボード音の問題だけを理由とした退職は、建設的な解決策とはならないです。
職場環境の改善や同僚との対話など、より適切な対処方法が必要にです。
たとえば、静音キーボードへの切り替えや、デスクレイアウトの変更など、様々な改善策を試すことで問題が解決することがあります。
環境改善の可能性を探ることが、最初に検討すべき対応だと言えるでしょう。
まとめ
メカニカルキーボードは、その優れた打鍵感から多くのITエンジニアに愛用されています。
しかし、職場での使用において、音の問題が避けられない課題となっています。
この問題に対しては、ハードウェアとソフトウェアの両面からアプローチすることが可能です。
静音スイッチへの交換やダンパーリングの使用、静音キーキャップへの換装といったハードウェアの改善に加え、タイピングの力加減やスピードの調整など、使用方法の工夫も効果的です。
また、Keychron K3 V2やFILCO Majestouch 2S Silentなど、最初から静音設計されたキーボードを選ぶことで、快適な打鍵感と静音性を両立することもできます。
デスクマットの使用や正しい姿勢での使用など、環境面での配慮も忘れずに行いましょう。
キーボードの音は決して能力や人格の問題ではありません。
適切な対策と周囲への配慮があれば、メカニカルキーボードは職場でも十分に活用できるツールです。
快適な作業環境と良好な人間関係の両立を目指して、自分に合った改善策を見つけていきましょう。



