会社を休んだ後に、診断書の提出を求められると困惑しますよね。
風邪で休んだだけなのに診断書が必要だと言われてしまうと、戸惑う気持ちわかります。
できることなら、診断書なしで済ませたいと考えるのは当然のことです。
実は、状況を理解して適切に対応するだけで、スムーズに進めることができます。
診断書が必要な理由がわかれば、余計なストレスを抱える必要はありません。
そこで今回は、「会社から診断書を出せと言われたときの対処法」をご紹介します。
診断書を求められたときは、落ち着いて対応できるようにしましょう。
- 診断書が必要になる理由と基準を理解できる
- 診断書を出せないときの適切な対処法を学べる
- 診断書提出のリスクと効果的な活用法がわかる
会社が診断書を求める理由

会社は従業員の健康状態を適切に把握し、労務管理を適正に行うために診断書を求めます。
これは会社の義務であると同時に、従業員の健康と安全を守るための重要な施策の一つです。
診断書は、休職や給与計算の根拠となる公的な書類として扱われます。
- 病気やケガの確認
- 長期休職のための証明
- 休業手当や給与の計算
- 休暇申請の証拠
- 労災申請のサポート
病気やケガの確認
従業員の健康状態を医学的な観点から正確に把握することが重要です。
会社は従業員の安全配慮義務を負っているため、復職時の業務内容や負荷を適切に判断する必要があります。
たとえば、インフルエンザに感染した場合、解熱後24時間経過するまでは出社を控えるべきとされています。
診断書があれば、会社は従業員の状態を正確に把握し、適切な対応を取ることができます。
従業員の健康状態を正確に把握することで、安全な職場環境を維持することができるのです。
長期休職のための証明
長期の休職が必要な場合、医師による正式な診断書は不可欠な書類になります。
会社は休職期間中の従業員の処遇を決定する際、医師の診断を重要な判断材料とするからです。
具体的には、うつ病などの精神的な不調で休職する場合、予想される回復期間や現時点での就業可否判断を医師に記載してもらいます。
これにより、会社は適切な休職期間を設定することができるのです。
休職中の従業員の健康管理と、円滑な職場復帰のために診断書による医学的な根拠が必要です。
休業手当や給与の計算
診断書は休業手当や傷病手当金の支給を判断する重要な証拠となります。
会社は従業員の欠勤が病気やケガによるものか確認し、適切な給与計算を行う必要があるからです。
仮に月給25万円の従業員が病気で2週間休んだ場合、傷病手当金の支給額は給与の3分の2程度となります。
診断書があれば、この期間の所得保障を受けることができます。
休業期間中の給与や手当の適切な計算のために、診断書による欠勤理由の証明が重要となるのです。
休暇申請の証拠
会社は従業員の休暇申請が正当な理由に基づくものかを確認する必要があります。
診断書は休暇の必要性を客観的に証明する重要な書類となり、公平な休暇管理を可能にするからです。
具体的には、手術後の療養など、長期の休暇が必要な場合、診断書に記載された療養期間をもとに休暇を承諾します。
休暇申請の透明性と公平性を確保するために、診断書による医学的な証明が必要になるのです。
労災申請のサポート
業務上の事故や疾病が発生した場合、労災保険の申請には医師による診断書が必須となります。
会社は従業員の労災申請をサポートする義務があり、診断書はその重要な証拠となるからです。
たとえば、長時間労働による過労性疾患の場合、医師の診断書に基づいて労災申請を行います。
診断書には発症時期や症状の経過など、詳細な医学的所見が記載されます。
労災保険による補償を適切に受けるために、診断書による医学的な証明が重要です。
診断書が出せないときの言い訳

診断書の提出を求められても、状況によっては入手や提出が難しい場合があります。
このような場合は、会社に対して状況を丁寧に説明し、代替案を提案することが重要です。
誠実なコミュニケーションを心がけることで、多くの場合は理解を得ることができます。
- 医者が診断書を出してくれない
- 個人のプライバシーを守りたい
- 診断書発行まで時間がかかる
- 思ったより症状が軽かった
- 診断書を紛失した
医者が診断書を出してくれない
診断書の発行を医師に依頼しても、断られるケースがあることを理解しておく必要があります。
医師には診断書発行の義務はなく、症状や状況によっては発行を見送る判断をすることがあります。
たとえば、風邪の症状で受診したものの、診察時には回復傾向にあり、安静治療のみで済む場合は、医師が診断書の発行を見送るかもしれません。
医師の判断を尊重しつつ、会社との円滑なコミュニケーションを図ることが大切です。
個人のプライバシーを守りたい
病気の内容によっては、会社に詳細を知られたくないと考えるのは当然のことです。
特にメンタルヘルスや女性特有の疾患など、デリケートな病気の場合は、プライバシーへの配慮が必要です。
診断書には病名や症状が記載されるため、それらの情報が職場で共有されることへの不安を感じる人も少なくありません。
プライバシーに関する懸念は正当な理由として認められることが多いため、会社と率直に話し合うことをお勧めします。
診断書発行まで時間がかかる
診断書の発行には一定の時間が必要となることを、会社に理解してもらう必要があります。
医師は正確な診断書を作成するため、検査結果や経過観察が必要な場合があるからです。
たとえば、MRIやCTなどの検査結果を待つ必要がある場合や、複数の診療科での診察が必要な場合は、すぐに診断書を発行することができません。
診断書発行までの時間的制約を会社に説明し、暫定的な対応について相談することが重要です。
思ったより症状が軽かった
当初は重症に感じられた症状が、受診時には軽症だったケースは珍しくありません。
医師は現時点での症状に基づいて判断を行うため、重症期の状態を診断書に記載することは難しいです。
具体的には、休暇を取得した時点では39度の熱があったものの、受診時には37度台まで解熱していた場合、医師は現在の症状に基づいて診断を行います。
症状の変化について会社に丁寧に説明し、対応を相談することが解決につながるでしょう。
診断書を紛失した
診断書の提出を遅らせる言い訳として、紛失を伝えることが考えられます。
具体的な時期や場所を説明できるようにしておくことで、より自然な言い訳となるのです。
たとえば、「通勤途中のカバンの中に入れていた封筒が見当たらなくなってしまい、電車内で紛失した可能性があります。明日にでも病院に再発行をお願いしに行きたいと思います」といった説明をすることで、一定の猶予を得ることができます。
診断書の紛失は誰にでも起こりうるアクシデントになるため、その場しのぎの言い訳には使えるでしょう。
診断書を出せないと言われたときの対処法

医師から診断書の発行を断られた場合でも、諦める必要はありません。
状況に応じて適切な対応を取ることで、多くの場合は解決策を見つけることができます。
会社に必要な診断書を入手するためには、いくつかの選択肢があります。
- 医者に必要な理由を説明する
- 別の病院で発行をお願いする
- 診断内容に誤解がないか確認
- 病院の領収書を会社に提出
- 医者の方針を尊重する
医者に必要な理由を説明する
診断書の必要性を医師に詳しく説明することで、発行してもらえる可能性が高まります。
多くの医師は、患者の事情を理解すれば柔軟に対応してくれるからです。
具体的には、「会社の規定で3日以上の病欠には診断書が必要なため、発行をお願いできないでしょうか?」「傷病手当金の申請に必要なので、ご検討いただけないでしょうか?」といった形で依頼するのが効果的です。
丁寧な説明と依頼により、医師の協力を得られる可能性が高まるでしょう。
別の病院で発行をお願いする
一つの医療機関で断られた場合、別の病院を受診して診断書の発行を依頼することも選択肢の一つです。
特に専門医のいる病院であれば、より詳しい診断と適切な診断書の発行が期待できます。
たとえば、内科で断られた場合でも、同じ症状を専門とする診療科のある病院であれば、より詳しい検査と診断に基づいた診断書を発行してもらえる可能性があります。
医療機関の変更を検討することで、必要な診断書を入手できるでしょう。
診断内容に誤解がないか確認
医師が診断書の発行を躊躇する理由の一つに、症状の解釈や診断内容への不安がある場合があります。
このような場合は、医師と十分なコミュニケーションを取ることが重要です。
具体的には、「先週から続く頭痛で仕事に支障が出ており、安静が必要な状態です」「通勤時の満員電車での立ち仕事が困難な状況です」といった具体的な症状と生活への影響を説明します。
医師との適切なコミュニケーションにより、診断書の発行につながるでしょう。
病院の領収書を会社に提出
診断書が入手できない場合の代替案として、病院の領収書や処方箋の提出を会社に提案する方法があります。
これらの書類でも、医療機関での受診事実を証明することができるからです。
たとえば、「診察と薬の処方を受けた際の領収書がありますので、これを提出させていただくことは可能でしょうか?」と会社に相談してください。
また、処方された薬の説明書なども、症状を証明する補助資料として活用できます。
代替書類の提出について会社と相談することで、柔軟な解決策を見つけることができるでしょう。
医者の方針を尊重する
医師が診断書の発行を見送る理由には、症状が軽微である場合や、診察時に症状が改善している場合など、医学的な根拠があります。
このような医師の判断は、患者の健康状態を考慮した専門的な見解です。
仮に「症状が軽度なため、診断書の発行は適切ではないと判断しました」と医師から説明された場合、その旨を会社に伝え、代替案を相談することが適切です。
医師からの説明内容を踏まえて、会社との対応を検討しましょう。
診断書提出後のやりとりで気をつけること

診断書を提出した後も、適切なフォローアップが重要です。
スムーズな職場復帰と今後の労務管理のために、会社側と十分なコミュニケーションを取ることが必要となります。
特に重要なのは、提出後の取り扱いや追加で必要な手続きの確認です。
- 診断内容を確認してから提出
- 診断書の利用方法を会社に確認
- 上司にプライバシー保護方針を聞く
- 他に必要な手続きがないか聞く
- 不安があれば人事部門に相談
診断内容を確認してから提出
診断書を会社に提出する前に、記載内容を必ず確認しておくことが重要です。
特に休職期間や就業制限などの記載は、その後の勤務条件に大きく影響する可能性があります。
たとえば、「要休養」という記載が「自宅療養」を意味するのか、「軽作業可」なのかといった具体的な解釈について、医師に確認しておきます。
また、投薬内容や通院頻度についても、会社から質問される可能性があるため、把握しておく必要があります。
提出前の内容確認により、その後のスムーズな対応が可能になるでしょう。
診断書の利用方法を会社に確認
診断書の提出後、会社がどのように利用するのかを確認することが重要です。
診断書は給与計算や休職手続き、傷病手当金の申請など、様々な用途に使用される可能性があります。
たとえば、人事部門に「この診断書は給与計算と休職手続きの両方に使用されるのでしょうか?」「傷病手当金の申請に使用する場合、別途コピーが必要になりますか?」といった確認を行ってください。
利用目的を明確にすることで、追加の手続きや書類が必要な場合に迅速に対応できるでしょう。
上司にプライバシー保護方針を聞く
診断書には個人の健康情報が含まれているため、その取り扱いについて会社の方針を確認することが重要です。
特に病名や症状の詳細について、どの範囲まで共有されるのかを把握しておく必要があります。
具体的には、「診断書の内容は人事部門以外の方とも共有されるのでしょうか?」「チーム内での共有事項について、どのように説明すればよいでしょうか?」といった確認を行います。
プライバシーの保護範囲を明確にすることで、安心して職場復帰の準備を進めることができるでしょう。
他に必要な手続きがないか聞く
診断書の提出だけでなく、その他の必要書類や手続きがないかを確認することが重要です。
会社の規定によっては、追加の書類提出や申請が必要になる場合があります。
具体的には、「傷病手当金の申請に必要な書類は他にありますか?」「復職時には診断書の再提出が必要になりますか?」「健康保険組合への手続きは別途必要でしょうか?」といった確認を行います。
必要な手続きを漏れなく把握することで、スムーズな対応が可能になるでしょう。
不安があれば人事部門に相談
診断書の提出や休職に関して不安や疑問がある場合は、人事部門に相談することをお勧めします。
人事部門は労務管理の専門部署であり、様々なケースに対応した経験があるからです。
たとえば、「休職期間中の給与計算について詳しく教えていただけますか?」「復職時の手続きの流れを確認させていただきたいのですが」といった形で相談を持ちかけます。
会社の人事部門に相談することで、適切なサポートを受けることができるでしょう。
診断書を出さない場合に考えられるリスク

診断書の提出は会社の規定で定められていることが多く、正当な理由なく提出を拒否することは様々な問題を引き起こす可能性があります。
特に長期の休暇や傷病手当金が関係する場合は、慎重な判断が必要です。
- 給与が支払われない可能性
- 休職扱いになるリスク
- 信頼関係の悪化
- 解雇や処分の対象になる
- 健康管理に支障が出る
給与が支払われない可能性
診断書を提出しないことで、休暇中の給与支払いが滞る可能性があります。
診断書を提出しない場合、どんな理由で休んだのかわからないからです。
たとえば、1週間の病欠で診断書を提出しなかった場合、その期間が無給扱いとなり、給与から控除されるかもしれません。
また、傷病手当金の申請にも診断書が必須となるため、長期の休養が必要な場合は特に注意が必要です。
会社の規定に沿った適切な対応により、給与や手当の不利益を防ぐことができるでしょう。
休職扱いになるリスク
診断書が提出されない場合、会社は欠勤を休職として扱う可能性があります。
休職は給与や勤務条件に大きく影響するため、安易に判断することは避けるべきです。
たとえば、欠勤が2週間を超える場合に休職発令となる会社では、診断書の不提出により予期せぬ休職処理が行われ、給与が減額されたり、職場復帰時の手続きが複雑になったりする場合があります。
そのため、適切な診断書の提出により、不要な休職処理を防ぐことができるのです。
信頼関係の悪化
正当な理由なく診断書の提出を拒否することは、上司や同僚との信頼関係を損なう原因となります。
特にチームで働く環境では、他のメンバーの業務負担が増えることへの配慮も必要です。
診断書の提出は、自身の体調不良を客観的に証明する手段です。
提出を拒否することは、休暇の理由に対する疑念を生む可能性があり、職場での評価にも影響を与えかねません。
会社の規定に従った適切な対応により、職場での信頼関係を維持することができるでしょう。
解雇や処分の対象になる
診断書の不提出が続く場合、就業規則違反として懲戒処分や解雇になる可能性があります。
特に再三の提出要請を無視した場合は、重大な問題として扱われる場合があるからです。
多くの会社では、正当な理由のない診断書の不提出を、服務規律違反として扱います。
始末書の提出や減給などの処分を受ける可能性があり、悪質な場合は解雇事由となってもおかしくありません。
会社の規則に従い、適切な手続きを行うことで、不要な処分を回避することができます。
健康管理に支障が出る
診断書の提出を避けることで、適切な健康管理や治療が遅れるリスクがあります。
診断書は単なる手続き書類ではなく、専門家による健康状態の評価として重要な意味を持つからです。
具体的には、腰痛や頭痛などの症状を抱えながら診察を受けずに無理を続けた場合、症状が重症化し、より長期の治療が必要になるかもしれません。
適切な診断と治療を受けることで、健康的な職場生活を送ることができるでしょう。
会社に診断書を出せと言われた際の疑問

診断書の提出を求められた際には、様々な疑問や不安が生じるものです。
提出の要否や手続きの方法、費用負担など、知っておくべき基本的な事項について理解しておくことで、適切な対応が可能になります。
- 診断書を出すと会社が病院に確認する?
- 通常は会社を何日休んだら診断書が必要?
- 会社を休むのが1日でも診断書が必要?
- 会社に提出する診断書の内容は?
- 会社に診断書の提出を拒否できる?
- 診断書の費用は会社が負担してくれる?
- バイトでも診断書を出さなければいけない?
診断書を出すと会社が病院に確認する?
会社が診断書の内容について病院に直接確認することは、原則としてありません。
医療情報は厳重に保護される個人情報であり、病院が患者の同意なく会社からの問い合わせに応じることはできないからです。
たとえば、診断書に記載された病名や治療期間について、会社が病院に電話で確認することはできません。
ただし、労災保険の申請など、正当な理由がある場合は、本人の同意を得た上で医療情報が共有されることがあります。
通常は会社を何日休んだら診断書が必要?
一般的に、連続して3日以上休む場合に診断書の提出が求められることが多いです。
ただし、この基準は会社によって異なり、就業規則や社内規定で定められています。
会社の規模や業態によって基準は様々で、1週間以上の場合に必要とする会社もあれば、5日以上の場合に必要とする会社もあります。
また、インフルエンザなどの感染症の場合は、期間に関わらず診断書の提出を求められることがあります。
会社の規定を確認し、適切なタイミングで診断書を提出することが重要です。
会社を休むのが1日でも診断書が必要?
1日の休暇で診断書の提出を求められることは、一般的ではありません。
ただし、会社の規定や状況によっては、1日の休暇でも診断書が必要になる場合があります。
特に、重要な会議や締切が設定された業務がある日の欠勤の場合や、度重なる1日休暇が続く場合には、診断書の提出を求められることがあります。
また、感染症の疑いがある場合も、1日でも診断書が必要になることがあります。
1日の休暇であっても、状況に応じて診断書が必要になることを理解しておきましょう。
会社に提出する診断書の内容は?
一般的な診断書には、患者の氏名、生年月日、診断名、治療期間、就業制限の有無、発行日、医療機関名、医師名などが記載されます。
ただし、会社が求める形式によって、記載内容は異なることがあります。
たとえば、「腰椎捻挫により、2週間の安静加療が必要。その間のデスクワークは可能だが、重量物の取扱いは制限する」といった具体的な内容が記載されます。
このような情報は、会社が勤務体制を検討する際の重要な判断材料となります。
必要な情報が適切に記載されているか、提出前に確認することが重要です。
会社に診断書の提出を拒否できる?
診断書の提出を完全に拒否することは難しく、正当な理由がない場合は就業規則違反となる可能性があります。
会社には従業員の健康管理責任があり、長期の休暇や傷病手当金の申請には診断書が必要になるからです。
具体的には、精神疾患や婦人科系の疾患など、デリケートな病名については、病名を伏せた診断書の発行を医師に依頼することができます。
状況に応じて、提出方法や記載内容について柔軟な対応を求めることは可能です。
診断書の費用は会社が負担してくれる?
診断書の発行費用は、原則として従業員の自己負担となります。
一般的な診断書の発行費用は、医療機関によって異なりますが、2,000円から5,000円程度が一般的です。
詳細な記載が必要な場合や、英文での発行が必要な場合は、さらに高額になることがあります。
たとえば、労災申請のために会社が診断書を求める場合は、会社負担となることが一般的です。
また、福利厚生の一環として、診断書発行費用を会社が補助する制度を設けている場合もあります。
費用負担について不明な場合は、人事部門に確認することをお勧めします。
バイトでも診断書を出さなければいけない?
アルバイトでも、正社員と同様に診断書の提出を求められることがあります。
特に長期の欠勤や、感染症による欠勤の場合は、診断書が必要になることが多いです。
たとえば、インフルエンザに感染した場合は、アルバイトでも職場での感染予防の観点から診断書の提出が必要になることがあります。
また、長期のアルバイトで、定期的に出勤している場合は、正社員と同様の基準が適用されることもあります。
雇用形態に関わらず、会社の規定を確認し、適切に対応することが重要です。
会社に診断書を出せと言われた体験談
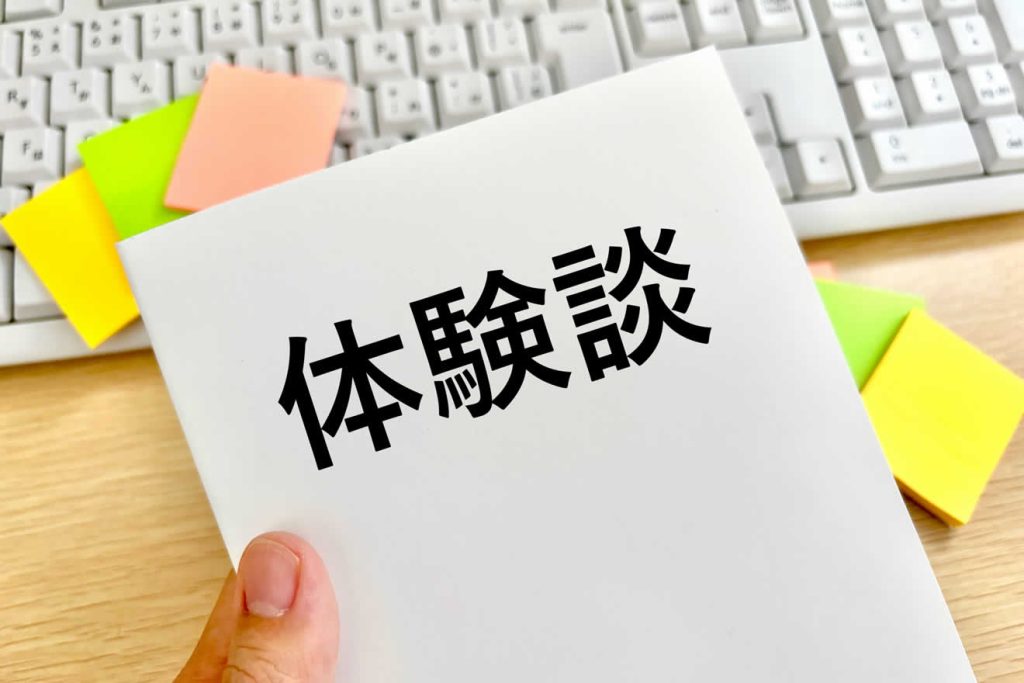
筆者も以前、体調不良で3日間会社を休んだときに、上司から「診断書を提出してください」とメールで言われた経験があります。
当時は、診断書がなぜ必要なのか、どうやって取得すればいいのか、全く分かりませんでした。
また、発行費用も気になり、正直なところ面倒だなと感じていたのです。
しかし、人事部に相談してみると、3日以上の病欠の場合は会社の規定で診断書が必要であること、傷病手当金の申請にも使用できることを教えてもらいました。
それをかかりつけ医に相談したところ、快く書いてもらうことになりました。
この経験から、診断書の提出は従業員の健康管理のための重要な仕組みだと理解できました。
今では後輩に対して、診断書について相談されることも多くなり、自分の経験を活かしてアドバイスができています。
会社の規定をきちんと理解し、必要な手続きを行うことで、安心して療養に専念できることを実感しました。
まとめ
会社から診断書の提出を求められることは、多くの人が経験する一般的な出来事です。
長期休職や休業手当の計算、労災申請など、会社には診断書を必要とする正当な理由があります。
診断書の入手が難しい場合は、医師に必要性を説明したり、別の病院を受診したりするなど、いくつかの対処方法があります。
また、状況によっては領収書や処方箋での代用を認めてもらえることもあります。
提出後は、内容の確認や利用方法の把握、プライバシーの保護など、いくつかの確認事項がありますが、上司や人事に相談すれば適切なアドバイスを得られます。
診断書の提出は、決して面倒な手続きではなく、むしろ自身の健康管理と適切な労務管理のための重要なステップです。
会社の規定を理解し、必要に応じて医師に相談しながら、前向きに対応していきましょう。



