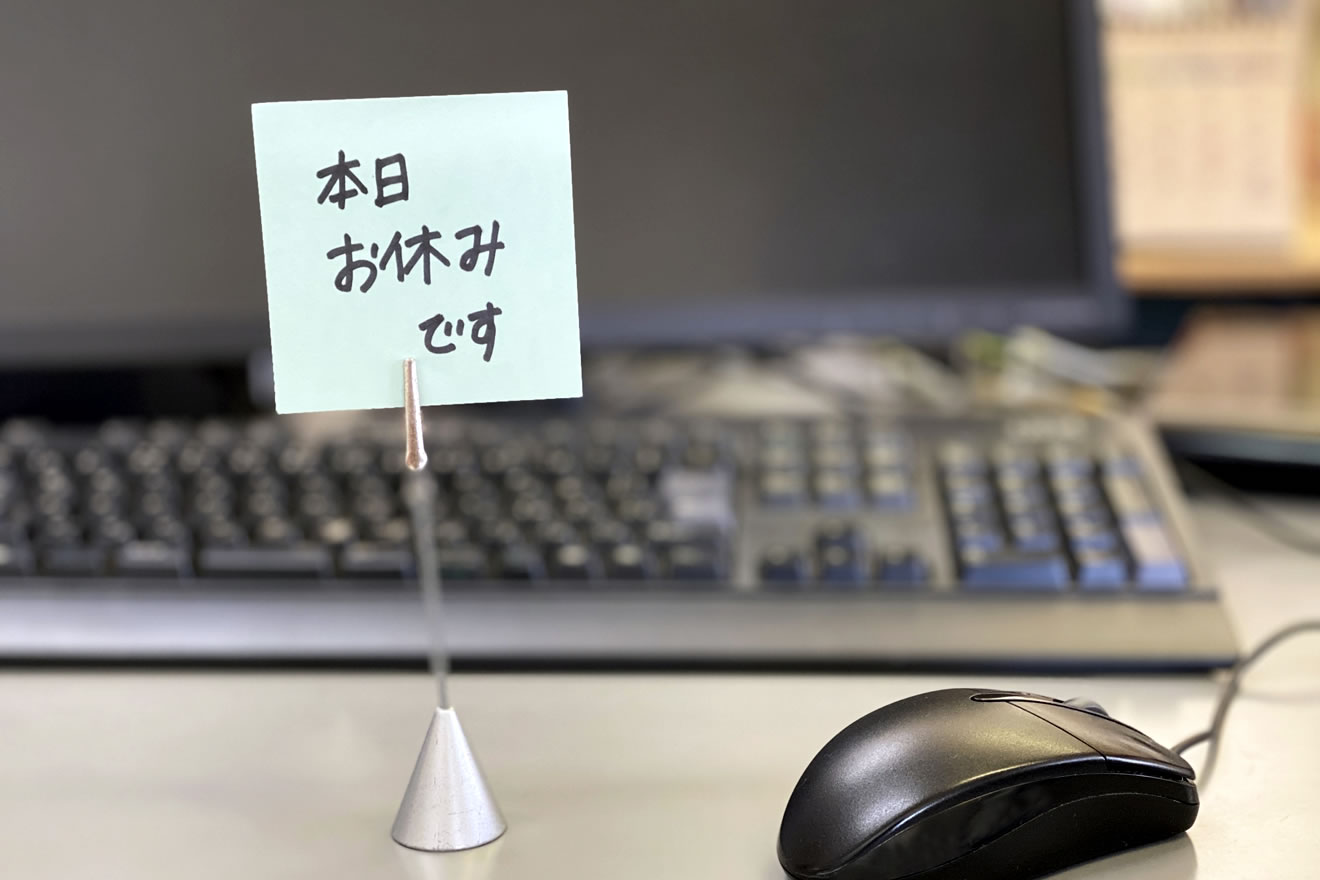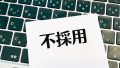職場での体調不良による欠勤は、チーム全体の業務に大きな影響を及ぼしますよね。
急な欠勤で仕事が滞ってしまうし、誰かがその分の業務をカバーしなければなりません。
体調不良で休みがちな同僚の状況を理解しつつ、円滑な業務遂行を実現したいですよね。
実は、体調不良で休みがちな同僚への対応は、適切な知識と理解があれば十分に対応できます。
体調不良による欠勤が建設的な対話のきっかけになれば、チーム全体の生産性低下にはつながりません。
そこで今回は、「仕事を体調不良で休む人の原因と対策」を深堀り解説します。
体調不良を迷惑だと思う前に、お互いの理解を深めながら、より良い職場環境を作っていきましょう。
- 体調不良による欠勤の背景要因を理解できる
- 職場全体への影響を客観的に把握できる
- 職場環境づくりのヒントを得られる
仕事を体調不良で休みすぎる主な原因

従業員の体調不良による休みには、多くの場合に目に見えない背景要因が存在します。
職場での過度な負担や生活習慣の乱れが重なり、心身の健康を損なってしまうケースが増加しています。
ここでは、頻繁な体調不良の裏に潜む代表的な原因を詳しく解説していきます。
- 睡眠不足や不規則な生活
- ストレスやプレッシャー
- 長時間労働や過重労働
- 不適切な食生活や運動不足
- 精神的・肉体的な過労
睡眠不足や不規則な生活
日々の睡眠時間が6時間未満の状態が続くと、免疫力が著しく低下して体調を崩しやすくなります。
睡眠不足により体内時計が乱れ、自律神経系のバランスが大きく崩れてしまうためです。
たとえば、深夜までスマートフォンを見続けることで、質の良い睡眠が取れず、翌日に強い倦怠感や頭痛を感じることがあります。
生活リズムの乱れは、体調不良の大きな要因となるのです。
ストレスやプレッシャー
過度なストレスは、自律神経系に悪影響を及ぼし、様々な身体症状として現れやすくなります。
ストレスホルモンの一つであるコルチゾールが慢性的に分泌され続けることで、免疫機能が低下してしまうためです。
たとえば、締切に追われる毎日が続くと、不眠や胃の不調、めまいなどの症状が出始め、最終的に出社できない状態にまで追い込まれます。
心理的なプレッシャーは、確実に身体症状として表れることを理解する必要です。
長時間労働や過重労働
一日の労働時間が10時間を超える状態が続くと、心身の回復が追いつかず、深刻な体調不良を引き起こします。
長時間の緊張状態により、体が休息モードに切り替わる機会を失ってしまうためです。
具体的には、残業が週に20時間を超えるような状況が続くと、慢性的な疲労が蓄積され、突然の発熱や激しい頭痛に見舞われることがあります。
過重労働は身体に大きな負担をかけ、重篤な健康被害を引き起こす可能性があるでしょう。
不適切な食生活や運動不足
栄養バランスの崩れた食事と慢性的な運動不足は、体の抵抗力を著しく低下させる原因となります。
必要な栄養素が不足し、代謝機能が低下することで、病気への抵抗力が弱まってしまうためです。
たとえば、昼食を毎日コンビニ弁当で済ませ、帰宅後はすぐに就寝するような生活を続けていると、徐々に体力が低下し、些細な環境変化でも体調を崩すようになります。
不適切な生活習慣は、長期的な健康状態に深刻な影響を及ぼすでしょう。
精神的・肉体的な過労
心身の疲労が蓄積されると、突然の体調不良や慢性的な不調に陥りやすくなります。
過度な負荷により自己回復機能が低下し、心身のバランスが大きく崩れてしまうためです。
仮に、新規プロジェクトの立ち上げ期に休日出勤が続き、さらに精神的なプレッシャーも重なると、突然のパニック発作や重度の不眠に悩まされることがあります。
過労状態は、心身の健康に重大な影響を及ぼすでしょう。
すぐ体調を崩す人を迷惑だと思うワケ

職場での体調不良による欠勤は、個人の問題だけでなく、組織全体に大きな影響を及ぼします。
特に短期間で頻繁に発生する体調不良は、生産性や職場の雰囲気を著しく低下させる要因となっています。
ここでは、体調不良による欠勤が周囲に与える具体的な影響について解説します。
- 仕事の進行が遅れる
- チームの効率が低下する
- 誰かが穴埋めしなければいけない
- 連絡や調整の手間が増える
- 予測できないリスクが増える
仕事の進行が遅れる
突然の欠勤により、計画されていた業務スケジュールに大きな遅延が発生してしまいます。
その人が担当していた重要な業務が一時的にストップしてしまい、プロジェクト全体の進行に支障をきたすためです。
たとえば、チーム内で唯一の経理担当者が体調不良で休むと、支払い処理や請求書の発行が滞り、取引先との関係にも影響が出てしまいます。
予定されていた業務の遅延は、組織全体の生産性低下につながるでしょう。
チームの効率が低下する
一人の体調不良による欠勤は、チーム全体の業務効率を大きく低下させる原因となります。
チームメンバー間の連携が乱れ、通常の業務フローが維持できなくなってしまうためです。
具体的には、3人チームで進めているプロジェクトで1人が休むと、残りのメンバーは通常業務に加えて情報共有や進捗確認にも時間を取られ、本来の業務に集中できなくなります。
業務効率の低下は、チーム全体のモチベーション低下にもつながるでしょう。
誰かが穴埋めしなければいけない
急な欠勤が発生すると、他のメンバーが代わりに業務を引き受けざるを得ない状況が生まれます。
期限の定められた業務や日常的な定型業務は、たとえ担当者が休んでも誰かが対応しなければならないためです。
たとえば、営業担当者が体調不良で休むと、重要な商談や顧客対応を他のメンバーが急遽引き継ぐことになり、その人の本来の業務にしわ寄せが行きます。
予定外の業務負担は、代替要員の心身にも悪影響を及ぼします。
連絡や調整の手間が増える
体調不良による欠勤は、関係者間での連絡調整に多大な時間と労力を要します。
急な欠勤に対応するため、業務の引き継ぎや予定の変更、関係者への連絡などが生じるためです。
仮に、プロジェクトリーダーが体調不良で休む場合、チームメンバーは取引先との打ち合わせの日程調整や、社内での代替者の選定など、複数の調整業務に追われることになります。
突発的な連絡調整は、業務の中断を招き、生産性を著しく低下させるでしょう。
予測できないリスクが増える
頻繁な体調不良による欠勤は、ビジネス上の予期せぬリスクを増大させます。
重要な業務の遂行が不安定になり、顧客対応や納期遵守などに支障をきたすからです。
たとえば、システム開発プロジェクトの核となるエンジニアが度々体調を崩して休むと、品質管理が不十分となり、重大なシステム障害を引き起こすリスクが高まります。
予測不能な事態の発生は、組織の信頼性と持続的な成長を脅かす要因となるでしょう。
体調不良でよく休む社員の末路とは

頻繁な体調不良による欠勤は、本人のキャリアや職場での立場に重大な影響を及ぼします。
一時的な症状の改善だけでなく、長期的な視点での対策が必要不可欠です。
ここでは、体調不良による度重なる欠勤がもたらす深刻な結果について解説していきます。
- 信頼を失う
- キャリアの停滞
- スキルアップしない
- 職場で孤立する
- 退職に追い込まれる
信頼を失う
度重なる体調不良による欠勤は、上司や同僚からの信頼を大きく損なうことになります。
急な欠勤が重なることで、仕事の依頼や重要な役割の割り当てを周囲が躊躇するためです。
たとえば、重要なプレゼンテーションを任されていた社員が当日に体調不良で休むことが続くと、クライアントからのクレームにつながり、組織全体の信用問題に発展することがあります。
一度失った信頼を取り戻すには、長期間の地道な努力が必要となるでしょう。
キャリアの停滞
体調不良による頻繁な欠勤は、昇進や昇給の機会を失うリスクを高めます。
体調管理ができていない社員に対して、より大きな責任や重要な職務を任せることが難しいと判断されるためです。
具体的には、年間の欠勤日数が同僚の2倍以上ある場合、人事評価で低い評価を受け、昇格試験の受験資格すら得られないケースもあります。
評価の低下は、長期的なキャリア形成に深刻な影響を及ぼすでしょう。
スキルアップしない
頻繁な体調不良は、業務経験の蓄積や新しいスキルの習得を妨げます。
体調不良による欠勤が重なることで、重要なプロジェクトへの参加機会が減少し、実践的な学習の場を失ってしまうためです。
仮に、新規システムの導入プロジェクトで体調を崩して長期休暇を取得すると、新技術の習得機会を逃し、市場価値の高いスキルを身につけることができません。
スキル不足は、将来的な転職や職務選択の幅を狭めることになるでしょう。
職場で孤立する
度重なる体調不良は、職場での人間関係を悪化させ、孤立を招きます。
同僚への負担増加や約束の不履行が重なることで、次第に周囲から距離を置かれるようになるためです。
たとえば、チーム内での飲み会や親睦会に体調不良を理由に参加できないことが続くと、重要な情報共有の場から外れ、次第にコミュニケーションが希薄になっていきます。
職場での孤立は、メンタルヘルスの悪化にもつながるでしょう。
退職に追い込まれる
深刻な体調不良が続く場合、最終的に退職を余儀なくされるケースがあります。
長期的な業務パフォーマンスの低下や、周囲への影響が無視できないレベルに達してしまうためです。
具体的には、年間の病欠が3ヶ月を超えるような状況が続くと、会社から休職を命じられ、復職のめどが立たない場合は自然退職となるかもしれません。
体調不良による退職は、次のキャリアにも大きな影響を及ぼすでしょう。
体調不良でよく休む人への上手な接し方

職場で体調不良を訴える同僚に対しては、適切なサポートと理解が重要です。
ただし、過度な干渉や無理な励ましは、かえって状況を悪化させる可能性があります。
ここでは、体調不良に悩む同僚との効果的なコミュニケーション方法について解説します。
- 健康を気遣う言葉をかける
- 休むことの重要性を理解する
- 業務の調整をサポートする
- 積極的にコミュニケーションを取る
- 感情的に批判しない
健康を気遣う言葉をかける
体調不良で休みがちな同僚には、適切なタイミングで体調を気遣う言葉をかけることが大切です。
本人が孤立感を感じることなく、職場での居場所を確保できるようにサポートする必要があるためです。
たとえば、休暇明けの出社時に「体調は少し良くなりましたか?」と、押しつけがましくない程度に声をかけることで、本人の不安や緊張を和らげることができます。
相手の体調を気遣う姿勢が、円滑な職場復帰を後押しするでしょう。
休むことの重要性を理解する
体調不良による休暇は、心身の回復に必要不可欠な時間であることを認識する必要があります。
無理な出社を促すことで、かえって症状が悪化し、より長期の休養が必要になってしまうからです。
具体的には、体調不良を訴える同僚が休暇を申請した際には、「ゆっくり休んで回復に専念してください」と伝え、休養の必要性を理解していることを示します。
体調管理の重要性を理解することが、健全な職場環境の維持につながるのです。
業務の調整をサポートする
体調不良の同僚の業務負担を適切に調整し、無理のない範囲でサポートすることが重要です。
急な体調不良時にも業務が滞りなく進むよう、チーム全体でバックアップ体制を整える必要があります。
たとえば、体調不良が予想される同僚には、あらかじめ業務の優先順位を確認し、緊急性の高いタスクを優先的にフォローできる体制を整えておきます。
適切な業務調整は、本人の負担軽減と職場全体の生産性維持に寄与するでしょう。
積極的にコミュニケーションを取る
体調不良の同僚とは、日常的なコミュニケーションを通じて、信頼関係を構築することが大切です。
相手が体調の変化や困りごとを相談できる関係性を築くことで、早期の対応が可能になります。
仮に、同僚が体調不良の兆候を見せた際には、「最近、忙しそうに見えますが、大丈夫ですか?」と、自然な形で声をかけ、状況を確認します。
日頃からの良好なコミュニケーションが、問題の早期発見と解決を可能にするでしょう。
感情的に批判しない
体調不良で休みがちな同僚に対して、感情的な批判や非難は避けるべきです。
批判的な態度が本人のストレスを増大させ、職場での孤立を招く可能性があるためです。
具体的には、同僚の体調不良による欠勤について、「また休むの?」「いつも具合が悪いね」といった否定的な発言を控え、建設的な対話を心がけます。
理解と共感に基づくアプローチが、職場の良好な人間関係を維持するのです。
すぐ体調を崩す人ができる仕事の取り組み方

体調管理に不安を抱える人は、自身の健康状態を考慮した無理のない働き方を心がける必要があります。
ここでは、体調を崩しやすい人が実践できる、持続可能な仕事への取り組み方について解説します。
適切な対策を講じることで、仕事と健康の両立が可能になります。
- 無理をせず休養を優先する
- 業務を分担して調整する
- 小さな目標を設定する
- 定期的に病院に行く
- ストレス管理を意識する
無理をせず休養を優先する
体調の変化を感じたら、早めの休養を取ることで重症化を防ぐことができます。
軽い症状の段階で適切な休養を取ることで、回復に要する時間を最小限に抑えることができるためです。
たとえば、朝起きた時に体調の不調を感じたら、無理に出社せず、半日休暇や在宅勤務を活用して体調管理を優先することで、症状の悪化を防ぐことができます。
体調管理を優先する姿勢が、長期的な就業継続につながるでしょう。
業務を分担して調整する
自分の体調と業務量を考慮し、適切な業務分担を心がけることが重要です。
一人で抱え込まず、チームメンバーと協力することで、急な体調不良時にも業務が滞らない体制を作れるためです。
具体的には、自分が担当するプロジェクトの進捗状況や課題を常に共有し、他のメンバーでもカバーできる部分は分担しておくことで、リスクを最小限に抑えられます。
業務の適切な分担は、個人とチーム双方の負担軽減に効果的です。
小さな目標を設定する
無理のない範囲で達成可能な小さな目標を設定し、段階的に取り組むことが効果的です。
大きな目標を細分化することで、体調管理をしながら着実に成果を積み上げることができるためです。
仮に、月間の売上目標を達成する必要がある場合、週単位や日単位の具体的な行動目標に分解し、体調と相談しながら優先順位をつけて取り組みます。
現実的な目標設定が、安定した業務遂行を可能にするでしょう。
定期的に病院に行く
予防的な健康管理として、定期的な医療機関への通院を習慣化することが大切です。
専門医による適切な診断と治療を受けることで、体調不良の予防や早期発見が可能になるためです。
たとえば、月に一度の定期検診を設定し、体調の変化を医師に相談することで、重症化する前に適切な対処法を見つけることができます。
継続的な医療相談が、安定した健康管理を実現するでしょう。
ストレス管理を意識する
日常的なストレス管理を行い、心身の健康維持に努めることが重要です。
適切なストレス解消法を見つけることで、体調不良のリスクを大幅に軽減できるためです。
具体的には、仕事終わりに軽い運動を取り入れたり、休日にはリラックスできる趣味の時間を確保したりすることで、ストレスの蓄積を防ぐことができます。
効果的なストレス管理が、安定した業務パフォーマンスを支えるのです。
仕事を体調不良で休みすぎたときの疑問

体調不良による度重なる欠勤は、当事者だけでなく周囲の人々にも大きな影響を与えます。
多くの人が抱える不安や疑問について、労働法規や実務的な観点から解説します。
正しい知識を持つことで、適切な判断と対応が可能になります。
- 体調不良でよく休む人はクビになる?
- 仕事で休みすぎと言われるのは何日から?
- 仕事を休む人のフォローで疲れる場合もある?
- パートは体調不良で休みすぎるとシフトが減る?
- 会社を休みすぎて気まずいなら辞めるべき?
体調不良でよく休む人はクビになる?
正当な理由のある体調不良による欠勤では、法律上、安易な解雇は認められていません。
労働安全衛生法により、企業には従業員の健康管理に配慮する義務が課せられているためです。
たとえば、医師の診断書を提出し、適切な休職手続きを踏んでいる場合、会社は治療に必要な休養期間を認める必要があり、この期間中の解雇は違法となります。
体調不良による休職は、法的に保護された労働者の権利です。
仕事で休みすぎと言われるのは何日から?
一般的に、年間の病気休暇が10日を超えると、人事考課や業務評価に影響を及ぼす可能性が高まります。
多くの企業で年次有給休暇の付与日数が年間20日程度であり、その半分を超える欠勤は業務効率に大きな影響を与えると判断されるためです。
具体的には、3ヶ月間で累計15日以上の欠勤がある場合、上司との面談が設定され、就業継続に関する協議が始まることがあります。
休暇日数の基準は、企業や職種によって異なることを理解しておく必要があるでしょう。
仕事を休む人のフォローで疲れる場合もある?
同僚の頻繁な欠勤により、代替要員の心身の疲労が蓄積することは十分にあり得ます。
通常業務に加えて欠勤者の業務もこなす必要があり、長期的には過重な負担となってしまうためです。
仮に、営業部門で5人チームの1人が月に5日以上休むような状況が続くと、残りのメンバーは自身の担当顧客に加えて、欠勤者の顧客対応も行う必要があります。
そのため、フォローする側の健康管理も重要な課題となるでしょう。
パートは体調不良で休みすぎるとシフトが減る?
シフト制の職場では、体調不良による欠勤が続くと、結果的にシフト回数が減少する可能性があります。
安定した人員配置を確保するため、出勤の確実性を考慮してシフトが組まれるためです。
たとえば、月間のシフトのうち3分の1以上をキャンセルするような状況が続くと、店舗運営の安定性を確保するため、シフトの優先順位が下がってしまうことがあります。
シフトの減少は、収入面での影響も考慮する必要があるのです。
会社を休みすぎて気まずいなら辞めるべき?
体調不良による欠勤が続いているからといって、即座に退職を選択するのは適切ではありません。
体調不良の根本的な原因を特定し、改善策を講じることで、就業継続が可能になる場合が多いためです。
具体的には、産業医との相談や人事部門への状況説明を行い、配置転換や業務内容の調整など、働き方の見直しを検討することで、状況が改善するケースもあります。
退職は最終手段として、まずは現状改善の可能性を探ることが重要です。
体調不良で休みすぎる人がいた職場の体験談

筆者は以前、体調不良を理由に頻繁に休む同僚がいる部署で働いていました。
最初は「また休むの?」と苛立ちを感じ、その人への不信感が募っていったのを覚えています。
特に、重要な締め切りが近い時期に休まれると、チーム全体が混乱し、私を含めた他のメンバーが残業で対応せざるを得ませんでした。
しかし、ある日その同僚が涙ながらに、持病の治療と仕事の両立に悩んでいることを打ち明けてくれました。
それまで「単なる仮病」だと思い込んでいたので、深く反省することになったのです。
その後、チーム内で話し合いの場を設け、業務の分担方法や情報共有の仕組みを見直しました。
この経験から、安易な批判や決めつけは問題の解決にならないこと、そして、適切なサポート体制があれば、多様な働き方が実現できることを学びました。
今では、体調不良で休む必要がある人への理解を深め、建設的な解決策を考えられるようになっています。
まとめ
体調不良による頻繁な欠勤は、本人だけでなく職場全体に大きな影響を及ぼします。
しかし、これは適切な対応と相互理解によって改善できる課題でもあります。
体調を崩しやすい背景には、睡眠不足や不規則な生活、ストレス、長時間労働など、様々な要因が存在します。
その結果、業務の遅延やチーム効率の低下、予測できないリスクの増加といった問題が発生し、最悪の場合、信頼低下や職場での孤立につながることもあります。
しかし、このような状況は決して避けられない問題ではありません。
体調不良の同僚に対して健康を気遣う言葉をかけ、適切な業務調整をサポートすることで、より良い職場環境を築くことができます。
また、体調を崩しやすい人自身も、無理をせず休養を優先しながら、小さな目標設定や定期的な通院を心がけることで、安定した就業継続が可能になります。
重要なのは、お互いを理解し、支え合える関係性を築くことです。
体調管理と業務の両立は決して簡単ではありませんが、職場全体で取り組むべき重要な課題として捉え、前向きな改善を目指していきましょう。