ビルメンテナンス業界への転職は、誰もが慎重になる選択ですよね。
給与が低いと生活が苦しくなってしまうし、将来のキャリアに不安を感じる気持ちよくわかります。
できることなら、後悔のない転職をしたいですよね。
実は、ビルメン業界の実態を正しく理解するだけで、適切な判断ができます。
業界の特徴や課題が明確になれば、ミスマッチによる失敗にはなりません。
そこで今回は、「ビルメンはやめとけと言われる真相」をご紹介します。
ビルメンに興味がある方は、この記事を参考に慎重に判断するようにしましょう。
- 業界が抱える7つの本質的な課題を理解できる
- 大手と中小企業の待遇の違いを把握できる
- 転職前に確認すべきポイントが明確になる
ビルメンはやめとけと言われる理由

ビルメンテナンス業界では、労働条件や職場環境に関する課題が数多く指摘されています。
業界特有の構造的な問題により、長期的なキャリア形成が難しいとされ、転職前に慎重な検討が必要です。
また、近年の人手不足により、一人当たりの業務負担が増加傾向にあることも懸念されています。
- 労働環境が厳しい
- 給与が低め
- キャリアの成長が限られる
- 繁忙期のストレスが大きい
- 職場の人間関係が厳しい
労働環境が厳しい
施設管理の現場では、日々過酷な労働環境にさらされることが常態化しています。
業務内容が多岐にわたり、一人で複数の業務をこなす必要があるためです。
たとえば、エアコンの不具合対応中に清掃要請が入り、さらに警備業務も並行して行わなければならない状況が日常的に発生します。
このような労働環境の厳しさは、長期的な就業を考える上で大きな懸念材料です。
給与が低め
ビルメン業界の給与水準は、他の施設管理関連業種と比較しても低い傾向にあります。
業界全体の単価の低さと、競争入札による価格低下が主な原因となっているためです。
具体的には、20代後半で月給20万円程度、30代でも25万円程度に留まることがあり、昇給も緩やかな傾向にあります。
このような給与水準では、将来的な生活設計を立てることが困難です。
キャリアの成長が限られる
ビルメン業界では、専門的なスキルを習得しても、それが十分なキャリアアップにつながらないのが現状です。
業務の専門性が高まっても、給与や待遇に反映されにくい業界構造があるためです。
仮に、電気や空調の資格を取得しても、実際の給与アップは数千円程度に留まることがあり、技術向上の努力が報われにくい状況が続いています。
キャリアの成長が限られるため、モチベーション低下の大きな要因となっています。
繁忙期のストレスが大きい
繁忙期には通常の2倍以上の業務量をこなす必要があり、精神的な負担が著しく増加します。
テナントの入れ替わり時期や定期点検の時期が重なると、業務が著しく集中するためです。
たとえば、大型商業施設では年末の大掃除と設備点検が重なり、一日12時間以上の勤務が1週間以上続くことも珍しくありません。
繁忙期のストレスが大きいため、心身の健康に深刻な影響を及ぼすでしょう。
職場の人間関係が厳しい
ビルメン現場では、複雑な人間関係のストレスに直面することが日常的になっています。
委託先や派遣先との多重の上下関係が存在し、それぞれの要求に応える必要があるためです。
例として、所属企業の上司、常駐先の管理者、テナント従業員など、異なる立場の人々からの相反する要求に対応しなければならない状況が頻繁に発生します。
こ職場の人間関係の複雑さは、日々のストレス要因となるでしょう。
ビルメンは生活できないと言われるワケ

ビルメン業界は、慢性的な人手不足にもかかわらず、待遇改善が進んでいない状況が続いています。
特に中小企業では、価格競争の激化により収益が圧迫され、従業員への還元が難しい状況です。
このため、生活の安定性を求める若手従業員の定着が困難になっています。
- 低い給与水準
- 残業代が少ない
- 福利厚生が不十分
- 不安定な勤務形態
- 負担が大きい仕事量
低い給与水準
ビルメン業界の給与水準は、全産業平均と比較して20%以上低い水準にとどまっています。
大手企業との価格競争により、人件費を抑える必要に迫られているためです。
たとえば、入社5年目で手取り18万円程度、10年選手でも25万円に届かないケースが見られます。
このような給与水準では、特に都市部での生活維持が困難です。
残業代が少ない
残業時間が実際の労働時間に比べて少なく計上される場合があります。
サービス残業が慣習化しており、正当な残業代の請求がしづらい職場環境があるためです。
具体的には、朝の準備作業や夕方の引き継ぎ時間が労働時間として認められず、月に10時間以上のサービス残業が発生することも珍しくありません。
このような残業代の未払い問題は、実質的な収入減少につながっているのです。
福利厚生が不十分
福利厚生制度が最低限の法定基準を満たすのみで、従業員の生活をサポートする体制が整っていません。
業界の競争激化により、福利厚生への投資が後回しにされているためです。
例として、社会保険は完備されているものの、住宅手当や家族手当などの生活支援制度が不在で、従業員の生活基盤を支える制度が不足している状態が続いています。
このような福利厚生の不足は、長期的な生活設計を困難にするでしょう。
不安定な勤務形態
シフト制による不規則な勤務が一般的で、生活リズムの確保が困難な状況です。
施設の運営時間に合わせた勤務が求められ、急なシフト変更も頻繁に発生するためです。
たとえば、夜勤と日勤が不規則に組み合わされ、体調管理が難しい上に、私生活の予定も立てづらい状況が常態化しています。
不安定な勤務形態は、ワークライフバランスの実現を妨げるでしょう。
負担が大きい仕事量
一人あたりの業務量が過剰で、日常的に高負荷な労働を強いられています。
人員不足が常態化しており、一人で複数人分の仕事をこなす必要があるためです。
仮に8時間勤務のシフトであっても、実際には休憩時間も十分に取れず、常に走り回っている状態で業務をこなさなければなりません。
負担が大きい仕事量は、長期的な就労を困難にする要因となるでしょう。
ビルメンで頭おかしいと思われる事例

ビルメンテナンス業界では、常識的に考えて理解しがたい状況が発生しやすいです。
現場レベルでの無理な要求や、管理体制の不備により、従業員の健康や安全が脅かされるケースが珍しくありません。
このような状況は、業界全体の信頼性を低下させる要因となっています。
- 無理な作業量
- 急なシフト変更
- 過剰な責任
- 無茶な清掃指示
- 設備不良の放置
無理な作業量
物理的に不可能と思われるほどの、無理な作業量が要求されるケースがあります。
人員削減により一人あたりの担当面積が増加し続け、基準作業時間内での作業完了が困難になっているためです。
例として、一日の清掃面積が3000平米を超え、移動時間を考慮すると1平米あたり1分も掛けられない状況で作業を強いられることがあります。
このような非現実的な作業量の要求は、作業品質の著しい低下を招いています。
急なシフト変更
シフト変更の連絡が直前になされ、個人の生活が著しく侵害される事態が頻発しています。
人員不足による急な欠員補充や、突発的な業務対応の必要性が適切に管理されていないためです。
たとえば、前日の夜に「明日の朝から出勤してください」という連絡が入り、予定していた用事をすべてキャンセルせざるを得ない状況が考えられます。
急で理不尽なシフト変更は、従業員の私生活を著しく阻害するでしょう。
過剰な責任
現場スタッフに対して、権限や待遇に見合わない過度な責任が押し付けられています。
管理職不在時の判断や、専門外の業務対応まで、すべて現場スタッフに責任が転嫁されるためです。
具体的には、深夜の設備トラブル時に、技術資格を持たない清掃スタッフが対応を迫られ、失敗した場合の責任も負わされるような事態が発生しています。
このような責任の押し付けは、スタッフの精神的負担を著しく増大させるでしょう。
無茶な清掃指示
施設管理者からの非現実的な清掃要求により、スタッフが危険な作業を強いられることがあります。
クレーム対応や見栄えを重視するあまり、安全性や作業基準が無視されているためです。
例として、高所での窓清掃を軽装備で行うよう指示されたり、強酸性洗剤の使用を適切な保護具なしで要求されたりするケースになります。
無茶な清掃指示は、重大な労働災害につながる可能性があるでしょう。
設備不良の放置
明らかな設備の不具合や故障が、長期間にわたって放置される事態があります。
予算不足や管理者の無関心により、必要な修理や更新が先送りにされ続けているためです。
たとえば、エレベーターの異音や空調設備の不具合が何ヶ月も放置され、その間の応急対応や苦情対応を現場スタッフが強いられ続けるという状況になります。
このような設備管理の杜撰さは、スタッフの業務負担を不必要に増大させるでしょう。
ビルメンは楽すぎと思う人の意見

ビルメンテナンス業界は厳しい声が多いものの、一方で「楽すぎ」という意見もあります。
なぜきついはずのビルメンが楽なのでしょうか?その理由を見ていきましょう。
- 業務内容が単純
- 体力的に楽
- 定時で終わることが多い
- 職場の雰囲気がゆるい
- 特別なスキルは不要
業務内容が単純
日常的な施設管理業務は、決められた手順に従って実施される単調な作業が中心となっています。
作業手順がマニュアル化されており、複雑な判断や専門的な知識を必要とする場面が限られているためです。
たとえば、清掃業務では決められた順序で同じ動作を繰り返すことが多く、警備業務でも定期的な巡回と記録が主な仕事となっています。
業務内容が単純であるため、誰でもできると言っても過言ではないでしょう。
体力的に楽
一般的な施設管理業務では、重労働や過度な身体的負担が少ないと考えられています。
最新の清掃機器や作業補助具の導入により、肉体的な負担が軽減されているためです。
例として、床清掃は自動洗浄機を使用し、ゴミ収集も台車を活用するなど、重い物を持ち上げたり運んだりする作業が少なくなっています。
このような作業環境の改善は、確かに身体的負担を軽減させてくれるでしょう。
定時で終わることが多い
通常の業務は、決められた時間内に完了するよう計画されており、残業が少ない傾向にあります。
作業スケジュールが時間単位で細かく設定され、定時内での業務完了が基本方針となっているためです。
具体的には、朝8時から夕方5時までの間で作業が組まれており、特別な案件がない限り、時間通りに退勤できることが多い状況です。
このような定時退社の実現は、ワークライフバランスの面で有利に働くでしょう。
職場の雰囲気がゆるい
現場では比較的自由な雰囲気があり、厳格な管理体制が敷かれていない場合があります。
直接の監督者が常駐していないことも多く、ある程度の裁量を持って業務を進められるためです。
たとえば、休憩時間の取り方に柔軟性があったり、作業の順序を自分で調整できたりと、細かな規則に縛られない職場環境が見られます。
職場の雰囲気がゆるいため、働きやすさの一因となっています。
特別なスキルは不要
入社時点での専門的なスキルや資格がなくても、基本的な業務をこなすことが可能です。
多くの作業が標準化されており、基本的な研修を受ければ誰でも始められる仕組みが整っているからです。
仮に未経験者であっても、先輩社員による指導のもと、清掃や受付、簡単な設備点検などの基本業務から段階的に覚えていくことができます。
特別なスキルが必要ないことから、新規就労者にとって魅力的な要素となっています。
ビルメンとして働く女性への注意点

近年、ビルメンテナンス業界でも女性の活躍が期待されています。
しかし、業界特有の課題により、女性が働く上での障壁も存在します。
安全面や健康面での配慮が必要な職場環境であり、就職前に十分な情報収集と検討が重要です。
- 体力的な負担が大きい
- 夜勤や不規則な勤務
- 男性中心の職場環境
- 安全対策を重視
- ストレスを溜め込まない
体力的な負担が大きい
女性スタッフの体力的な負担は、想像以上に大きいのが現状です。
重い清掃機器の運搬や、長時間の立ち仕事が日常的に発生するためです。
たとえば、20キロ以上ある床洗浄機の移動や、重いゴミ袋の運搬など、女性には負担の大きい作業が発生します。
体力的な負担が大きいため、限界を考慮した業務分担を意識することが重要です。
夜勤や不規則な勤務
女性スタッフでも、深夜勤務や変則シフトが発生しています。
24時間稼働の施設では、夜間帯の人員配置も必要となるためです。
具体的には、夜10時から翌朝6時までの夜勤シフトや、早朝5時からの早出勤務なども珍しくありません。
生活のリズムが乱れやすいため、就業前に勤務時間帯の確認が重要です。
男性中心の職場環境
現場では依然として男性優位の雰囲気が残っています。
界全体が男性中心で発展してきた歴史的背景があるためです。
例として、更衣室やトイレなどの女性用設備が不十分な職場も多く、休憩スペースも男性を基準に設計されていることがあります。
男性中心の職場環境になるため、事前に確認することが賢明です。
安全対策を重視
残念ながら、女性スタッフの安全確保が十分でない現場が散見されます。
危険作業や夜間作業における安全配慮が不足しているためです。
仮に夜間の警備業務や高所作業を任された場合、男性スタッフと同様の対応を求められ、危険な状況に遭遇することもあります。
女性でも危険な目に遭う可能性はあるため、安全管理体制の確認を怠らないようにしましょう。
ストレスを溜め込まない
女性スタッフは男性よりも、精神的負担が蓄積しやすい環境です。
セクハラやパワハラのリスクが存在し、嫌な目に遭うことも珍しくありません。
たとえば、男性客からの不適切な言動や、男性上司からの過度な要求など、精神的なストレスの原因となる出来事が発生しています。
ストレスが溜まりやすいため、心身の健康管理を最優先に考えて行動してください。
ビルメンに関するよくある疑問

ビルメンテナンス業界では、様々な疑問や不安を抱える方が多くいます。
業界の実態は外部からは見えづらく、誤解や偏見も存在するのが実情です。
そこで、ビルメンに関するよくある疑問をご紹介します。
- ビルメンの平均年収は?
- ビルメンに必要な資格は?
- ビルメンの離職率は高い?
- ビルメンになって後悔する人は?
- ビルメンは性格悪い人が多い?
- ビルメンはやばい人が多い?
- ビルメンの彼氏は恥ずかしい?
ビルメンの平均年収は?
ビルメンの平均年収は、350~400万円程度と低い傾向にあります。
参考:ビルメンテナンスの仕事の年収・時給・給料|求人ボックス
大手企業と中小企業で待遇に大きな格差があり、全体の年収水準を押し下げているためです。
たとえば、大手企業では400万円以上の年収も珍しくありませんが、中小企業では300万円程度にとどまるケースが発生します。
給与水準は企業規模や勤務地域によって大きく異なるため、注意してください。
ビルメンに必要な資格は?
業務に特別な資格は必要ありませんが、キャリアアップには複数の資格取得が求められます。
設備管理や監督業務を行う際には、電気や空調などの専門資格が必要となるためです。
例として、第二種電気工事士や危険物取扱者、ボイラー技士など、設備の種類に応じた資格を取得する必要があります。
資格取得することで、昇進や収入アップが期待できるでしょう。
ビルメンの離職率は高い?
業界平均の離職率は年間30%を超えており、特に入社1年以内の早期離職が目立ちます。
労働条件や職場環境への不満が主な要因となり、若手従業員の定着が難しいためです。
具体的には、入社後3ヶ月以内に20%程度が退職し、1年以内には40%近くが離職すると言われています。
ビルメンの離職率は高いため、若手の定着率改善は業界全体の課題です。
ビルメンになって後悔する人は?
体力的な負担やシフト勤務の厳しさを甘く見ていると、後悔する可能性が高くなります。
実際に業務を始めてから厳しさに気づき、予想外の労働条件に不満を持つからです。
たとえば、求人票に記載された待遇と実態が異なる、キャリアアップの機会が少ない、体力的な負担が予想以上に大きいなどの理由で後悔する人が多く見られます。
入社してから後悔しないためにも、十分な企業研究が必要になるでしょう。
ビルメンは性格悪い人が多い?
職場の人間関係に対する不満や評判は、一般的な職場と比べて特に目立つものではありません。
むしろ、協調性や責任感を持った人材が多く、チームワークを重視する職場文化があるためです。
仮に一部の社員との関係が悪化しても、シフト制のため異なる時間帯で勤務することで対応できます。
一概に性格が悪い人が多いとは言えないため、決めつけないようにしましょう。
ビルメンはやばい人が多い?
一部の偏見や誤解により、そのような印象が広がっていますが、実態とは異なります。
むしろ、施設の安全管理や顧客対応を担う責任ある立場であり、一定の適性が求められるためです。
例として、防災センターや受付業務では、冷静な判断力や適切なコミュニケーション能力が必須とされ、厳格な採用基準が設けられています。
業界に対する偏見は、実態を正しく理解していない場合が多いのです。
ビルメンの彼氏は恥ずかしい?
職業に対する偏見や社会的評価の低さから、そのような不安を感じる方もいます。
しかし、施設の安全や快適さを支える重要な仕事であり、社会的な必要性は極めて高いです。
たとえば、オフィスビルや商業施設、病院など、私たちの生活に欠かせない場所の維持管理を担う専門職として、その価値は確実に認められています。
ビルメンの彼氏は恥ずかしくないため、自信を持って接しましょう。
ビルメンとして働く人の体験談
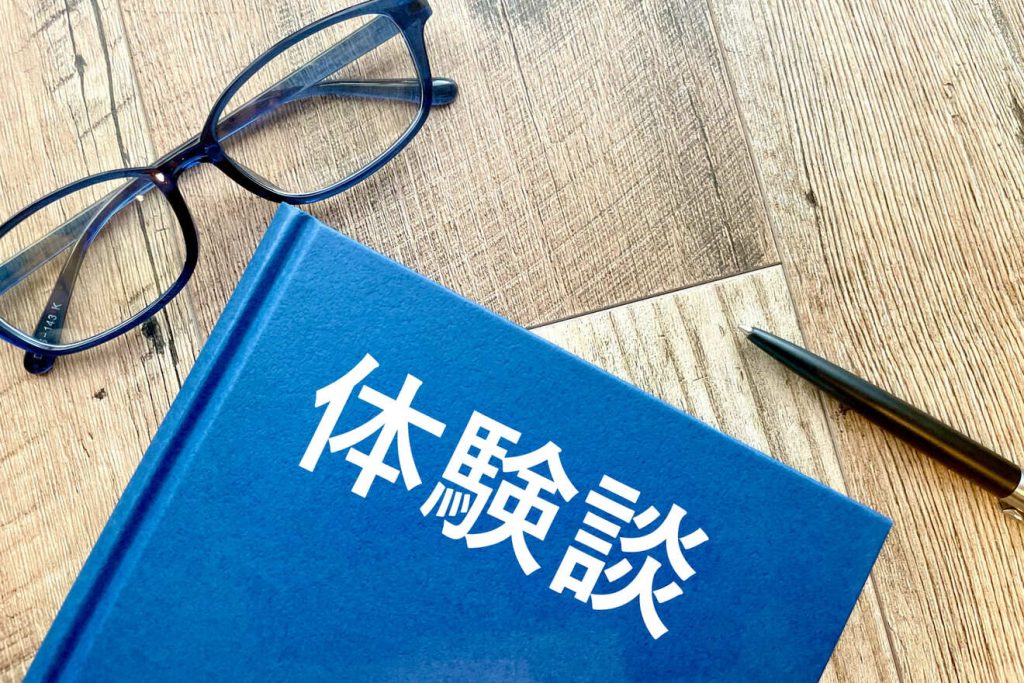
筆者は採用支援の仕事をしている中で、ビルメンテナンス現場で働く人から様々な体験談を聞く機会がありました。
特に印象的だったのは、40代の男性社員からの話です。
「入社3年目ですが、正直きつい仕事です。特に人手不足で、一人で何役もこなさないといけない。先週なんか、エアコンの点検中に清掃の応援要請が入って、その合間に警備室の代務も頼まれました。でも、定時で帰れるのが救いですね。以前の営業職は残業が当たり前でしたから」
と言う意見を聞き、体力的な負担はあるものの、ワークライフバランスは整えやすいと感じました。
また、20代の女性社員からは「夜勤があるのは覚悟していましたが、急なシフト変更が多くて困ります。でも、資格取得のサポートがあるので、将来のステップアップを目指しています」という意見も聞きました。
現場の生の声からは、確かに厳しい環境が伺えますが、同時にやりがいや将来性を見出している方も少なくないようです。
ビルメンはやめとけの総括
ビルメンテナンス業界では、確かに労働環境の厳しさや給与水準の低さ、キャリア成長の限界など、様々な課題が指摘されています。
特に、繁忙期のストレスや複雑な人間関係、残業代の少なさ、不十分な福利厚生など、生活面での不安要素も少なくありません。
また、無理な作業量や急なシフト変更、過剰な責任など、一般的には理解しがたい状況も存在します。
しかし一方で、定時で帰れる職場も多く、特別なスキルがなくても始められる間口の広さは、キャリアチェンジを考える方にとって魅力的な要素となっています。
実際、大手企業では400万円以上の年収も可能で、電気工事士やボイラー技士などの資格取得によるキャリアアップの道も開かれているのです。
重要なのは、入社前に職場環境や待遇を十分確認し、自身の価値観や生活設計に合った企業を選ぶことです。
ビルメンは社会に必要不可欠な仕事であり、その価値は確実に認められています。
業界研究を十分に行い、慎重に企業選びをすることで、充実したキャリアを築くことは十分可能でしょう。



