職場で事あるごとに「辞める」と言っているのに、なかなか辞めない人はいませんか。
毎回「辞める」と聞かされたら心配になるし、振り回されているという気持ちよくわかります。
できることなら、そんな人に惑わされずに自分のペースで仕事を続けたいですよね。
実は、辞める発言を繰り返す人の心理を理解することで冷静に対処できます。
相手の真意が分かれば、必要以上に動揺することはありません。
そこで今回は、「辞める辞めると言って辞めない人の心理と対処法」をご紹介します。
職場環境を改善させ、ストレスフリーで働けるようにしましょう。
- 辞める発言を繰り返す人の5つの心理パターンを理解できる
- 振り回されずに冷静に対処する具体的な方法がわかる
- 自分が辞める発言をした後の適切な撤回方法を学べる
辞める辞める言う人の5つの心理

職場で「辞める」と繰り返し言いながら実際には辞めない人には、さまざまな心理が働いています。
表面的な発言の裏には複雑な感情や思考が隠れており、その背景を理解することで適切な対応ができるでしょう。
- 周囲の注目や同情を引きたい
- 本気で辞めたいわけではない
- 自分の待遇や環境を変えたい
- 本当に辞めたいけど踏み出せない
- 「辞める」が口癖になっている
周囲の注目や同情を引きたい
「辞める」発言は周囲からの関心や同情を集める効果的な手段として使われがちです。
注目を浴びたい気持ちや、自分の状況を理解してもらいたい欲求が強い人ほど、この傾向が見られます。
たとえば、忙しい時期や人間関係で悩んでいる際に「もう辞めたい」と発言することで、同僚や上司からの心配や気遣いを引き出そうとします。
注目を集めたい心理から生まれる発言だと理解しておきましょう。
本気で辞めたいわけではない
辞める発言をする人の多くは、実際には現在の職場を離れる意思がありません。
不満やストレスを感じた際の感情的な反応として、「辞める」という言葉を使っているだけなのです。
具体的には、残業が続いた日や上司に叱られた後などに「もう辞める」と発言するものの、翌日には普通に出勤している状況が典型例です。
本心では現在の職場に留まりたいと考えている場合が多いのです。
自分の待遇や環境を変えたい
現状への不満を表現し、職場環境や待遇の改善を求める手段として辞める発言が使われることがあります。
直接的に改善を要求するよりも、辞める可能性をほのめかすことで変化を促そうとする心理です。
例として、給与や労働条件に不満がある際に「この待遇なら辞めるしかない」と発言し、会社側の対応を期待する行動が挙げられます。
改善要求の遠回しな表現として理解しておいてください。
本当に辞めたいけど踏み出せない
心の奥では転職や退職を望んでいるものの、実際の行動に移せない葛藤を抱えている場合もあります。
経済的不安や転職への恐怖心が強く、決断できずにいる状態で「辞める」発言を繰り返すのです。
仮に新しい職場が見つからない不安や、収入が途絶える心配から、退職の意思はあっても実行に移せずにいる人がこれに該当します。
本心では変化を望んでいても行動できない心理状態なのです。
「辞める」が口癖になっている
長期間にわたって辞める発言を繰り返すうちに、それが習慣的な口癖となってしまうケースもあります。
特別な意味を持たずに、反射的に「辞める」という言葉が出てしまう状態です。
例として、ちょっとした業務上の問題が発生するたびに「もう辞めよう」と自然に口に出してしまう人が該当します。
口癖として定着してしまい、深い意味がない場合も多いでしょう。
辞める辞めると言って辞めない人の理由

辞める発言を繰り返す人には、実際に退職しない具体的な理由が存在します。
表面的な言葉とは裏腹に、現実的な問題や心理的な障壁が行動を阻んでいるのです。
これらの理由を把握することで、相手の真意を理解できるでしょう。
- 本音では辞めたくない
- 転職に自信がない
- 決断力が乏しい
- 家庭の事情がある
- 重要な仕事が続いている
本音では辞めたくない
辞める発言とは正反対に、心の底では現在の職場を離れたくない気持ちが強い場合があります。
慣れ親しんだ環境や人間関係への愛着が、退職への抵抗感を生み出しているのです。
たとえば、同僚との関係が良好で職場の雰囲気に満足している人が、一時的な不満から「辞める」と言いながらも、実際には居心地の良さを手放したくないと感じています。
本心では現在の環境を大切に思っているからこそ辞められないのです。
転職に自信がない
自分のスキルや経験に不安を感じ、転職市場での競争力に自信を持てない状況です。
新しい職場で通用するかどうかの不安が、退職への一歩を踏み出すことを困難にしています。
具体的には、専門性の低い業務に従事している人や、長期間同じ職場にいる人が「他では通用しないかもしれない」と考え、転職をためらう傾向があります。
自信の欠如が現状維持を選択させる要因となっているのです。
決断力が乏しい
重要な判断を下すことが苦手で、退職という大きな決断を避け続けている状態です。
変化への恐怖心や失敗への不安が強く、現状を変える勇気を持てずにいます。
例として、何事においても他人の意見に頼りがちで、自分で重要な選択をした経験が少ない人が、退職という人生の転機に直面して迷い続けるケースが挙げられます。
決断を先延ばしにする習慣が退職を阻んでいるのです。
家庭の事情がある
経済的な責任や家族の状況が、退職を現実的に困難にしている場合があります。
収入の途絶や転職活動による不安定さが、家計に与える影響を考慮して踏み切れずにいるのです。
仮に住宅ローンや子どもの教育費などの固定支出があり、安定した収入を手放すリスクを取れない状況の人がこれに該当します。
家族への責任感が退職を困難にしている現実的な理由です。
重要な仕事が続いている
担当している業務の責任感や、プロジェクトの完了までは辞められないという職業意識が働いています。
中途半端な状態で退職することへの罪悪感や、同僚への迷惑を考慮して時期を先送りしているのです。
例として、大型プロジェクトのリーダーを務めている人や、後任の育成が必要な専門業務を担当している人が「区切りがつくまでは」と退職を延期し続ける状況があります。
責任感の強さが退職のタイミングを逃す原因となっているでしょう。
辞めると騒ぐ人に振り回されないコツ

職場で辞める発言を繰り返す人に対しては、適切な距離感と対応方法を身につけることが重要です。
感情的になったり過度に反応したりせず、冷静に対処することで自分自身を守れます。
効果的な対応策を実践して、職場環境を良好に保ちましょう。
- 感情的に反応しない
- 一定の距離感を持つ
- 周囲と共有しておく
- 上司に事実を報告
- 自分の感情ケアも忘れない
感情的に反応しない
辞める発言に対して慌てたり心配したりせず、冷静な態度を保つことが大切です。
過度な反応は相手の注目を集めたい欲求を満たし、さらなる発言を誘発する可能性があります。
たとえば、同僚が「もう辞める」と言った際に「大変だね」「どうしたの?」と過剰に心配するのではなく、「そうですか」と淡々と受け流すことで相手の期待する反応を与えません。
冷静な対応を心がけて、不必要な騒動を避けてください。
一定の距離感を持つ
辞める発言を頻繁にする人とは、適度な距離を保ちながら接することが重要です。
深く関わりすぎると、相手の感情に巻き込まれて自分自身がストレスを感じる原因となります。
具体的には、業務上必要な連絡は取りつつも、プライベートな相談や愚痴を聞く役割は避け、表面的で礼儀正しい関係性を維持します。
程良い距離感を保って、自分の精神的な負担を軽減しましょう。
周囲と共有しておく
辞める発言を繰り返す人の行動パターンを、信頼できる同僚や上司と情報共有することが効果的です。
一人で抱え込まず、チーム全体で状況を把握することで適切な対応策を検討できます。
例として、定期的なミーティングの際に「○○さんが最近辞める発言を繰り返している」という事実を報告し、業務への影響を最小限に抑える方法を話し合います。
チーム全体で情報を共有して、組織的に対処してください。
上司に事実を報告
辞める発言が業務や職場環境に悪影響を与えている場合は、上司に客観的な事実を報告することが必要です。
個人的な感情を交えず、具体的な発言内容や頻度、業務への影響を整理して伝えます。
仮に毎日のように辞める発言があり、チームの士気が下がっている状況であれば、日時と発言内容を記録して上司に相談します。
事実に基づいた報告をして、適切な対処を求めてください。
自分の感情ケアも忘れない
他人の辞める発言に振り回されることで生じる、ストレスや疲労感にも注意を払うことが大切です。
自分自身の精神的な健康を守るため、適切なストレス発散方法を見つけておきます。
例として、仕事後の運動や趣味の時間を確保し、職場での出来事を引きずらないよう意識的にリフレッシュする時間を作ります。
自分の心身の健康を最優先に考えて、無理をしないでください。
会社に辞めると言った後に撤回する方法

一度辞めることを伝えた後でも、適切な手順を踏めば撤回することは可能です。
誠実な対応と明確な意思表示により、職場での信頼関係を回復できます。
ここではあなたが「辞めることを止めた」場合を想定して、適切に撤回する方法をご紹介します。
- 早めに伝える
- 上司に相談する
- 撤回理由を正直に伝える
- 迷惑をかけたことを謝る
- これからの意欲を伝える
早めに伝える
退職の意思を撤回したいと決めたら、できるだけ早急に伝えることが重要です。
時間が経過するほど会社側の準備が進み、撤回が困難になる可能性があります。
たとえば、退職届を提出した翌日に気持ちが変わった場合は、即座に直属の上司に連絡を取り、撤回の意思を伝えます。
迅速な行動により、お互いの負担を最小限に抑えてください。
上司に相談する
撤回の意思が固まったら、まず直属の上司に相談することから始めましょう。
上司は人事手続きや業務調整の状況を把握しており、撤回の可能性について適切な判断を下せます。
具体的には、個別の面談時間を設けてもらい、撤回したい理由と今後の働く意欲について率直に話し合います。
上司との相談を通じて、撤回への道筋を見つけてください。
撤回理由を正直に伝える
なぜ退職の意思を撤回したいのか、その理由を誠実に説明することが信頼回復の第一歩です。
曖昧な説明では相手の理解を得られず、今後の関係性に悪影響を与える可能性があります。
例として、家族との話し合いで考えが変わった、冷静になって現在の職場の価値を再認識した、などの具体的な理由を述べます。
正直な理由説明により、相手の納得と理解を得ましょう。
迷惑をかけたことを謝る
退職発言により迷惑をかけたことを素直に謝罪することが大切です。
後任探しや業務引き継ぎの準備など、会社側が費やした時間と労力に対する配慮を示します。
仮に人事部が既に求人活動を開始していた場合は、その労力に対して心からお詫びの気持ちを表現します。
真摯な謝罪の姿勢を示して、信頼関係の修復に努めてください。
これからの意欲を伝える
撤回後はこれからの意欲を伝えることが大切です。
口先だけでなく、具体的な行動計画や目標を示すことで、本気度を証明できます。
例として、スキルアップのための研修受講や、新しいプロジェクトへの積極的な参加意思を表明します。
前向きな姿勢を示して、今後の貢献への強い意志を伝えてください。
辞める辞めるハラスメントの具体例
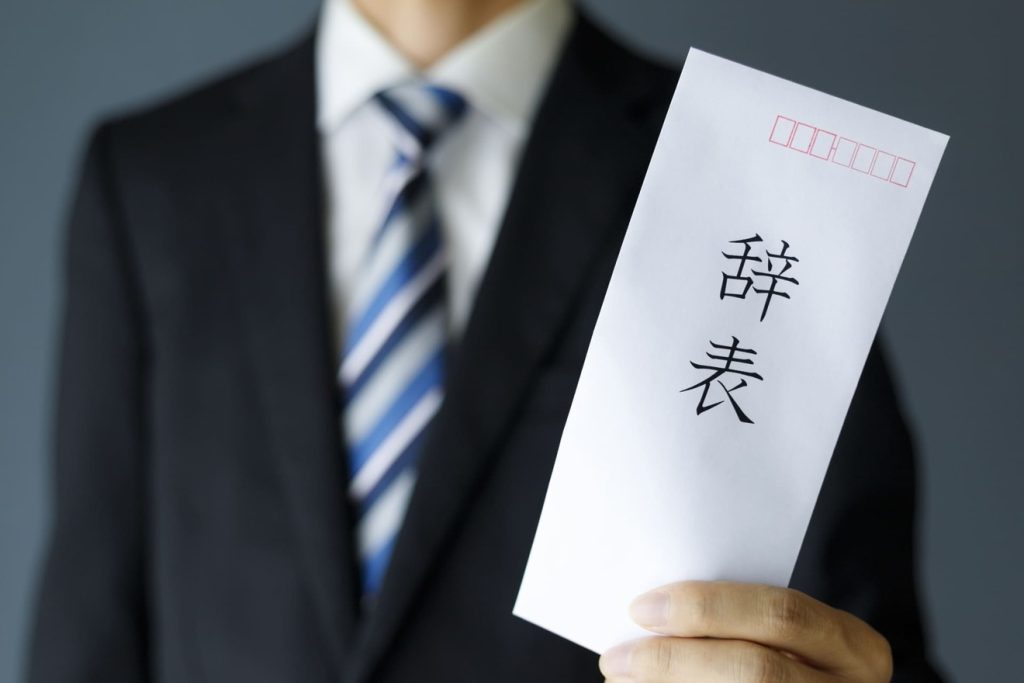
職場での頻繁な辞める発言は、時として周囲に迷惑をかけるハラスメント行為となることがあります。
本人に悪意がなくても、同僚や上司に精神的な負担を与える可能性があります。
問題となる行動パターンを理解して、適切な対処法を考えましょう。
- 毎日「もう辞めたい」発言
- 忙しい時に「もう辞める」宣言
- 上司への遠回しアピール
- 辞める前提で責任逃れ
- 他人の前で「辞めたい」演出
毎日「もう辞めたい」発言
日常的に辞めたいという発言を繰り返し、周囲の人々を不安にさせる行為です。
聞かされる側は毎回反応に困り、精神的な疲労を感じるようになります。
たとえば、朝の挨拶代わりに「今日も辞めたい」と言ったり、昼休みに「午後からもう嫌だ、辞めよう」と愚痴をこぼしたりする行動が該当します。
継続的な発言により、職場の雰囲気を悪化させる要因となります。
忙しい時に「もう辞める」宣言
繁忙期や重要な業務の最中に辞める発言をして、チーム全体の士気を下げる行為です。
タイミングの悪さが周囲のストレスを増大させ、業務効率にも悪影響を与えます。
具体的には、締切直前のプロジェクトで「こんな忙しさなら辞める」と発言し、他のメンバーの集中力を削いだり不安を煽ったりします。
最も配慮が必要な時期での発言は、特に問題となるでしょう。
上司への遠回しアピール
直接的な要求ではなく、辞める発言を通じて上司に待遇改善を求める行為です。
間接的な圧力をかけることで、自分の要求を通そうとする意図が見え隠れします。
例として、人事評価の時期に「この待遇では続けられない」「他にいい条件の会社がある」などと発言し、昇進や昇給を暗に要求する行動があります。
遠回しな要求方法として使われる場合があります。
辞める前提で責任逃れ
辞める可能性をほのめかすことで、責任ある業務や困難な仕事を避けようとする行為です。
将来性がないことを理由に、現在の責任から逃れようとする意図があります。
仮に新しいプロジェクトのリーダーを任された際に「どうせ辞めるかもしれないので」と断ったり、研修への参加を「意味がない」と拒否したりします。
責任回避の手段として辞める発言が使われているのです。
他人の前で「辞めたい」演出
特定の人物がいる場面で意図的に辞める発言をして、注目や同情を集めようとする行為です。
計算された演出により、自分への関心を引こうとする意図が明確に見られます。
例として、上司が近くにいる時だけ「もう限界、辞めたい」と大きな声で発言したり、人気のある同僚の前で弱々しく「続けられない」と訴えたりします。
演出的な発言により、周囲を困惑させる行動パターンです。
辞める辞める言って辞めない人への疑問

職場でよく見かける「辞める」発言について、多くの人が抱く疑問があります。
実際の行動と発言の矛盾や、その後の展開について理解を深めることが重要です。
よくある疑問とその答えを整理してみましょう。
- 本当に辞める人と辞めない人の違いはなに?
- 仕事を辞めると言った後に続けるのはなぜ?
- 勢いで辞めると言ってしまったらどうなる?
- 辞めるのを止めると信用をなくす?
- 一度辞めると言った社員は撤回できない?
本当に辞める人と辞めない人の違いはなに?
実際に退職する人は具体的な行動を伴い、辞めない人は発言だけに留まる傾向があります。
行動パターンの違いを観察することで、本気度を判断できるでしょう。
たとえば、本当に辞める人は転職サイトに登録したり面接を受けたりする一方、辞めない人は愚痴や不満を口にするだけで具体的な準備をしません。
行動の有無が最も明確な判断基準となります。
仕事を辞めると言った後に続けるのはなぜ?
経済的な不安や転職への恐怖心が、発言後も現職に留まる主な理由です。
感情的な発言と現実的な判断の間にギャップが生じているのです。
具体的には、収入の途絶への不安や、新しい環境への適応に対する心配が、退職への一歩を踏み出すことを阻んでいます。
現実的な制約が発言を行動に移すことを困難にしているのです。
勢いで辞めると言ってしまったらどうなる?
感情的になって退職を宣言した場合でも、冷静になれば撤回の道は残されています。
早急な対応と誠実な説明により、関係修復は可能です。
例として、上司との面談で撤回の意思を伝え、今後の働く意欲を示すことで、職場での立場を回復できる場合があります。
迅速で誠実な対応により、信頼関係を再構築できるでしょう。
辞めるのを止めると信用をなくす?
適切な理由説明と今後への意欲表示があれば、信用失墜は避けられます。
重要なのは、撤回の理由と今後の取り組み姿勢を明確に示すことです。
仮に家庭の事情で考えが変わった場合や、冷静になって会社の価値を再認識した場合など、納得できる理由があれば理解を得られます。
誠実な対応により、むしろ信頼関係が深まる可能性もあります。
一度辞めると言った社員は撤回できない?
法的には退職の撤回は可能であり、会社の合意があれば職場復帰できます。
ただし、会社側の事情や準備状況によって対応が変わる場合があります。
例として、後任が決まる前や引き継ぎが完了していない段階であれば、撤回が受け入れられる可能性が高くなります。
タイミングと状況次第で、撤回の成功率は大きく変わってくるでしょう。
辞めると言って辞めないパートさんの話

筆者が学生時代にアルバイトをしていたコンビニで、「辞める辞める」が口癖のパートさんがいました。
事あるごとに店や店長の悪口を言い、「こんな職場もう嫌だ」「明日にでも辞めてやる」と愚痴をこぼしていたのです。
しかし、そんな発言を繰り返しながらも、彼女は一向に辞める気配がありませんでした。
筆者は不思議に思い、仲の良い先輩に訪ねてみたところ、驚くような事実を教えてもらったのです。
「あの人、家庭がうまくいってないんだよ。旦那さんとの関係が悪くて、そのストレスを職場で発散してるだけ」と先輩は説明してくれました。
さらに「ああ言ってるけど、本当は辞められないのは本人が一番理解していると思う」とのこと。
どうやら家庭環境に問題があるようで、他人にかまってもらいたいと思っていたようです。
この経験から筆者は、辞める発言の裏には様々な事情が隠れていることを学びました。
表面的な言葉に振り回されず、相手の置かれた状況を理解することの大切さを実感したのです。
まとめ
職場で「辞める辞める」と言って辞めない人には、注目を集めたい心理や本当は辞めたくない気持ち、待遇改善への期待など様々な理由があります。
転職への自信不足や決断力の乏しさ、家庭の事情といった現実的な制約も影響しているのです。
このような人に振り回されないためには、感情的に反応せず一定の距離感を保つことが重要です。
周囲と情報共有し、必要に応じて上司に報告することで組織的に対処できます。
相手の言葉に惑わされすぎずに、ストレスを溜めないよう注意しましょう。
仮に、あなた自身が勢いで「辞める」と言ってしまった場合でも、早めに撤回の意思を伝え、正直な理由説明と謝罪、今後への意欲を示すことで信頼関係を回復できます。
辞める発言を繰り返す人の心理を理解し、適切な対処法を実践することで、職場でのストレスは大幅に軽減されるのです。
他人に振り回されることなく、自分らしく働ける環境を作っていきましょう。



