出世をするのは誇らしいことですが、ふと「管理者にならなきゃ良かった」と思う瞬間がありますよね。
仕事は増えるし、プレッシャーで押しつぶされそうになる気持ち、よくわかります。
できることなら、もう少し肩の力を抜いて働きたいですよね。
実際のところ、「管理者にならなきゃよかった」と悩むのは、あなただけではありません。
管理職はやることが多いため、役割を果たせないと思う人も多いです。
今回の記事では、「管理者にならなきゃ良かったと思う理由と対処法」についてご紹介します。
管理職になってつらい思いをしている方は、ぜひ参考にしてください。
- なぜ「管理職にならなきゃ良かった」と思うのか
- 管理職になってはいけない人の特徴を知る
- 管理職がつらいときの対処法を学ぶ
管理職にならなきゃ良かったと思う理由
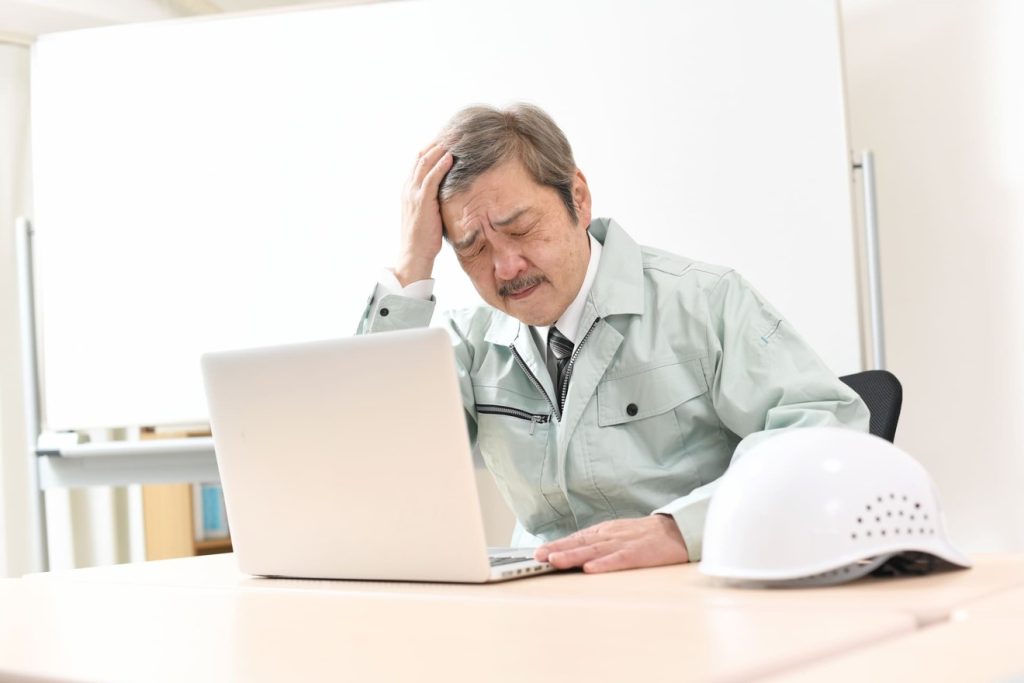
管理職に昇進することはキャリアの大きなステップですが、その後に「管理職にならなきゃ良かった」と感じることもあります。
実際の業務の厳しさや責任の重さに気づき、後悔することがあるでしょう。
そこで、どのような理由で管理職を公開することがあるのか解説します。
- 仕事量の増加
- 人間関係の変化
- 期待とプレッシャー
- スキル不足
- バランスの難しさ
仕事量の増加
管理職になると、多くの人が「仕事量が増えた」と感じます。
チーム全体の業務管理やメンバーの指導、会議の参加など、日常的なタスク以外の負担が加わるからです。
たとえば、プロジェクトの進行を管理するのはもちろん、予算の配分やクライアントとの交渉も担当しなければならない場合があります。
自分の業務に集中する時間が減り、プライベートとのバランスが取りづらくなるのです。
人間関係の変化
管理職に昇進すると、周囲の人間関係が大きく変わる可能性があります。
かつての同僚が部下になる場合、役割の違いが新たな緊張を生むかもしれません。
以前はフランクに話せていた同僚が、指導を受ける立場になることで不満を抱いたり、距離を感じたりすることが考えられます。
こうした状況がストレスとなり、仕事へのモチベーションを下げる原因となるでしょう。
期待とプレッシャー
管理職には高い期待が寄せられるため、その分プレッシャーも増大します。
上層部からの成果要求や部下からのサポート期待に応える必要があるため、常に成果を意識した働き方が求められるからです。
たとえば、新しいプロジェクトの成功を上層部から期待されつつ、同時に部下の成長支援やチーム全体のパフォーマンス向上を図る必要があります。
このような多面的なプレッシャーは、精神的な負担を増やし、管理職を後悔する要因の一つとなるでしょう。
スキル不足
管理職としてのスキルが不足していると、その役割が重荷に感じられることがあります。
多くの企業では、管理職に対してリーダーシップや意思決定能力、問題解決能力などの高度なスキルが求められるからです。
たとえば、新しいチームメンバーの教育や、トラブル発生時の適切な対応が求められる場面、自分のスキル不足を痛感するかもしれません。
これがストレスの原因となり、「管理職にならなければ良かった」と感じる瞬間が生まれるのです。
バランスの難しさ
管理職には、業務の多忙さとプライベートのバランスを保つ難しさもついて回ります。
責任範囲が広がることで、仕事が終わらないことが増え、家族や友人との時間が削られていくからです。
具体的には、長時間労働や休日出勤が常態化し、心身の疲労が蓄積していくケースがあります。
このような状況では、精神的・身体的な健康に悪影響を及ぼし、「管理職をやめたい」という気持ちが強まるでしょう。
管理職になりたくない人が増えている事情

近年、若手社員の約77%が「管理職になりたくない」と回答している背景には、複数の要因が存在します。
参考:若手社員の8割近くが「管理職になりたくない」…リーダーが育ちにくい時代の「上司代行」の可能性
まず、少子高齢化による人材不足が深刻化し、労働力が減少する中、管理職の業務負担が増大しています。
これにより、管理職は自身の業務に加え、部下の育成を同時に行う「プレイングマネージャー」としての役割を強いられることが多く、「忙しい」「辛い」といったネガティブなイメージが定着しました。
さらに、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントへの配慮が必要となり、責任が重くのしかかる管理職は、一般社員から避けられる存在になっています。
このような状況から、企業は社内で新たなリーダーを育成しづらくなり、代わりに外部の専門家に「上司代行」を任せるケースも少なくありません。
結果として、管理職に対する憧れが薄れ、代わりに外部のプロフェッショナルの支援を受けるスタイルが注目されるようになっています。
管理職になってはいけない人の特徴

すべての人が管理職に向いているわけではありません。
管理職に不向きな特徴を持っていると、役割を全うするのが難しくなることがあります。
どのような特性が管理職に適さないのかを知ることで、自身に合ったキャリアを選ぶ参考になるでしょう。
- 人と関わるのが苦手
- 自己中心的
- 成長意欲がない
- ストレス耐性が低い
- 他人の意見を受容できない
人と関わるのが苦手
管理職には、さまざまな人とコミュニケーションを取るスキルが求められます。
チームのリーダーとして、メンバーとの信頼関係を築き、円滑な業務運営を行うことが必要です。
しかし、人と関わるのが苦手な人は、部下との対話や他部署との調整にストレスを感じることが多く、チームのパフォーマンスにも悪影響を与えます。
人との関係構築が苦手な場合、管理職には向いていないと言えるでしょう。
自己中心的
管理職はチーム全体の成果を考えた行動が求められますが、自己中心的な人はその役割を果たすのが難しいです。
自己中心的な性格の人は、自分の意見や利益を優先しがちで、チームメンバーの意見を尊重したり、適切なサポートを提供したりすることができません。
例として、会議で自分の意見ばかりを押し通し、他のメンバーの意見を無視する場合、チーム内で不満が高まり、信頼関係の破綻につながります。
自分さえ良ければ良いという考えの人は、管理職になってはいけないでしょう。
成長意欲がない
管理職には、絶えず自己改善を目指す成長意欲が必要です。
業務内容が多岐にわたるため、新しいスキルの習得や最新の知識を取り入れる姿勢が求められます。
しかし、成長意欲がない人は、学びの機会を逃し、業務の質を向上させるための努力を怠ってしまいます。
新しいプロジェクトに対する積極的な取り組みがなく、現状維持を選び続ける場合、組織の成長を妨げる要因となるでしょう。
ストレス耐性が低い
管理職には多くの責任やプレッシャーが伴います。
ストレス耐性が低い人は、その重圧に耐えられず、精神的に追い詰められる可能性が高いです。
例として、タイトなスケジュールの中で複数のタスクを同時進行する必要がある場合、ストレスを感じやすい人はパフォーマンスが低下し、チーム全体に悪影響を及ぼします。
そのため、ストレス耐性が低い人は、管理職に向いていないと言えるでしょう。
他人の意見を受容できない
管理職は様々な意見を取り入れて、最適な意思決定を行うことが求められます。
しかし、他人の意見を受容できない人は、チームメンバーのアイデアやフィードバックを無視しがちで、柔軟な対応ができません。
部下の提案に対して常に否定的な態度を取ることで、チームの士気を低下させることが考えられます。
このような態度は組織の成長を阻むだけでなく、信頼関係を損ねる要因となるでしょう。
管理職を辞めてよかったと思えるケース
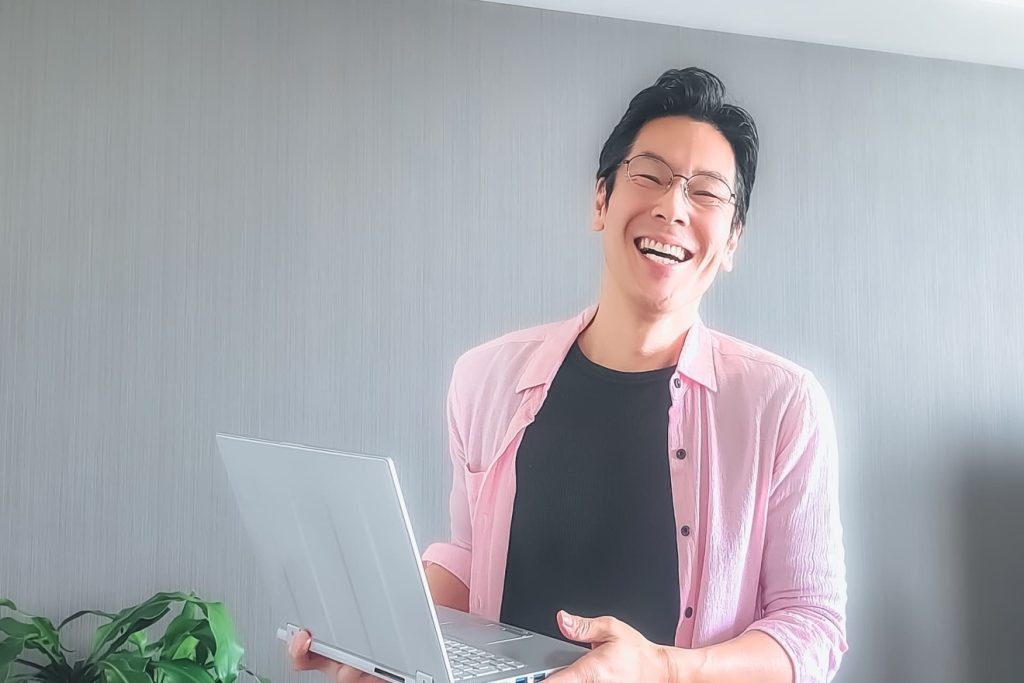
管理職を辞めることで、思わぬメリットがある場合もあります。
管理職を辞めたことで得られる具体的な良い変化を知ることで、自分にとって最良の選択を見つける手助けとなるでしょう。
- ストレスが軽減される
- 専門的な仕事に集中できる
- ワークライフバランスの改善
- 新たなキャリアパスを見つけられる
- 新しい環境でリフレッシュできる
ストレスが軽減される
管理職を辞めることで、多くのストレスから開放されます。
管理職になると、チームの成果を求められる責任や、複数の業務を同時にこなすプレッシャーがつきものです。
しかし、これらの負担から解放されることで、精神的なストレスが大幅に軽減されます。
たとえば、部下のマネジメントや目標達成のプレッシャーから離れることで、心の平穏を取り戻せます。
ストレスが軽減され、自分らしい働き方を見つけることができるでしょう。
専門的な仕事に集中できる
管理職を辞めることで、自分の専門分野に集中できる時間が増えます。
管理職を辞めて現場に戻ることで、自分の得意な領域でのスキルを磨き、キャリアの専門性を高めることができるからです。
たとえば、定時に帰宅して自己学習に励んだり、勉強会に参加することもできます。
技術職であれば新しい技術の習得に集中できるようになるため、プロフェッショナルとして評価を高められるでしょう。
ワークライフバランスの改善
管理職を辞めることで、ワークライフバランスの改善が期待できます。
管理職は業務量が多く、残業や休日出勤が常態化しやすいですが、辞めることでプライベートの時間を確保できるからです。
たとえば、家族や友人と過ごす時間が増えたり、自分の趣味や健康のために活動する時間ができます。
ワークライフバランスを整えることで、より充実した毎日を送ることができるでしょう。
新たなキャリアパスを見つけられる
管理職を辞めることで、新たなキャリアパスを見つけるチャンスが広がります。
これまでのキャリアを活かして、新しい分野や職種に挑戦することができるからです。
具体的には、管理職としての経験を活かして、コンサルタントやプロジェクトマネージャーなど、別の職務に転身することも考えられます。
新たな道を切り開くことで、自分にとって最適なキャリアを見つけることができるでしょう。
新しい環境でリフレッシュできる
管理職を辞めて新しい環境に移ることで、心身ともにリフレッシュすることができます。
管理職としての業務が精神的にも体力的にも負担となっている場合、新しい場所で新たなスタートを切ることが効果的です。
例として、異動や転職を通じて、新しい同僚や業務に触れることで、新鮮な気持ちで仕事に取り組むことができます。
環境を変えることで、再び意欲的に仕事に向き合うことができるでしょう。
管理職がつらいときの対処法

管理職としての業務がつらいと感じるとき、効果的な対処法を知っておくことは非常に重要です。
業務の負担を軽減し、ストレスを減らすための具体的な方法を知ることで、働き方が変わってくるでしょう。
- 労働環境を改善する
- 課題を可視化する
- 同じ管理職に相談する
- 役割の変更を検討する
- リフレッシュする方法を探す
労働環境を改善する
管理職がつらいと感じる原因の一つは、労働環境の問題です。
長時間労働や過度な責任感がストレスの要因となります。
まずは、自分の労働環境を見直し、改善策を講じるようにしてください。
たとえば、タスクの優先順位を整理し、必要以上の業務を抱え込まないようにすることで、負担を軽減できます。
また、職場のレイアウトや休憩スペースの活用など、物理的な環境の改善も心身のストレス軽減に役立つでしょう。
課題を可視化する
管理職としての業務が煩雑で負担が大きい場合、課題を可視化することが重要です。
問題の原因や対策を明確にすることで、解決への道筋が見えてきます。
日々の業務をリスト化し、何が優先事項で、何が後回しにできるかを明確にすることが大切です。
プロジェクト管理ツールを活用してタスクを視覚化し、進捗状況を把握することで、業務をより効率的に進めることができるでしょう。
同じ管理職に相談する
孤独を感じやすい管理職には、同じ立場の人との交流が有効です。
職場や業界の同僚、他社の管理職とも積極的に交流し、互いの悩みや成功事例を共有することが励みになります。
たとえば、定期的にミーティングや交流会を開き、困難な状況を乗り越えるためのアイデアやアドバイスを得ることができます。
相談することで新たな視点や解決策が見つかり、気持ちが軽くなるでしょう。
役割の変更を検討する
管理職としての業務が重すぎる場合、役割の変更を検討することも一つの手です。
自分のスキルや強みを再評価し、それを活かせる他のポジションに移ることを考えてみてください。
例として、管理職を降りて専門職に戻ることで、自分の得意な分野で力を発揮し、仕事への満足感を取り戻すことができます。
一社員に戻ることで、ストレスは軽減され、のびのび働けるようになるでしょう。
リフレッシュする方法を探す
管理職のプレッシャーに押しつぶされそうなときは、リフレッシュする方法を探してください。
休暇を取ったり、趣味や運動に励むことで、心身の健康を保つことができます。
たとえば、週末に自然の中で過ごす時間を作ったり、定期的なフィットネスやヨガのクラスに参加したりすることで、リフレッシュ効果が期待できます。
あなたに合った方法でストレスを解消し、健康的な働き方を維持しましょう。
管理職に関するよくある疑問

管理職になると、さまざまな疑問や悩みが生まれます。
ここからは管理職になった人が感じやすい、よくある疑問について解説します。
- 管理職は責任が強いから潰れる?
- 管理職は誰も助けてくれない?
- 大企業の管理職は疲れやすい?
- 女性管理職は疲れることが多い?
- 管理職でストレスが限界に達したらどうする?
管理職は責任が強いから潰れる?
管理職になると、チーム全体の成果に対する責任が重くのしかかるため、「潰れるのではないか」と不安に感じる人も多いです。
管理職は部下のパフォーマンスや業務進行の管理、上層部からの期待に応えることが求められます。
しかし、その重圧を軽減するためには、自分一人で抱え込まず、周囲と協力する姿勢が大切です。
たとえば、部下に適切な権限を委譲し、チームとしての力を最大限に活用することで、責任の負担を分散することができます。
自分一人で抱え込まないようにし、時には部下を頼るようにしてください。
管理職は誰も助けてくれない?
「管理職になると誰も助けてくれない」と思うかもしれませんが、実際にはそうではありません。
上司や同僚、部下とのコミュニケーションを大切にし、助けを求めることで周囲の支援を得ることができます。
例として、定期的なミーティングを開催し、現状の課題やリソース不足についてオープンに話し合うことで、部下からさまざまな意見が集まります。
部下に仕事を任せれば自身の負担は減るし、業務の新陳代謝を起こせるでしょう。
大企業の管理職は疲れやすい?
大企業の管理職は、複雑な業務プロセスや多様な利害関係者との調整が求められるため、「疲れやすい」と感じる場合があります。
特に組織の規模が大きいほど、管理すべき範囲も広がり、意思決定に時間がかかるからです。
ただし、効果的な業務の効率化や時間管理のスキルを身につけることで、負担を軽減することは可能になります。
デリゲーション(権限委譲)を積極的に行い、信頼できる部下にタスクを任せることで、自身の負担を減らすことができるでしょう。
女性管理職は疲れることが多い?
女性管理職は、家庭と仕事の両立や、職場における偏見や期待のギャップなど、独自の課題に直面することが多くなります。
そのため、「疲れることが多い」と感じることも少なくありません。
しかし、これらの課題に対して、家庭内でのサポートを求めたり、職場での環境改善を図ったりすることで、負担を軽減することが可能です。
フレックスタイム制度やテレワークを活用し、柔軟な働き方を実現することで、バランスを取りやすくなるでしょう。
管理職でストレスが限界に達したらどうする?
管理職でストレスが限界に達した場合、自分の健康を最優先に考えてください。
ストレスの兆候に気づいたら、適切な休息を取ることが大切です。
具体的には、有給休暇や福利厚生を利用して、しばらく休んでも構いません。
早期にストレスを発散することで、心穏やかに現場復帰できるでしょう。
まとめ
管理職になるのは大きなステップアップですが、ふとした瞬間に「管理職にならなきゃ良かった」と感じる場合があります。
仕事量の増加や人間関係の変化、期待とプレッシャーやバランスの難しさから、疲れてしまっても仕方ないです。
管理職にも向き・不向きがあり、人と関わるのが苦手な人や、ストレス耐性が低い人は上手く対応することができません。
一方、管理職を辞めることで、専門的な仕事に集中でき、ワークライフバランスは改善し、新たなキャリアパスを見つけるチャンスが広がります。
管理職がつらいと感じるときは、労働環境を改善し、課題を可視化した後、同じ管理職に相談してみてください。
その上で、管理職に向いてないと思ったら、役割の変更を申し出て、管理職を降りるのも一つの方法です。
管理職といっても、会社の中で与えられた役割にすぎず、それが全てではありません。
あなたに合った働き方を見つけて、無理しないようにしましょう。



