退職時の定期代返還は、多くの人が悩む問題ですよね。
会社から返金を求められたらどうしようと不安になってしまうし、できれば返したくないという気持ちよくわかります。
できることなら、定期代を返さずに済ませたいですよね。
実は、定期代は返す・返さないは会社のルールによって異なります。
退職時の定期代精算が適切に理解できれば、無駄なトラブルにはなりません。
そこで今回は、「退職時に定期代を返さない場合の考え方」をご紹介します。
定期代の仕組みが正しく理解できれば、安心して退職手続きが行えるでしょう。
- 退職時の定期代精算ルールが理解できる
- 返金が必要なケースと不要なケースがわかる
- 定期代返金を求められた時の対処法を習得できる
退職時の定期代精算の基本ルール

退職時の定期代精算は、労働者と会社双方にとって重要な手続きです。
多くの会社では交通費として定期代を支給しており、退職時にはその精算が必要になる場合があります。
精算方法や返金の有無は会社によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
- 定期代は会社の負担分
- 精算ルールは会社規定で決まる
- 余った分は返金されることがある
- 定額支給なら返さないこともある
- 返さないと天引きされる可能性
定期代は会社の負担分
定期代の多くは会社が業務上必要な経費として負担しています。
会社は従業員の通勤にかかる交通費を福利厚生の一環として支給するため、本来は会社の資産として扱われます。
たとえば、月額1万円の定期代を会社が支給している場合、その費用は会社の経費として計上されており、従業員個人の所有物ではありません。
そのため、退職時には使用していない期間分の精算が求められることがあります。
精算ルールは会社規定で決まる
定期代の精算方法は各会社の就業規則や社内規定によって定められています。
法律で統一されたルールがないため、会社ごとに異なる取り扱いとなっているのが現状です。
具体的には、就業規則の「退職に関する事項」や「交通費支給規定」に詳細が記載されており、これらの規定が精算の基準となります。
退職前に必ず自社の規定を確認し、どのような精算が必要なのかを把握しておきましょう。
余った分は返金されることがある
使用していない定期代の残額は、会社に返金を求められるケースがあります。
定期券には有効期限があり、退職日以降は使用できないため、残りの期間分が無駄になってしまうからです。
仮に、6ヶ月定期を購入して3ヶ月で退職した場合、残り3ヶ月分の費用相当額の返金を求められる可能性があります。
このような場合は、定期券を会社に返却し、日割り計算で精算することが一般的です。
定額支給なら返さないこともある
交通費が定額支給の場合は、返金が不要なケースも多くあります。
定額支給は実際の交通費に関係なく一定額を支給する制度のため、精算の概念がないことが理由です。
例として、月額2万円の交通費定額支給を受けている場合、実際の定期代が1万5千円でも2万円でも、支給額は変わりません。
このような支給方法では、退職時の精算も発生しないことが多いため、返金の心配は少ないでしょう。
返さないと天引きされる可能性
定期代の返金義務があるにも関わらず返済しない場合、給与や退職金から差し引かれることがあります。
会社は労働基準法に基づき、従業員の同意があれば給与から必要経費を控除することが認められているためです。
たとえば、最終月の給与が30万円で、返金すべき定期代が5万円の場合、25万円しか支給されない可能性があります。
トラブルを避けるためにも、返金が必要な場合は速やかに対応することをおすすめします。
退職時に定期代を返さないとどうなる?

定期代の返金義務があるにも関わらず応じない場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。
会社との信頼関係が悪化するだけでなく、金銭的なトラブルに発展することもあります。
円満な退職のためにも、適切な対応を心がけることが重要です。
- 会社から返金依頼が来る
- 給与や退職金から差し引かれる
- 会社との関係が悪化する
- トラブルや法的請求の可能性
- 退職後に罪悪感が残る
会社から返金依頼が来る
返金義務がある定期代を返さない場合、会社から直接返金の依頼が届きます。
会社は支給した交通費の適正な精算を行う義務があり、未返金分については回収する必要があるためです。
具体的には、人事部や総務部から電話やメールで連絡があり、返金期限や振込先などの詳細が伝えられます。
この段階で速やかに対応すれば、大きなトラブルに発展することは避けられるでしょう。
給与や退職金から差し引かれる
返金に応じない場合、最終給与や退職金から該当金額が差し引かれることがあります。
労働基準法では、労働者の同意があれば給与から必要な控除を行うことが認められているからです。
仮に、退職金が100万円で未返金の定期代が8万円の場合、92万円しか受け取れない可能性があります。
予想していた金額より少ない支給額となるため、事前に精算しておくことが大切です。
会社との関係が悪化する
定期代の返金を拒否し続けると、会社との関係が著しく悪化してしまいます。
退職後も転職の際の推薦状や在籍証明など、前職との関係が必要になる場面があるためです。
例として、転職先から前職への照会があった際に、金銭トラブルがあったことが伝わる可能性があります。
良好な関係を保つためにも、正当な返金要求には素直に応じることが賢明です。
トラブルや法的請求の可能性
悪質な場合は、会社が法的手段を取る可能性も否定できません。
定期代の未返金は会社の損失であり、民事上の不当利得として扱われる可能性があるためです。
たとえば、高額な定期代を長期間返金しない場合、内容証明郵便による催告や法的措置が検討されることがあります。
小額であってもトラブルの種となるため、早期の解決を心がけることが重要でしょう。
退職後に罪悪感が残る
返金すべき定期代を返さないまま退職すると、長期間にわたって罪悪感に悩まされることがあります。
お世話になった会社に迷惑をかけたという気持ちが、新しい職場での集中力にも影響する可能性があるためです。
具体的には、同僚との会話で前職の話題が出た際に、後ろめたい気持ちを感じることがあります。
清々しい気持ちで新たなスタートを切るためにも、適切な精算を行っておくことが大切です。
退職時に返金が必要になるケース
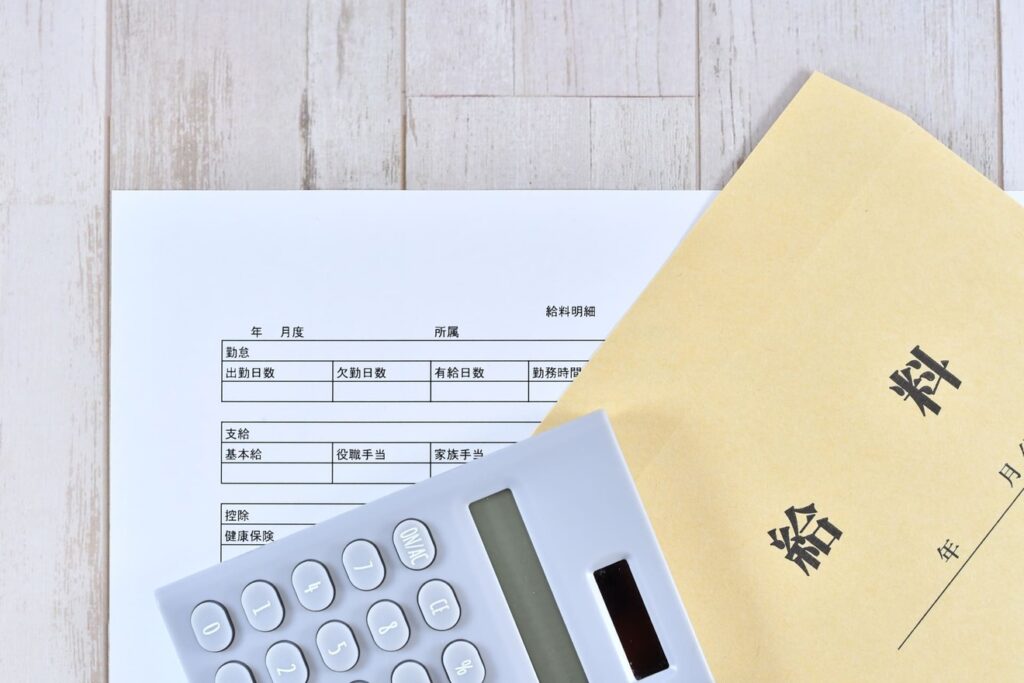
定期代の返金が必要になる具体的なケースを理解しておくことは重要です。
会社の支給方法や退職のタイミングによって、返金義務の有無が決まります。
事前に自分の状況を確認し、適切な準備をしておきましょう。
- 実費精算で定期代を支給されていた場合
- 定期券を会社が購入・負担していた場合
- 社内規定で返金と明記されている場合
- 特別支給された定期代
- 退職日が定期の途中の場合
実費精算で定期代を支給されていた場合
実際の定期券購入費用を精算で支給されている場合は、返金が必要になることが多くあります。
実費精算は会社が実際の交通費を立て替えているため、使用しない分は返却する必要があるからです。
たとえば、6ヶ月定期18万円を購入し3ヶ月で退職した場合、残り3ヶ月分の9万円相当の返金を求められます。
このような支給方法では、退職時の精算が発生することを前提として考えておきましょう。
定期券を会社が購入・負担していた場合
会社が直接定期券を購入して従業員に支給している場合も、返金が必要になります。
定期券自体が会社の資産であり、退職後は使用権限がなくなるため、現物または相当額の返却が求められるからです。
仮に、会社購入の3ヶ月定期が1ヶ月残っている状態で退職する場合、定期券の返却と残存価値分の精算が行われます。
会社管理の定期券は個人の判断で処分できないため、必ず返却手続きを行ってください。
社内規定で返金と明記されている場合
就業規則や交通費規定に返金について明記されている場合は、必ず従う必要があります。
社内規定は労働契約の一部として法的拘束力があるため、従業員は規定に従った精算を行う義務があるからです。
例として、規定に「退職時は未使用分の交通費を返金する」と記載されていれば、金額の大小に関わらず返金が必要です。
規定の内容に疑問がある場合は、退職前に人事部に確認を取ることをおすすめします。
特別支給された定期代
通常の交通費とは別に特別に支給された定期代は、返金対象となることがあります。
出張や研修などで臨時に支給された交通費は、目的が限定されているため使用しない分は返却が求められるからです。
具体的には、3ヶ月間の研修用定期代を支給されたが、1ヶ月で退職することになった場合、残り2ヶ月分の返金が必要になります。
特別支給の場合は通常よりも厳格な精算が求められるため、注意が必要になるでしょう。
退職日が定期の途中の場合
定期券の有効期間中に退職する場合は、残存期間分の返金が求められることが一般的です。
定期券は継続的な通勤を前提とした割引制度のため、途中で使用できなくなる場合は精算が必要になるからです。
仮に、6月末まで有効な定期券で5月中旬に退職する場合、約1.5ヶ月分の未使用期間について精算が行われます。
退職日が決まったら、定期券の有効期限と照らし合わせて精算の準備をしておきましょう。
退職時に返金が不要なケース

すべての場合で定期代の返金が必要というわけではありません。
支給方法や会社の規定によっては、返金義務が発生しないケースも多くあります。
自分の状況がどれに該当するかを確認してみましょう。
- 定額支給の交通費の場合
- 会社規定で返金義務がない場合
- 退職時に定期を使い切っている
- 社内で返金不要の慣例がある
- 上司から返さなくても良いと言われた
定額支給の交通費の場合
毎月一定額の交通費が支給される定額支給制度では、返金が不要なことが多くあります。
定額支給は実際の交通費に関係なく固定額を支給するため、精算という概念がないからです。
例として、月額2万円の交通費定額支給を受けている場合、実際の定期代が1万5千円でも2万5千円でも支給額は変わりません。
このような制度では退職時の精算も発生しないため、返金を心配する必要はないでしょう。
会社規定で返金義務がない場合
就業規則や社内規定で明確に「返金不要」と定められている場合は、返金義務はありません。
法律で返金が義務付けられているわけではないため、会社の規定に従った取り扱いとなるからです。
たとえば、規定に「退職時の交通費精算は行わない」と明記されていれば、定期代が余っていても返金する必要がありません。
不安な場合は退職前に人事担当者に確認を取ることで、トラブルを避けることができます。
退職時に定期を使い切っている
定期券の有効期限が退職日と同時か、それ以前に切れている場合は返金が不要です。
使用予定期間がすべて消化されているため、会社側も返金を求める理由がないからです。
仮に、3月末で定期が切れて3月末に退職する場合、定期代はすべて適正に使用されたことになります。
退職日を定期の有効期限に合わせることで、精算の手間を省くことも可能でしょう。
社内で返金不要の慣例がある
明文化されていなくても、社内で返金を求めない慣例が確立している場合があります。
長年の運用で返金を求めないことが通例となっており、従業員もそれを前提として考えているからです。
具体的には、過去の退職者が定期代を返金していない実績があり、会社側も黙認している状況です。
とはいえ、慣例は変更される可能性があるため、念のため確認しておくとが安心です。
上司から返さなくても良いと言われた
直属の上司や人事担当者から明確に「返金不要」と言われた場合は、その指示に従って問題ありません。
会社の正式な判断として返金を求めないことが決定されているため、従業員側で心配する必要がないからです。
たとえば、退職の相談時に上司から「定期代は気にしなくて良い」と言われた場合、その言葉を信頼して構いません。
ただし後々のトラブルを避けるため、可能であれば書面やメールで確認を残しておきましょう。
定期代の返金を求められたときの対処法

実際に定期代の返金を求められた場合の適切な対処方法を知っておくことは重要です。
慌てずに冷静に対応することで、スムーズな解決につなげることができます。
以下のステップに沿って対応してみましょう。
- 社内規定を確認
- 上司に相談する
- 金額を確認する
- 小額ならすぐ返す
- 記録を残す
社内規定を確認
返金を求められたら、まず就業規則や交通費規定の内容を確認してください。
規定に基づいた請求なのか、それとも慣例や担当者の判断なのかを明確にする必要があるからです。
たとえば、規定に「実費精算の場合は退職時に精算する」と記載されていれば、返金は正当な請求となります。
規定の内容を理解することで、適切な対応方針を決めることができるでしょう。
上司に相談する
返金の詳細について不明な点があれば、直属の上司に相談することが大切です。
上司は会社の方針を理解しており、適切なアドバイスや手続きの案内をしてもらえるからです。
具体的には、「定期代の返金について詳しく教えてください」と素直に相談し、会社の考えを聞いてください。
上司との相談を通じて、円滑な解決策を見つけることができます。
金額を確認する
返金すべき金額の詳細な内訳を確認し、計算に間違いがないかチェックしましょう。
定期代の日割り計算は複雑な場合があり、担当者が誤って計算している可能性もあるからです。
仮に、6ヶ月定期18万円で2ヶ月使用した場合、残り4ヶ月分の12万円が返金対象となるかを確認します。
金額に疑問がある場合は、計算根拠を教えてもらうことで納得して対応できるでしょう。
小額ならすぐ返す
返金額が小さい場合は、議論せずに速やかに返金することをおすすめします。
少額の金銭トラブルで会社との関係を悪化させるメリットはなく、円満な退職を優先すべきだからです。
例として、数千円程度の返金であれば、その場で現金で支払うか、指定口座に振り込んで解決しましょう。
小額であっても誠実に対応することで、会社からの信頼を維持することができます。
記録を残す
返金に関するやり取りは、必ず記録として残しておくことが重要です。
後日トラブルが発生した際に、適切な対応を行ったことを証明する材料となるからです。
たとえば、返金完了時には領収書をもらったり、メールでのやり取りを保存しておきます。
記録を残すことで、双方にとって安心できる解決となるでしょう。
退職の定期代に関するよくある疑問

退職時の定期代について、多くの人が抱く疑問や不安があります。
これらの疑問を解決することで、安心して退職手続きを進めることができます。
よくある質問とその回答をまとめました。
- 会社から何も言われなければ返さなくていい?
- 定期券を使わず残っているけど、返金義務ある?
- 会社が定期券を回収すると言われたらどうする?
- 給与から定期代が天引きされるのは違法?
- 月途中の退職だと定期代はどうなる?
会社から何も言われなければ返さなくていい?
会社から返金の要求がない場合でも、規定上返金義務があれば自主的に申し出るべきです。
就業規則に返金について記載されている場合、会社が請求しなくても従業員の義務として存在するからです。
たとえば、規定に明記されているにも関わらず会社が見落としている場合、後日問題となる可能性があります。
円満な退職のためにも、自ら確認して適切な対応を取ることをおすすめします。
定期券を使わず残っているけど、返金義務ある?
使用していない定期券でも、会社の規定や支給方法によって返金義務が発生します。
定期券の現物価値ではなく、会社が負担した交通費としての精算が求められるからです。
仮に、体調不良で通勤に使用していない定期券でも、会社負担分については返金対象となることがあります。
使用の有無に関わらず、会社の規定に従った精算を行うことが重要でしょう。
会社が定期券を回収すると言われたらどうする?
会社から定期券の回収を求められた場合は、素直に応じることが適切な対応です。
会社購入の定期券は会社の資産であり、退職後は返却する義務があるからです。
具体的には、人事部や総務部の指示に従って、指定された日時に定期券を持参して手続きを行います。
定期券回収と同時に、残存価値がある場合の精算方法も確認しておきましょう。
給与から定期代が天引きされるのは違法?
労働者の同意があれば、給与からの控除は労働基準法上問題ありません。
入社時の契約や就業規則で同意している場合、会社は必要な控除を行うことができるからです。
例として、雇用契約書に「会社が立て替えた費用は給与から控除する」旨の記載があれば、天引きは適法となります。
同意していない控除については労働基準監督署に相談することも可能です。
月途中の退職だと定期代はどうなる?
月途中の退職では、日割り計算で定期代の精算が行われることが一般的です。
定期券は月単位の割引制度のため、使用しない期間分については返金が求められるからです。
仮に、月末まで有効な定期券で月の半ばに退職する場合、残り半月分の定期代相当額の返金が必要になります。
会社によって計算方法が異なるため、退職前に具体的な精算方法を確認しておきましょう。
退職時に定期代を返すか迷った体験談
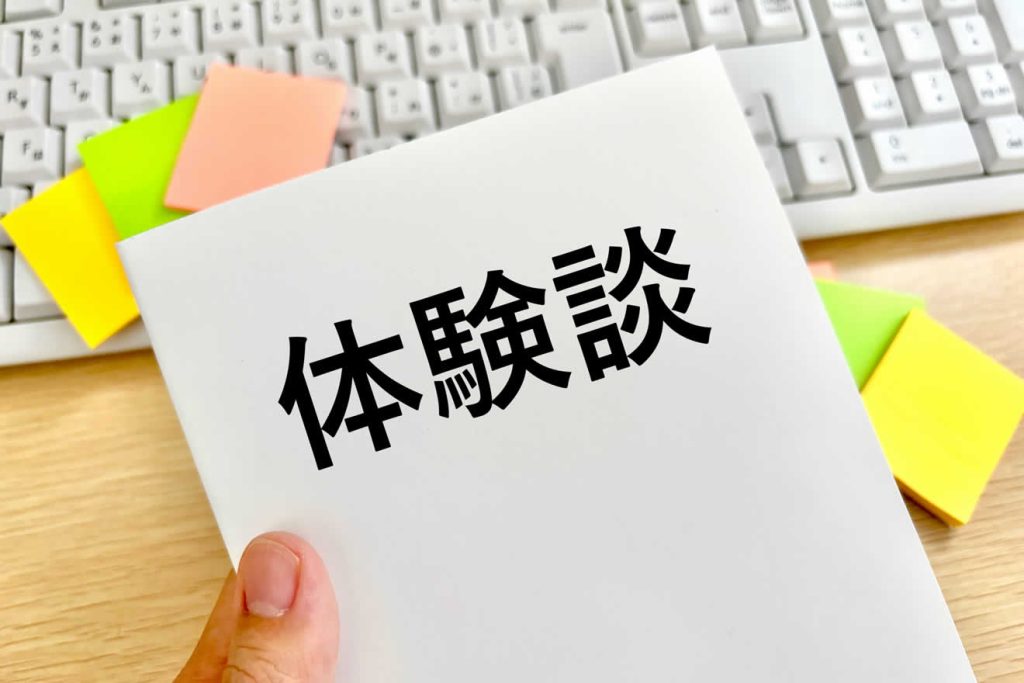
筆者も以前、退職時の定期代について悩んだ経験があります。
電車通勤をしていたので、退職するときに定期代の扱いが気になりました。
当時使っていた定期代は月額1万5000円ほどで、退職月の中頃に辞める予定だったため、半額程度は返さなくてはいけないのではないかと思ったからです。
上司に相談しようとも考えましたが、自分から定期代の話を切り出すのも変だと感じ、結局は静観することにしました。
もし会社から何か言われたら、その時に対応すれば良いだろうと考えていたのです。
そして退職日を迎えて会社を辞めましたが、結局のところ定期代の返還を求められることはありませんでした。
人事部からも上司からも、定期代については一切触れられずに退職手続きが完了したのです。
後日ネットで調べてみると「定期代を返す・返さない」の論争がまれにあることを知りましたが、筆者の場合は自分からわざわざ聞かなくても良い結果となりました。
ただし、返金が必要になるケースもあるということを頭に入れておいた方が安心だと思います。
まとめ
退職時の定期代精算について、基本的なルールから具体的な対処法まで詳しく解説してきました。
定期代は会社の負担分であり、精算ルールは会社規定によって決まります。
実費精算や会社購入の定期券では返金が必要になることが多い一方で、定額支給や社内規定で返金義務がない場合は返金不要となります。
もし返金を求められた場合は、社内規定を確認し、上司に相談して金額をチェックすることが大切です。
小額であれば速やかに返金し、やり取りの記録を残しておきましょう。
退職時の定期代に関する疑問は、事前に人事部や上司に確認することで解決できます。
新しいスタートに向け、定期代の精算も含めて気持ちよく退職手続きを進めていきましょう。



