職業訓練でWebデザイナーを目指すのは、本当に正しい選択なのか迷いますよね。
ネットで調べると「やめとけ」という声ばかり出てくるし、失敗したらどうしようと思う気持ちわかります。
できることなら、確実に就職につながる手段を選びたいですよね。
実は、Webデザイナーの職業訓練を受講しても、必ずWebデザイナーになれるわけではありません。
職業訓練の実態を把握しないと、後悔することになります。
そこで今回は、「職業訓練でWebデザイナーを目指すメリット・デメリット」をご紹介します。
職業訓練が自分に合っているかどうか見極め、冷静に判断するようにしてください。
- 職業訓練でWebデザイナーを目指すリスクと問題点の把握
- 職業訓練の具体的なメリット・デメリットの理解
- 選考に落ちる原因や授業についていけない理由の事前対策
職業訓練でWebデザイナーはやめとけと言われる理由

職業訓練でWebデザイナーを目指すことに対して、否定的な意見が多いのは事実です。
主な理由として、スキルの習得レベルや就職活動の厳しさが挙げられます。
期待していたほどの成果を得られずに終わってしまうケースが少なくありません。
まずは、Webデザイナーの職業訓練が否定されがちな理由を見ていきましょう。
- スキルが浅い
- 就職が難しい
- 競争が激しい
- 自主学習が必要
- 現場とのギャップ
スキルが浅い
職業訓練では基礎的なスキルしか身につかない場合が多いです。
限られた期間で多くの内容を学ぶため、どうしても表面的な知識に留まりがちになります。
たとえば、PhotoshopやIllustratorの基本操作は覚えられても、実際の制作現場で求められる高度なテクニックまでは習得できません。
職業訓練だけでは実務レベルに到達するのは困難でしょう。
就職が難しい
職業訓練修了後の就職活動は想像以上に厳しいものです。
企業側が即戦力を求める傾向が強く、基礎レベルのスキルでは採用に至らないことが多いためです。
具体的には、未経験者歓迎の求人でも実際は経験者が優遇され、書類選考で落とされるケースが頻発しています。
就職を前提とするなら、より実践的な学習方法を検討すべきです。
競争が激しい
Webデザイン業界は競争が非常に激しい分野です。
多くの人が参入を希望するため、同じレベルのスキルを持つ人材が溢れている状況だからです。
仮に職業訓練を修了しても、同様の経歴を持つ他の応募者との差別化が困難になります。
この激しい競争を勝ち抜くには相当な努力が必要になります。
自主学習が必要
職業訓練期間中も修了後も継続的な自主学習が欠かせません。
技術の進歩が早いWeb業界では、常に新しい知識やスキルの習得が求められるためです。
例として、新しいデザインツールやプログラミング言語が次々と登場するため、学習を怠ると即座に時代遅れになってしまいます。
自分で学習を続ける意欲がなければ成功は難しいでしょう。
現場とのギャップ
職業訓練で学ぶ内容と実際の制作現場には大きなギャップがあります。
訓練では理想的な環境で学習しますが、現実のプロジェクトでは厳しい締切や予算制約があるからです。
たとえば、クライアントからの無理な要求や短期間での修正対応など、訓練では体験できない状況に直面します。
このギャップを埋めるには実務経験が不可欠です。
職業訓練でWebデザイナーを目指すメリット

職業訓練には確実なメリットも存在しており、条件次第では有効な選択肢となります。
費用面や学習環境の充実度を考慮すると、独学よりも効率的に基礎を固められる可能性があるのです。
- 費用が安い
- 基礎が身につく
- 就職支援が充実
- 仲間と学べる
- 実践的な課題がある
費用が安い
職業訓練の最大のメリットは、費用の安さです。
失業保険受給者なら基本的に無料で受講でき、さらに交通費支給もあるためです。
具体的には、民間のWebデザインスクールが30万円以上かかるのに対し、職業訓練なら教材費程度で済みます。
経済的負担を抑えて学習したい人には大きな魅力といえるでしょう。
基礎が身につく
体系的なカリキュラムにより、確実に基礎知識を習得できます。
独学では見落としがちな基本的な理論やルールを網羅的に学べるからです。
例として、色彩理論やレイアウトの原則など、デザインの土台となる知識をしっかりと身につけられます。
基礎固めには非常に有効な手段でしょう。
就職支援が充実
多くの職業訓練校では手厚い就職支援を提供しています。
キャリアカウンセラーによる個別相談や履歴書添削、面接練習などのサポートが受けられるためです。
仮に一人で就職活動を行う場合と比較すると、専門的なアドバイスを受けられる分だけ有利になります。
就職活動に不安がある人には心強いサポートです。
仲間と学べる
同じ目標を持つ仲間と一緒に学習できる環境があります。
お互いに刺激し合いながら学習を進められるため、モチベーション維持に効果的だからです。
たとえば、作品の相互レビューやグループワークを通じて、多角的な視点を養うことができます。
一人では続かない学習も仲間がいれば継続しやすくなります。
実践的な課題がある
実際の制作現場を想定した課題に取り組める機会があります。
架空の企業サイトやバナー制作など、実務に近い内容を経験できるためです。
具体例として、クライアントからの要望書に基づいてWebサイトを制作する課題では、実際の業務フローを体験できます。
実践経験を積む貴重な機会として活用できるでしょう。
職業訓練でWebデザイナーを目指すデメリット

職業訓練には見過ごせないデメリットも多く存在します。
特に最新技術への対応や個別指導の面で限界があり、期待した成果を得られない可能性が高いです。
- カリキュラムが古い場合がある
- 個別対応が難しい
- 実務経験が不足しやすい
- 通学時間や場所の制約
- 終了後の自主努力が必須
カリキュラムが古い場合がある
職業訓練のカリキュラムが時代遅れになっているケースがあります。
公的機関のカリキュラム更新は民間に比べて遅く、最新のトレンドに対応できていないためです。
たとえば、現在主流のレスポンシブデザインやUI/UXデザインの内容が不十分な場合があります。
古い知識では現場で通用しない可能性が高いです。
個別対応が難しい
大人数での授業形式のため、個人のレベルに合わせた指導が困難です。
講師一人に対して受講生が多すぎるため、きめ細かいサポートが期待できないからです。
例として、理解度に差がある受講生全員に対して同じペースで進行するため、ついていけない人が出てしまいます。
個別の疑問や課題解決には限界があるでしょう。
実務経験が不足しやすい
職業訓練だけでは実際の制作現場で必要な経験が不足します。
模擬的な課題はあっても、本物のクライアントワークとは異なるためです。
仮に完璧に課題をこなしても、実際のプロジェクトでは予想外の問題や要求変更が発生します。
現場感覚を身につけるには別途実務経験が必要です。
通学時間や場所の制約
職業訓練校への通学には時間的・地理的な制約があります。
決められた時間と場所で受講する必要があり、個人の都合に合わせられないためです。
具体的には、遠方から通学する場合の交通費や時間コスト、家庭の事情で通学困難になるリスクがあります。
柔軟性に欠ける点は大きなデメリットといえます。
終了後の自主努力が必須
職業訓練修了後も継続的な学習と努力が絶対に必要です。
訓練期間だけでは実務レベルに到達できず、その後の成長が就職成功の鍵となるためです。
例として、ポートフォリオの充実や新しい技術の習得など、終了後も相当な時間投資が求められます。
訓練を受けただけで満足していては成功は難しいでしょう。
Webデザインの職業訓練に落ちた理由

Webデザインの職業訓練は競争率が高く、不合格になる人も多いのが現実です。
選考に落ちる理由を理解することで、再挑戦時の対策を立てることができます。
- 申し込み多数で枠が少ない
- スキルや熱意不足と判断された
- 目的や計画があいまい
- 書類や面接での自己PR不足
- 基本的に競争率が高い
申し込み多数で枠が少ない
Webデザイン講座は人気が高く、募集人数に対して応募者が多すぎる状況です。
在宅ワークへの憧れや手に職をつけたい人が殺到するため、必然的に競争が激化するからです。
たとえば、定員20名の講座に100名以上が応募することも珍しくありません。
基本的に数倍から十数倍の競争率になると考えておくべきです。
スキルや熱意不足と判断された
選考では受講への本気度や適性が厳しく評価されます。
なんとなく応募した人や準備不足の人は、熱意不足と判断されて落とされるためです。
具体例として、志望動機があいまいだったり、Webデザインについての基礎知識が全くない状態では不利になります。
事前の情報収集と明確な目標設定が重要でしょう。
目的や計画があいまい
受講後の具体的なビジョンが不明確だと選考で不利になります。
訓練校側は就職実績を重視するため、明確な目標を持つ人を優先的に選ぶからです。
仮に「なんとなくWebデザインに興味がある」程度の動機では、本気度を疑われてしまいます。
受講後のキャリアプランを具体的に示す必要があります。
書類や面接での自己PR不足
選考書類や面接での自己アピールが不十分な場合があります。
限られた時間で自分の魅力や可能性を伝えきれないと、他の応募者に後れを取るためです。
例として、過去の経験をWebデザインにどう活かすかを具体的に説明できない人は印象に残りません。
効果的な自己PRの準備が選考突破の鍵となります。
基本的に競争率が高い
Webデザイン講座の競争率は他の職種と比べて特に高い傾向があります。
クリエイティブな仕事への憧れと参入障壁の低さが人気の理由だからです。
具体的には、他の技術系講座が2-3倍程度なのに対し、Webデザインは5~10倍以上になることもあります。
高い競争率を前提として選考対策を万全に整える必要があるでしょう。
Web系の職業訓練についていけない原因

職業訓練を受講しても、途中でついていけなくなる人が一定数存在します。
事前に原因を把握しておくことで、対策を立てて成功確率を高められます。
- 知識の基礎不足
- 学習ペースの違い
- 自主学習の不足
- モチベーション低下
- 講師との相性問題
知識の基礎不足
パソコンやインターネットの基礎知識が不足していると授業についていけません。
職業訓練では基本的なPC操作ができることを前提として進行するためです。
たとえば、ファイル管理やショートカットキーの使い方すら分からない状態では、ソフトの操作説明についていけなくなります。
最低限のPC知識は事前に身につけておくべきです。
学習ペースの違い
個人の学習ペースと授業の進行速度が合わない場合があります。
集団授業では平均的なペースで進むため、理解の遅い人は置いていかれがちになるからです。
例として、PhotoshopやHTMLの基本操作でつまずくと、その後の応用内容が全く理解できなくなります。
自分のペースに合わない場合は別の学習方法を検討すべきでしょう。
自主学習の不足
授業時間だけでは内容を完全に理解・習得できません。
復習や課題制作など、授業外での自主的な学習が不可欠だからです。
仮に授業を真面目に受けていても、家での復習を怠ると確実に遅れを取ってしまいます。
継続的な自主学習ができない人は成功が困難です。
モチベーション低下
長期間の学習でモチベーションを維持するのは簡単ではありません。
思ったより難しい内容や就職活動の厳しさを知って、やる気を失う人が多いためです。
具体例として、制作課題が思うように進まなかったり、同期と比較して劣等感を感じることがあります。
強い目的意識がないとモチベーション維持は困難でしょう。
講師との相性問題
講師の教え方や人柄との相性が悪いと学習効果が下がります。
理解しやすい説明方法や学習スタイルは人それぞれ異なるためです。
例として、理論中心の講師と実践重視の受講生では、学習アプローチにズレが生じてしまいます。
相性が合わない場合は個人での学習補完が必要になるでしょう。
職業訓練のWebデザイナーに関する疑問

職業訓練でWebデザイナーを目指す際によくある疑問にお答えします。
事前に正確な情報を把握することで、適切な判断ができるでしょう。
- Webデザイナーの職業訓練を受ける方法は?
- 職業訓練のWebデザイナーは倍率が高い?
- 職業訓練のeラーニングはある?
- Webデザインを受講した後の就職先は?
- 40代が職業訓練でWebデザインをするのはあり?
Webデザイナーの職業訓練を受ける方法は?
ハローワークでの申し込みが基本的な受講方法です。
失業保険受給者であることが条件となり、キャリアカウンセリングを経て応募する流れになります。
たとえば、離職票を持参してハローワークで相談し、適性や目標を確認した上で申し込み手続きを行います。
まずはお近くのハローワークで詳細を確認してください。
職業訓練のWebデザイナーは倍率が高い?
非常に高い倍率になることが一般的です。
人気職種のため応募者が殺到し、定員の5倍から10倍以上の競争になることも珍しくありません。
具体的には、都市部では特に競争が激しく、地方でも3倍程度の倍率は覚悟する必要があります。
高倍率を前提とした選考対策が不可欠でしょう。
職業訓練のeラーニングはある?
一部の訓練校でeラーニング形式の講座が提供されています。
新型コロナの影響でオンライン対応が進み、在宅での受講が可能になったケースもあります。
例として、基礎的な理論部分はオンライン、実習は対面という混合型の講座もあります。
地域や訓練校によって対応が異なるため確認が必要です。
Webデザインを受講した後の就職先は?
制作会社やIT企業への就職が主な進路となります。
ただし、未経験者向けの求人は限られており、就職活動は想像以上に厳しいのが現実です。
仮に就職できても、最初は低賃金でのアシスタント業務から始まることが多くなります。
即戦力レベルまでスキルを高める継続努力が重要です。
40代が職業訓練でWebデザインをするのはあり?
年齢的にはかなり厳しい選択といわざるを得ません。
Web業界は若手が多く、40代未経験者の採用は非常に困難だからです。
具体例として、同じスキルレベルなら20代が優先される傾向が強く、書類選考で落とされるケースが多発しています。
現実的な転職戦略を慎重に検討すべきでしょう。
Webデザイナーの職業訓練をした人の体験談
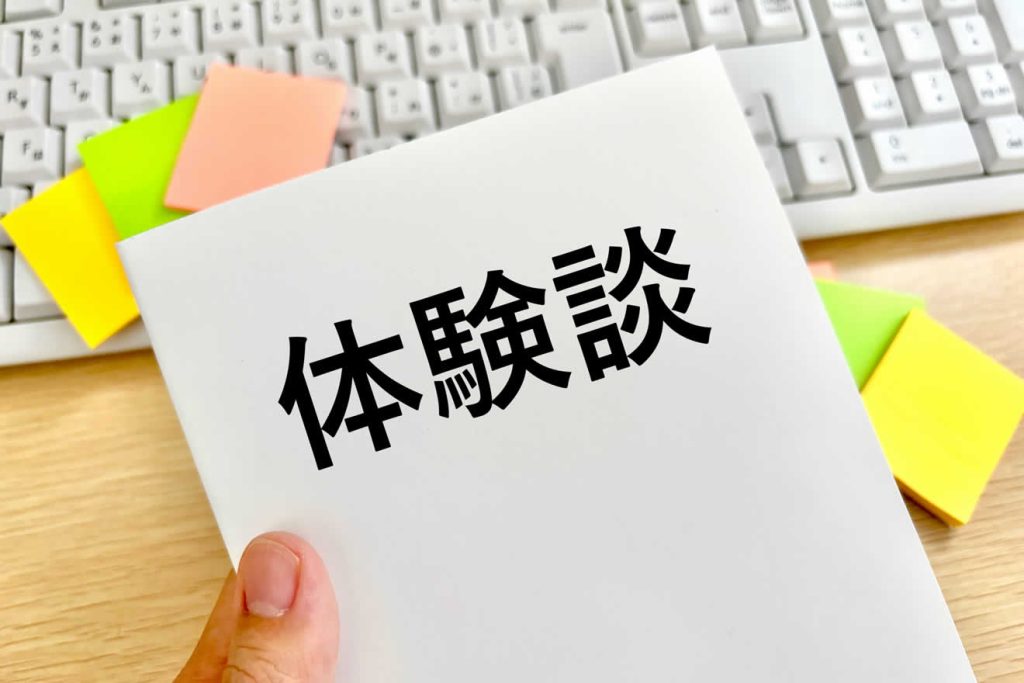
筆者の知人がWebデザイナーの職業訓練を受講した際の体験談をご紹介します。
知人は会社を退職後、3ヶ月間の職業訓練に通いました。
しかし、実際に受けてみると基礎的な内容ばかりで、PhotoshopやIllustratorの基本操作、HTMLの初歩的な書き方程度しか学べなかったそうです。
「正直、全然勉強にならなかった」と知人は振り返ります。
特にWeb制作会社への就職活動では、実務経験やポートフォリオの質が重視されるため、職業訓練で学んだ基礎スキルは全く評価されませんでした。
書類選考の段階で「実務経験なし」という理由で次々と落とされ、面接にすら進めない状況が続いたといいます。
その後、知人は独学でのスキルアップに方向転換しました。
オンライン教材で学習しながら、クラウドソーシングで小さな案件を受注し、実績を積み上げていく方法です。
「職業訓練に通うよりも、独学で勉強してクラウドソーシングで案件をこなしながら実績を積んだほうが、確実に就職に繋がる」と語っていました。
筆者も長くIT業界にいますが、知人が言うように独学で行動できる人ではないと、難しいと思います。
まとめ
職業訓練でWebデザイナーを目指すことに対して「やめとけ」と言われる理由には、スキルが浅い、就職が難しい、競争が激しいといった現実的な問題があります。
また、カリキュラムが古い場合や個別対応の難しさ、実務経験不足といったデメリットも存在します。
しかし、費用が安く基礎が身につく、就職支援が充実している、仲間と学べるといったメリットも確実にあります。
重要なのは、職業訓練の特徴を理解した上で自分に適した選択をすることです。
職業訓練に落ちた場合や授業についていけない場合の原因を事前に把握し、対策を立てることで成功確率を高められます。
Webデザイナーへの道は決して平坦ではありませんが、適切な準備と覚悟があれば職業訓練も有効な選択肢となります。
まずは自分の状況と目標を明確にし、最適な学習方法を選択しましょう。



