仕事に対する「気持ちの糸が切れる瞬間」は、誰にでも訪れるものですよね。
毎朝目覚ましが鳴った瞬間から憂鬱になってしまうし、「このまま同じ環境で頑張り続けるべきか」と迷う気持ちよくわかります。
できることなら、前向きな気持ちで仕事に取り組みたいですよね。
実は、この「気持ちが切れた状態」を冷静に分析することで、正しい判断ができます。
モチベーションが完全に失われているのであれば、無理に続ける必要はありません。
そこで今回は、「気持ちが切れたときの退職の判断基準」をご紹介します。
仕事への情熱が消えてしまったなら、それを新たなスタートの機会に変えるようにしましょう。
- 気持ちが切れるメカニズムと原因を理解できる
- 心が限界に達した時の具体的な対処法を学べる
- 退職から転職までの計画的なステップを知れる
仕事で気持ちが切れてしまう原因

多くの人が経験する「気持ちが切れる」状態は、突然訪れるものではなく、日々の積み重ねによって引き起こされます。
心理的な限界を超えるサインとして現れるこの現象を理解することが、適切な対処への第一歩となります。
- 過剰な仕事量
- 職場の人間関係
- 努力が評価されない
- 仕事のマンネリ化
- 不安定な職場環境
- 報酬に対する不満
- キャリアの停滞感
過剰な仕事量
業務量が許容範囲を超えると、心身ともに疲弊し、モチベーションが急激に低下することがあります。
長時間労働や際限のない仕事の増加は、人間の回復力を超えるストレスを生み出すからです。
たとえば、平日は毎日深夜まで残業し、休日出勤も常態化している状態が続くと、睡眠不足や慢性疲労から判断力が鈍り、些細なミスが増え、さらに自己嫌悪に陥るという悪循環に陥ります。
心身の健康を守るためにも、自分のキャパシティを見極め、必要に応じて業務調整を依頼しましょう。
職場の人間関係
良好な人間関係がない職場環境は、日々のストレスを増幅させ、気力を奪います。
同僚や上司とのコミュニケーション不足は、毎日の出社を苦痛に変え、心の余裕を失わせるからです。
具体的には、些細な意見の相違が感情的な対立に発展したり、チーム内での孤立感を感じたりすることで、本来の業務に集中できなくなり、エネルギーが人間関係の維持に消費されていきます。
職場での良好な人間関係を築くための努力をしつつも、過度にストレスを感じる環境は見直す必要があるでしょう。
努力が評価されない
頑張りが正当に評価されないと感じる状況は、モチベーションを根本から損なう要因となります。
人は自分の貢献が認められ、適切なフィードバックを得ることで、仕事への意欲を維持できるからです。
たとえば、徹夜で仕上げたプロジェクトが上司から一言の評価もなく、むしろ些細な点を指摘されるだけだったり、同僚の軽い努力は称賛される一方で、自分の地道な貢献は当然視されたりする状況が続くと、「何のために頑張っているのか」という虚無感に襲われます。
適切な評価を求めることは決してわがままではなく、健全な職場環境の基本要素だと理解しましょう。
仕事のマンネリ化
同じ業務の繰り返しは、次第に仕事の意義や面白さを感じられなくなる原因になります。
人間の脳は新しい刺激や挑戦を好む性質があり、単調な作業の継続は知的好奇心や成長意欲を満たせません。
具体的には、入社当初は意欲的に取り組んでいた業務も、3年、5年と同じ作業を繰り返すうちに、「この先も変わらない日々が続くのか」という閉塞感が募り、次第に出社すること自体に意味を見出せなくなっていきます。
新しい挑戦や学びの機会を意識的に取り入れることで、仕事への新鮮な視点を維持できるでしょう。
不安定な職場環境
会社の経営状況や組織変更が不透明だと、将来への不安から気持ちが切れやすくなります。
人間は心理的安全性を求める生き物であり、先行きが見えない状況は大きな精神的負担となるからです。
たとえば、突然の人員整理や度重なる組織再編、経営陣からの矛盾するメッセージなどにより、「いつ自分の立場が変わるか分からない」という恐怖心が日々の業務に集中できない状態を作り出します。
不確実な状況でも自分を守るための情報収集や準備をしながら、コントロールできる範囲に意識を向けることが大切です。
報酬に対する不満
努力や能力、市場価値に見合わない報酬は、仕事への意欲を低下させる重要な要因です。
適切な報酬は単なる生活の糧だけでなく、会社からの評価の証でもあり、モチベーションと直結します。
具体的には、同業他社と比較して明らかに低い給与水準や、長年昇給がない状況、責任や業務量の増加に報酬が伴わないケースなどにおいて、「この会社は自分の価値を認めていない」という感覚が芽生え、徐々に仕事へのコミットメントが薄れていきます。
自分の市場価値を正しく把握し、必要に応じて待遇改善の交渉や転職を検討することも選択肢の一つです。
キャリアの停滞感
成長の実感がない状態が続くと、プロフェッショナルとしての充実感を失い、気持ちが切れやすくなります。
人は自己成長やスキルアップを通じて仕事に意義を見出すからです。
たとえば、新しい知識やスキルを身につける機会がなく、5年前と同じレベルの仕事しか任されない環境では、「このまま取り残されるのではないか」という焦りや「自分の市場価値が下がっている」という恐怖が、日々の業務への意欲を削いでいきます。
自己投資や新たな挑戦を自ら求めることで、キャリアの停滞感から抜け出す一歩を踏み出せます。
気持ちの糸が切れやすい仕事の種類

職種によって抱えるストレスや心理的負担は異なります。
特に人との関わりが多い職業や責任が重い立場では、精神的な疲労が蓄積しやすく、気持ちの糸が切れるリスクが高まることがあるのです。
そのため、選んだ職種の特性を理解することで、適切な対策を取ることができるでしょう。
- 接客業
- 医療・介護職
- 営業職
- 教師・教育関連
- ITエンジニア
接客業
常に笑顔と親切さを求められる接客業は、感情による消耗が蓄積しやすい職種です。
顧客満足を最優先する環境では、自分の本当の感情を抑え込み、常に良いパフォーマンスを見せ続けなければならないからです。
たとえば、理不尽なクレームに対しても冷静に対応し続けたり、自分が疲れていても明るく振る舞い続けたりする必要があるため、次第に「本当の自分」と「仕事上の自分」の乖離が大きくなり、感情のバランスを崩してしまいます。
自分の感情と向き合う時間を意識的に作り、オフの時間にはしっかり切り替えて過ごすことが大切です。
医療・介護職
命と健康に関わる責任の重さから、医療・介護職は精神的負担が特に大きい職種となります。
人の生死に関わる判断を日常的に行うプレッシャーや、感情的に辛い場面に何度も立ち会う経験は、徐々に心の余裕を奪っていくからです。
具体的には、夜勤や不規則な勤務形態による身体的疲労に加え、患者や利用者の苦しみに寄り添い続けることで生じる「共感疲労」が蓄積し、次第に感情が麻痺したり、逆に些細なことで涙もろくなったりするなどの変化が現れます。
専門職としてのプライドを大切にしながらも、自分自身のケアを怠らず、必要に応じて同僚と感情を共有することが重要です。
営業職
常に結果を求められる環境は、営業職特有のストレス要因となります。
個人の実績が明確に数値化され、常に評価にさらされる状況は、自己肯定感を損なう原因になりやすいです。
たとえば、どれだけ誠実に顧客対応をしても契約に結びつかないことがある不確実性や、毎月のノルマ未達が続くことでの焦り、競争環境での孤立感などが重なると、「自分は無能なのではないか」という思考に陥りやすくなります。
数字だけでなく、プロセスの質も自己評価の基準にし、短期的な結果に一喜一憂しない視点を持つことが助けになります。
教師・教育関連
子どもの未来を預かる責任の重さと、多様な期待に応える必要がある教育職は、燃え尽き症候群のリスクが高い職種です。
生徒や保護者、学校、社会からの様々な期待に応えようとする中で、理想とする教育を実践することの難しさに直面するからです。
具体的には、授業の準備や事務作業、生徒指導、保護者対応など多岐にわたる業務をこなす中で、「もっと生徒一人ひとりに向き合いたい」という思いと現実とのギャップに苦しみ、次第に教育者としての情熱が薄れていくことがあります。
教育の仕事の価値を再確認しながら、完璧を求めすぎず、小さな成長や変化を喜べる視点を持つことが大切です。
ITエンジニア
テクノロジーの急速な進化と締め切りに追われる環境は、ITエンジニアの精神的疲労を招きやすい要因です。
常に新しい技術を学び続ける必要性と、プロジェクトの厳しい納期の間で板挟みになることで、慢性的な時間不足と焦りを感じやすくなります。
たとえば、昼夜を問わない緊急対応や、無理なスケジュールでのプロジェクト遂行、技術的負債の蓄積に対する無力感などが重なると、「どれだけ頑張っても追いつかない」という諦めや挫折感が広がり、次第に仕事への情熱が失われていきます。
自己成長のペースを自分で決め、技術習得と休息のバランスを意識的に取る必要があるでしょう。
気持ちが切れてしまった時の対処法

仕事への意欲が突然消失したとき、それは心身からのSOSサインかもしれません。
無理に耐え続けるのではなく、適切に自分自身をケアすることが、健全な状態への回復には不可欠です。
まずは自分を責めることなく、以下の対処法を試してみましょう。
- 休息を取る
- 感情を整理する
- 環境を変える
- サポートを求める
- 小さな目標を設定する
- ストレスを発散する
- 専門家に相談する
休息を取る
心身が限界に達したサインを感じたら、まずは十分な休息を優先させることが回復への第一歩です。
疲労が蓄積した状態では冷静な判断ができず、問題がさらに深刻化する恐れがあります。
たとえば、有給休暇を数日取得して睡眠時間を確保したり、週末は仕事関連の連絡を遮断したりすることで、心身をリセットする時間を作ることができます。
休息は怠慢ではなく、長期的なパフォーマンスを維持するための必要な投資だと捉えましょう。
感情を整理する
気持ちが切れた状態では、自分の感情を言語化し整理することで、問題の本質を見極めることができます。
モヤモヤした不満や怒りをそのままにしておくと、より大きなストレスとなって心身に悪影響を及ぼすからです。
具体的には、日記を書いたり、信頼できる相手に話を聞いてもらったりすることで、「なぜ自分はこんなに苦しいのか」「何が一番のストレス要因なのか」を客観的に分析できるようになります。
自分の感情と向き合い、それを受け入れることが、次のステップに進むための土台となるでしょう。
環境を変える
同じ環境に留まり続けることで問題解決が難しい場合は、物理的または心理的な環境の変化が有効です。
視点や立場を変えることで、これまで気づかなかった解決策や可能性が見えてくるからです。
たとえば、部署異動や業務内容の変更を申し出たり、デスクの配置を変えたり、在宅勤務の日を増やしたりするなど、小さな変化から始めることで新鮮な気持ちで仕事に向き合えるようになります。
環境変化を恐れず、自分にとって最適な働き方を模索することは、キャリア構築において重要な要素です。
サポートを求める
一人で抱え込まず、周囲の力を借りることは、困難な状況を乗り越えるための賢明な選択です。
人間は社会的な生き物であり、適切なサポートがあることで回復力が高まります。
具体的には、上司に業務調整を相談したり、同僚と協力体制を築いたり、家族や友人に気持ちを吐露したりすることで、精神的な負担が軽減し、新たな視点や解決策を得られることがあります。
弱みを見せることは恥ではなく、より良い状況を作り出すための勇気ある一歩だと理解してください。
小さな目標を設定する
大きな壁に圧倒されているときは、達成可能な小さな目標を設定することで、成功体験を積み重ねてください。
小さな成功体験は自己効力感を高め、「できる」という感覚を取り戻す助けになるからです。
たとえば、一日の業務を細かく分解し、「午前中にメール返信を終わらせる」「今日は一つの書類を完成させる」など、具体的かつ達成可能な目標を設定することで、少しずつ自信を回復していくことができます。
一歩一歩の小さな進歩を認め、自分を褒める習慣をつけることが長期的な回復につながるでしょう。
ストレスを発散する
溜まったストレスを健全な方法で発散することは、心のバランスを保つために不可欠です。
抑圧された感情やストレスは、放置すると心身の不調や突発的な感情爆発につながりかねません。
具体的には、運動やスポーツで体を動かしたり、創作活動や趣味に没頭したり、自然の中で過ごしたりするなど、仕事とは全く異なる活動を通じてリフレッシュする時間を作ることが大切です。
自分に合ったストレス発散法を見つけ、定期的に実践することで、心の余裕を維持できます。
専門家に相談する
自分だけでは対処が難しいと感じたら、専門家のサポートを受けることも選択肢の一つです。
心の不調は風邪と同じように適切なケアが必要であり、早期の対応が症状の悪化を防ぎます。
たとえば、産業医やカウンセラー、心療内科医などの専門家に相談することで、客観的な視点からのアドバイスや、状況に応じた具体的な対処法、必要であれば適切な治療を受けることができます。
専門家への相談は弱さの表れではなく、自己管理能力の高さと前向きな姿勢の証です。
気持ちが切れて退職する際の注意点

仕事に対するモチベーションが完全に失われたとき、退職は一つの選択肢となります。
しかし、感情的な判断だけで行動すると後悔を招くことも珍しくありません。
冷静さを保ちながら、計画的に進めることで、次のステップへのスムーズな移行が可能になります。
退職を考える際には以下のポイントに注意しましょう。
- 退職理由を明確にする
- 引き継ぎをしっかり行う
- 退職時期を考慮する
- 転職先を見つけてから辞める
- 法的な手続きを確認する
退職理由を明確にする
感情的な判断ではなく、自分が退職を考える本当の理由を冷静に分析することが重要です。
明確な理由を把握することで、次の職場で同じ問題に直面するリスクを減らし、より良い選択ができます。
たとえば、「人間関係がつらい」と感じている場合でも、それが特定の上司との相性なのか、組織文化との不一致なのか、自分のコミュニケーションスタイルに課題があるのかを具体的に分析することで、次の職場選びの際の重要な判断材料となります。
自分の価値観や優先順位を見つめ直し、退職後に何を実現したいのかを明確にすることで、後悔のない決断ができるのです。
引き継ぎをしっかり行う
どれほど気持ちが切れていても、社会人として責任ある引き継ぎを行うことが将来の評価につながります。
不十分な引き継ぎは、残される同僚に負担をかけるだけでなく、自分自身の社会的信用にも関わる問題です。
具体的には、業務マニュアルの作成、重要な連絡先のリスト化、未完了案件の状況整理、特殊なノウハウの共有など、自分がいなくなっても業務が滞らないための準備を計画的に進めることが大切です。
丁寧な引き継ぎは、円満退社への道を開き、将来的なキャリアにおいても良い評判として残ります。
退職時期を考慮する
会社やチームにとって負担の少ない時期を選んで退職することで、人間関係や評判を損なうリスクを減らせます。
気持ちが切れていても、退職のタイミングは計画的に選ぶことが賢明な判断です。
たとえば、繁忙期や大きなプロジェクトの山場、決算期などを避け、比較的落ち着いた時期に退職の意向を伝えることで、会社側も柔軟に対応しやすくなり、円満な退職につながりやすくなります。
退職後も業界内での評判や人脈を大切にするためにも、最後まで配慮ある行動を心がけましょう。
転職先を見つけてから辞める
経済的な安定を確保するためにも、なるべく次の就職先を決めてから辞めてください。
感情的な判断で突然退職すると、経済的不安や焦りから、次のキャリアでも妥協した選択をしてしまう可能性があります。
具体的には、現職に在籍しながら転職活動を進め、内定を獲得してから退職の意思を伝えることで、空白期間なくキャリアを継続でき、経済的なリスクも最小限に抑えられます。
計画的なキャリア移行は、精神的な余裕も生み出し、新しい環境への適応もスムーズになるでしょう。
法的な手続きを確認する
退職に関する法的権利や義務を理解し、適切な手続きを踏むことで、トラブルを未然に防げます。
感情的になりがちな退職プロセスでも、法的な側面をしっかりと押さえておくことが重要です。
たとえば、退職届の提出時期(一般的には2週間前だが、就業規則で1ヶ月前などと定められていることも多い)、有給休暇の消化権利、競業避止義務の有無、退職金や社会保険の手続きなど、確認すべき事項を洗い出し、計画的に対応することが必要です。
法的なトラブルを避けるためにも、就業規則を確認し、必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。
糸が切れた後の退職から転職までのステップ

気持ちが切れた状態からの退職は、単なる逃避ではなく、キャリアの再構築の機会でもあります。
混乱しがちなこの時期を乗り越え、より良い職場環境へと移行するためには、段階的なアプローチが効果的です。
感情に流されず、計画的に次のステップへ進むことで、新たな可能性が開けるでしょう。
- 心の整理と休息
- 自己分析と希望条件の整理
- 転職市場のリサーチ
- 転職活動と面接
- 退職手続きと新しい職場への適応
心の整理と休息
退職を決意した後、まずは十分な休息を取り、心の整理をすることが次へのステップの土台となります。
強いストレスを抱えたまま次の環境に飛び込むと、同じ問題を繰り返すリスクが高まるからです。
たとえば、退職後に1〜2週間の空白期間を意識的に作り、旅行に出かけたり、趣味に没頭したり、ただ十分な睡眠を取るなど、心身をリセットする時間を大切にすることで、冷静な判断力と前向きな気持ちを取り戻すことができます。
この期間は無駄ではなく、長期的なキャリア形成における重要な投資だと捉えることが大切です。
自己分析と希望条件の整理
前職での経験を踏まえ、自分の強み・弱み・価値観を分析し、次に求める職場環境を明確にしてください。
職場のミスマッチを繰り返さないためには、自己理解と職場に求める条件の明確化が不可欠です。
具体的には、「前職で何が辛かったのか」「どんな環境なら力を発揮できるか」「譲れない条件は何か」などを紙に書き出し整理することで、漠然とした不満や希望が具体的な条件として明確になり、転職活動の指針となります。
自分自身と向き合うこの過程を丁寧に行うことで、より自分に合った職場を見つける確率が高まるでしょう。
転職市場のリサーチ
自分の希望条件に合う業界や企業の情報を幅広く収集し、現実的な選択肢を把握してください。
感情的な退職後に焦って転職先を決めると、条件面での妥協が大きくなりがちです。
たとえば、転職サイトの求人情報を分析したり、業界セミナーに参加したり、知人からの情報収集や企業の口コミサイトをチェックするなどします。
多角的な視点から情報を集めることで、表面的な求人情報だけでは見えない企業の実態や業界動向を把握できます。
時間をかけて情報収集することで、自分の市場価値の現実的な理解にもつながり、交渉の際にも有利になるでしょう。
転職活動と面接
準備が整ったら、計画的に応募と面接に臨み、企業と自分の相性を見極めることが大切です。
転職活動は単なる就職先探しではなく、自分と企業の価値観や方向性のマッチングを確認するプロセスです。
具体的には、履歴書や職務経歴書を丁寧に作成し、面接では前職での退職理由を建設的に伝えつつ、自分が求める環境や貢献できる価値を明確に説明することで、互いに期待値のギャップが生じにくくなります。
面接では聞かれることに答えるだけでなく、自分から質問することで企業文化や職場環境がわかってくるでしょう。
退職手続きと新しい職場への適応
内定を獲得したら、現職での退職手続きを丁寧に行い、新環境へのスムーズな移行を目指してください。
最後まで誠実な対応を心がけることで、前職での人間関係を良好に保ちながら新しいスタートを切れます。
たとえば、退職の意思を直属の上司に伝え、必要な引き継ぎ資料を作成し、並行して新しい職場で求められるスキルの準備や情報収集を行うことで、精神的にも実務的にも余裕を持って環境の切り替えができます。
新しい職場では、最初の3ヶ月を「学びの期間」と位置づけ、周囲への適応と自分の価値発揮のバランスを意識しましょう。
気持ちが切れた時のよくある疑問
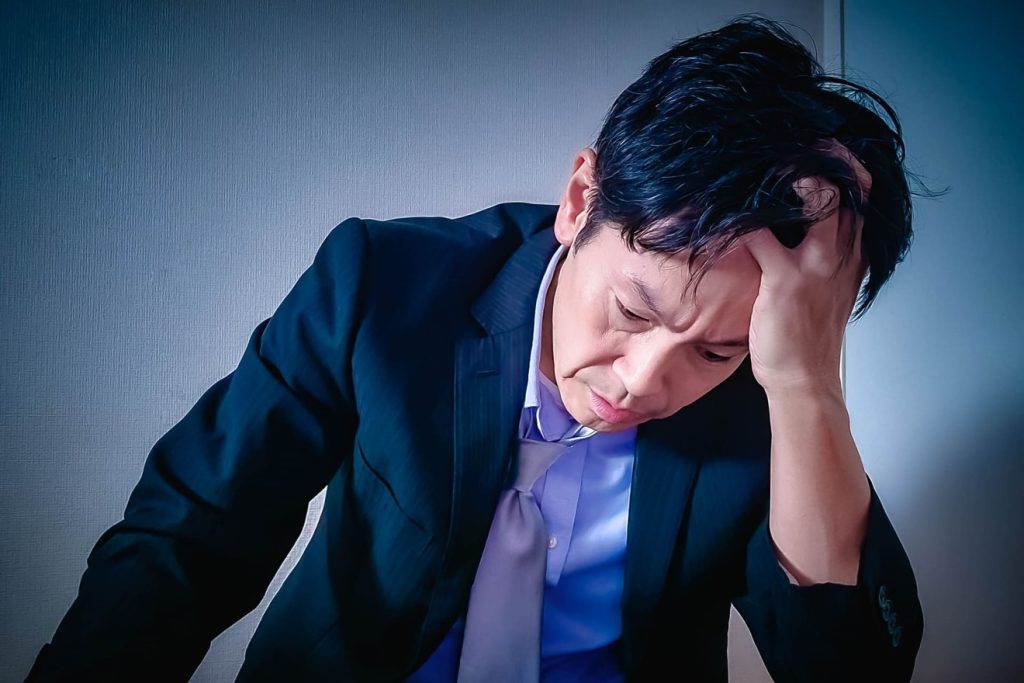
仕事に対するモチベーションの喪失は誰もが経験する可能性がある現象です。
そんな時、多くの人が同じような疑問や不安を抱えています。
ここでは、気持ちが切れた状態に関する一般的な疑問に答え、その背景にある心理メカニズムを解説します。
- 仕事がどうでも良くなってしまったのはなぜ?
- モチベーションが切れたら休職するのもあり?
- 急にやる気がなくなった部下はどうする?
- 急に気持ちが切れるのは病気?
- 真面目な人ほど糸が切れるようになる?
仕事がどうでも良くなってしまったのはなぜ?
長期間にわたる過度なストレスや期待と現実のギャップが、仕事への無関心さを引き起こす主な原因です。
人間の心は自己防衛のために、過度なストレス状況から精神を守ろうとして感情の麻痺や無関心という反応を示すことがあります。
たとえば、何度も頑張っても評価されない経験や、自分の価値観と合わない業務を続けることで、「どうせ何をしても変わらない」という学習性無力感に陥り、徐々に仕事への情熱や関心が薄れていきます。
この状態は心からのサインであり、自分の価値観や環境との関係を見直す重要な機会として捉えることが大切です。
モチベーションが切れたら休職するのもあり?
モチベーションが完全に失われた状態は、休職を検討する正当な理由になり得ます。
心身の疲労が蓄積したまま無理に仕事を続けることは、生産性の低下や健康被害につながる可能性があるからです。
たとえば、毎日強い憂鬱感を感じているのであれば、一時的に職場を離れ、自分を立て直す時間を作るのも大切です。
休職は決して逃げではなく、長期的なキャリア形成のための戦略的な選択肢の一つだと捉えましょう。
急にやる気がなくなった部下はどうする?
まずは原因を探るための対話の機会を設け、個人の状況に合わせたサポートを提供することが有効です。
部下のモチベーション低下には、仕事内容の不一致、評価への不満、私生活での問題など様々な要因が考えられます。
たとえば、1対1の面談の場を設けて「最近何か困っていることはないか」と率直に尋ねたり、必要に応じて休息を促すことで、多くの場合は回復の兆しが見られます。
管理職として重要なのは、問題の早期発見と適切な対応であり、個人の状況を尊重しながらも組織としてのサポート体制を整えることが信頼関係構築につながります。
急に気持ちが切れるのは病気?
突然のモチベーション喪失が持続する場合、うつ病やバーンアウト症候群などの可能性も考慮する必要があります。
一時的な意欲低下と病的な状態の境界は明確でなく、症状が2週間以上続く場合や日常生活に支障をきたす場合は注意が必要です。
具体的には、仕事へのやる気だけでなく、睡眠や食欲の乱れがある、集中力が著しく低下するといった症状が現れる場合は、専門家に相談してください。
心の不調は早期発見・早期対応が重要であり、自分を責めるのではなく適切な休息と専門的なサポートを受けることが回復への近道です。
真面目な人ほど糸が切れるようになる?
責任感が強く完璧主義傾向のある人は、自分に高い基準を設定し続けるため、燃え尽き症候群のリスクが高まります。
真面目な人ほど「こうあるべき」という理想像と現実とのギャップに苦しみ、限界を超えても頑張り続ける傾向があるのです。
たとえば、「迷惑をかけたくない」「期待に応えなければ」という思いから休息を取らずに働き続けたり、知らず知らずのうちに心身の余力を使い果たしてしまいます。
自分の限界を認識し、完璧を求めすぎない姿勢や、時には「ほどほど」で良しとする柔軟性を持つことが、長期的なキャリア構築には不可欠です。
気持ちが切れてしまって退職した話

筆者が20代の頃、ベンチャー企業でWeb制作の仕事をしていました。
入社当初は「自分のデザインでユーザー体験を変えられる」という夢を抱いていたのですが、現実は違いました。
日々の業務は既存テンプレートの色変更や文字サイズ調整といった流れ作業の連続。
「これがデザインなのか?」という疑問が日に日に大きくなっていったのです。
企画会議での提案も「よくわからない」という理由で却下され続け、創造性を発揮する機会はありません。
ある月曜日の朝、いつものようにデスクに向かった時、突然「もうこれ以上続けられない」と感じました。
PCの電源を入れる手が震え、画面を見るだけで吐き気がするほどでした。
それからは辞めるタイミングばかりを考えていたと思います。
そんな中で当時の上司と衝突したことをきかっけに、会社を辞めることになりました。
仕事が楽しければ上司に歯向かうこともなかっただろうなっと、今になっては思います。
やはり、どんな仕事でも気持ちが切れたら退職するしかないのではないでしょうか。
気持ちが切れるという経験は、自分の本心と向き合う重要なメッセージだったのです。
まとめ
気持ちの糸が切れてしまったとき、それは自分自身と向き合うための大切なシグナルです。
過剰な仕事量や人間関係の悩み、評価への不満など、様々な原因が複雑に絡み合い、徐々に気力を奪っていきます。
特に接客業や医療・介護職、IT業界など、精神的負担の大きい職種ではこの現象が起こりやすいことを理解しましょう。
気持ちが切れそうになったときは、早めに休息を取り、感情を整理することから始めてください。
必要に応じて環境変化を模索し、周囲のサポートを求めることも大切です。
気持ちが切れたから退職するというのは、決しておかしい行動ではありません。
新しい人生をスタートさせるためにも、自分を責めずに前向きに行動するようにしましょう。



