トリマーになるのは、動物好きにとって夢のような仕事ですよね。
ただ、ネットには「トリマーはやめとけ」といった意見もあるため、不安になる気持ちわかります。
できることなら、好きなことを仕事にして、楽しく働きたいですよね。
実は、トリマーの現実をしっかり理解することで、応募するかどうかを判断できるのです。
事前に情報を知ることで、後悔せずに納得した選択ができます。
そこで今回は、「トリマーを目指すなら知っておきたいメリット・デメリット」をご紹介します。
もしあなたがトリマーの道に進むなら、不安を解消しながら、理想の働き方を叶えられるようにしましょう。
- トリマーの仕事内容や魅力を詳しく理解できる
- トリマーになるためのステップを明確に把握できる
- 自分に向いているかどうか判断するためのヒントが得られる
トリマーの仕事内容

トリマーの主な仕事は、犬や猫などのペットの毛をカットし、シャンプーや爪切り、耳掃除といったグルーミングを行うことです。
見た目を整えるだけでなく、ペットの健康状態をチェックする役割も担っています。
毛玉や皮膚の異常、体重の変化など、飼い主が気づきにくい部分を観察し、適切にアドバイスすることも求められます。
加えて、ペットとの信頼関係を築き、ストレスを最小限にする技術が重要です。
トリミングサロンや動物病院に勤務するほか、自分でサロンを開業する道もあり、働き方の幅が広い職業です。
トリマーの平均年収

トリマーの平均年収は、一般的に250万円から350万円程度と言われています。
経験やスキルによって差があり、駆け出しのトリマーの場合は年収200万円台のスタートが一般的です。
一方で、技術を磨き独立開業した場合や高級サロンで働く場合は、年収が上がることもあります。
ただし、トリマーの仕事は長時間労働になることも多く、給料が労働量に見合わないと感じる人もいるようです。
年収だけではなく、自分のライフスタイルや働き方の希望と照らし合わせて考えることが大切です。
トリマーの将来性

ペット産業が拡大を続ける中で、トリマーの需要は今後も高まると予測されています。
特に、高齢化が進むペットのケアや、トリミングを通じた健康維持の重要性が認識されつつあります。
さらに、ペットのファッションや美容にこだわる飼い主が増えているため、トリミングのスキルが評価される場面が多くなっています。
ただし、業界の競争は激しく、技術の向上や差別化が求められます。
また、AIや自動化技術の進展により、一部の業務が効率化される可能性もありますが、人間の手による繊細なケアは依然として重要であり、やりがいのある職業と言えるでしょう。
トリマーが「やめとけ」と言われる理由

トリマーは動物好きにとって魅力的な仕事ですが、厳しい現実もあります。
体力やメンタルの負担が大きい点や、収入面での課題など、理想と現実のギャップに悩む人も少なくありません。
ここからは、トリマーが「やめとけ」と言われる具体的な理由を解説します。
- 体力的にきつい
- 給料が低い
- ストレスが溜まりやすい
- 怪我や病気のリスク
- 休みが取りづらい
体力的にきつい
トリマーの仕事は立ち仕事が基本で、1日に何時間も同じ姿勢で作業を続けることがあります。
大型犬のシャンプーやトリミングは特に体力を要し、腰や肩に負担がかかりやすいです。
たとえば、大型犬を抱えて作業台に乗せる場合や、動き回る小型犬を安全に固定する際など、かなりの体力を使います。
このように、体力的な負担が大きい職業であることを理解しておく必要があるでしょう。
給料が低い
トリマーの収入は、ペット産業の需要が増加しているにもかかわらず、高いとは言えません。
経験や技術の差が大きく反映されるため、駆け出しのトリマーでは手取りが非常に少ないケースもあります。
たとえば、フルタイムで働いていても生活費をギリギリ賄える程度の給料にとどまることがあります。
特に都市部では、家賃や交通費を考慮すると十分な余裕がないと感じる人も多いようです。
ストレスが溜まりやすい
トリマーの仕事は動物相手とはいえ、人間の顧客とのコミュニケーションも重要です。
飼い主の要望に応えるプレッシャーや、ペットが協力的でない場合の対応がストレスとなることがあります。
具体的には、気性が荒く噛みつこうとする犬を扱うときや、飼い主の理想の仕上がりに満たないと不満を言われる場合などが挙げられます。
こうした状況が重なると、精神的な疲労が溜まりやすくなるでしょう。
怪我や病気のリスク
動物相手の仕事には、噛まれる、引っ掻かれるといった怪我のリスクが伴います。
さらに、動物由来の感染症に注意が必要で、日々の衛生管理を徹底しなければなりません。
たとえば、過剰な力で抵抗する猫に引っ掻かれ、傷が化膿するケースなどがあります。
こうしたリスクを最小限にするための、知識や注意力が求められる仕事です。
休みが取りづらい
トリミングサロンは、土日や祝日、年末年始といった繁忙期に営業していることが多く、トリマーにとって休暇を確保しにくい環境です。
特にペットホテルを併設している店舗では、休みなく出勤を求められる場合があります。
たとえば、家族旅行が計画しづらかったり、体調不良時でも休めないことがあるなど、プライベートの時間を犠牲にする必要があります。
休みが取りづらいため、疲労が蓄積しやすいでしょう。
トリマーになる魅力やメリット

トリマーは、動物好きにとって理想的な職業であり、多くのやりがいや充実感を得られる点が魅力です。
また、職業としての安定性や将来の可能性も広がっています。
ここでは、トリマーのポジティブな側面について解説します。
- 動物と毎日触れ合える
- やりがいを感じやすい仕事
- 雇用が安定している
- チームで働く楽しさ
- 独立や開業のチャンス
動物と毎日触れ合える
トリマーは、動物が好きな人にとって夢のような職業です。
日々の仕事を通じて犬や猫などのペットと触れ合い、その健康や見た目を整えることで飼い主にも喜んでもらえます。
たとえば、毛が伸び放題だった犬を整えて清潔感のある姿に仕上げることで、ペットがさらに愛される存在になるのを間近で感じることができます。
動物と過ごす時間が多いことは、何物にも代えがたい魅力です。
やりがいを感じやすい仕事
トリマーは、ペットと飼い主の両方に喜びを提供できる仕事です。
施術が終わった後、飼い主から感謝の言葉をもらえる瞬間は、大きなやりがいとなります。
「とても可愛くなりました」「またお願いしたい」といった声を直接聞けることで、仕事へのモチベーションが高まります。
結果が目に見えやすい職業である点も、トリマーならではの魅力です。
雇用が安定している
ペット産業が拡大している現代では、トリマーの需要は非常に高まっています。
特に、ペットを家族の一員として考える人が増えているため、トリミングサロンや動物病院での求人があります。
地方でも求人を見つけやすく、一定の技術を持っていれば就職に困ることが少ないのが特徴です。
長く働ける職業であり、安心感があるでしょう。
チームで働く楽しさ
トリミングサロンでは、他のトリマーやスタッフと協力しながら仕事を進めることが多いです。
一人では対応しきれない場合も、チームワークで乗り越えることができ、仲間との絆が深まります。
具体的には、忙しい日でもスタッフ同士で分担しながら業務を進めることで、達成感を共有できます。
チームで働く楽しさを実感できるため、人間的に成長できるでしょう。
独立や開業のチャンス
トリマーは、自分のスキルを活かして独立や開業を目指せる職業でもあります。
自分の理想とするサロンを作ることや、オリジナルのサービスを提供することで、やりがいや収入アップを目指せます。
たとえば、小型犬専門のサロンや、オーガニック製品を使ったトリミングサービスなど、個性を活かしたビジネス展開が可能です。
夢を広げるチャンスがある点は、大きなメリットと言えます。
トリマーに向いている人の特徴

トリマーは、動物への愛情だけでなく、いくつかの特性やスキルが求められる仕事です。
向いている人の特徴を知ることで、自分がトリマーとして活躍できるかどうかを判断しやすくなります。
こここでは、トリマーに必要な特性について詳しく解説します。
- 動物が好き
- 手先が器用
- 忍耐力がある
- 体力がある
- コミュニケーションが得意
動物が好き
動物への深い愛情は、トリマーにとって欠かせない要素です。
犬や猫の性格や状態を理解し、信頼関係を築くことが仕事の基本だからです。
たとえば、怖がりな犬に優しく接して緊張をほぐしたり、気分屋な猫に無理をさせないよう工夫するなど、動物に寄り添う姿勢が必要です。
動物好きであれば、日々の仕事が楽しく感じられるでしょう。
手先が器用
トリミングでは、細かい作業が求められます。
ハサミやバリカンを使ってペットの毛を美しく整えるためには、手先の器用さが重要です。
たとえば、毛の長さを均一に揃えたり、顔周りのデリケートな部分を仕上げる際には、慎重な技術が求められます。
手先が器用で、手作業が得意な人には向いている職業といえるでしょう。
忍耐力がある
トリマーの仕事では、動物が思うように動かず時間がかかることも多くあります。
飼い主の要望に応えながら動物の安全を守るためには、忍耐力が必要です。
たとえば、暴れる犬を落ち着かせながら施術を進めたり、長時間の作業でも集中力を切らさずに対応する場面などが挙げられます。
忍耐力が必要であり、困難に立ち向かう粘り強さが求められる仕事です。
体力がある
トリマーは、動物を抱えたり、長時間立ち仕事をすることが多く、体力が求められる職業です。
大型犬のトリミングや重いシャンプーボトルを運ぶ作業では、肉体的な負担がかかります。
具体的には、一日中サロンで動き回ることが続いても、健康的に働き続ける体力がある人は、この仕事に向いていると言えます。
体力があることで、柔軟に動けるでしょう。
コミュニケーションが得意
トリマーは、動物だけでなく飼い主とのコミュニケーションも重要です。
飼い主の要望を正確に聞き取り、仕上がりに反映させることで信頼関係を築きます。
たとえば、「毛を短めに整えて欲しい」「この部分だけは触らないで欲しい」といった要望に柔軟に対応できると、リピーターにつながります。
相手の気持ちを汲み取り、丁寧に説明できる人に向いている職業です。
未経験からトリマーになるステップ

トリマーとして働くためには、動物に関する知識や技術を学び、実践を積むことが重要です。
未経験者でも、必要な準備をしっかりと進めることでトリマーの道を切り開けます。
この章では、未経験からトリマーになるための具体的なステップを解説します。
- 動物と接する機会を作る
- 専門学校に通う
- 実務経験を積む
- 資格を取得する
- 就職活動をする
動物と接する機会を作る
トリマーを目指す第一歩は、動物と触れ合う時間を増やすことです。
動物の行動や気持ちを理解することで、将来の仕事に活かせる基礎が身につきます。
たとえば、動物保護施設でボランティアをしたり、ペットを飼っている知人の手伝いをするなど、日常的に動物に関わる経験を積むのが良いでしょう。
この経験は、専門的な学びを始める前の土台となります。
専門学校に通う
トリマーとしての知識や技術を体系的に学ぶためには、専門学校に通うのが一般的です。
学校では、トリミングの基本的な技術だけでなく、動物の健康管理や接し方など、幅広いスキルを習得できます。
具体的には、シャンプーの仕方やハサミの使い方、犬種ごとのカットスタイルなどを実践的に学べる環境が整っています。
学校選びは、自分の目標や予算に合った場所を選ぶことが重要です。
実務経験を積む
学校で基本を学んだ後は、実際に現場で経験を積むことが重要です。
トリミングサロンや動物病院などで働きながら、実践的なスキルを高めます。
たとえば、さまざまな性格やサイズのペットを扱うことで、柔軟な対応力や効率的な作業方法を身につけることができます。
この段階では、先輩トリマーからの指導を受けることがスキル向上の鍵となるでしょう。
資格を取得する
トリマーとしての信頼性を高めるために、資格を取得することを目指してください。
日本では、必須資格はありませんが、民間資格の取得が就職や開業に役立つことが多いです。
たとえば、JKC(ジャパンケネルクラブ)の公認資格や、ペットトリマー検定などがよく知られています。
資格は、実技試験や筆記試験を含む場合が多いため、計画的な準備が必要です。
就職活動をする
資格を取得し、一定のスキルを身につけたら、就職活動を始めます。
自分の希望に合ったトリミングサロンや動物病院を探し、面接や履歴書で自分の経験や強みをアピールしてください。
たとえば、「学校で習得した基本スキルに加え、現場での実務経験があります」といった具体的な内容を伝えると、採用されやすくなります。
また、インターンシップやアルバイト先からそのまま就職するケースも多いです。
トリマーとして成功するための条件

トリマーとして長く活躍するためには、ただ技術を身につけるだけでなく、継続的な努力と心構えが重要です。
ここからは、トリマーとして成功するために必要な条件を解説します。
- 専門知識を深める
- 技術を磨き続ける
- 体力と忍耐力を維持する
- 安全な作業環境を整える
- 動物を心から愛する
専門知識を深める
トリマーは、動物の種類や特徴に応じた施術を行うための専門知識が欠かせません。
犬種ごとのカットスタイルや、ペットの健康状態に気を配る知識が求められます。
たとえば、皮膚が弱い犬には刺激の少ないシャンプーを使うなど、個々の動物に合わせた対応が必要です。
専門書を読んだりセミナーに参加するなど、常に学ぶ姿勢を持つことが大切です。
技術を磨き続ける
トリミングの技術は一度身につけたら終わりではありません。
トレンドの変化や新しい技術の登場に対応し続けることで、顧客のニーズに応えられるトリマーになれます。
例として、SNSで人気のカットスタイルや、新しい道具の使い方を学ぶことが挙げられます。
練習を重ねることで、技術をブラッシュアップし、競争の激しい業界で差別化を図れるでしょう。
体力と忍耐力を維持する
トリマーの仕事は体力的にも精神的にもハードです。
そのため、健康を維持し、ストレスを上手にコントロールすることが必要になります。
たとえば、定期的な運動で体力をつけたり、趣味の時間を持ってリフレッシュするなど、バランスの取れた生活を心がけてください。
忍耐力を持って困難に向き合う姿勢が、長く働くためのコツとなります。
安全な作業環境を整える
トリミングの現場では、動物やスタッフの安全を確保することが最優先です。
道具の管理や清潔な環境の維持はもちろん、動物がストレスを感じにくい配慮も重要です。
たとえば、ハサミやバリカンを定期的に点検することや、動物が落ち着ける空間作りを意識することが挙げられます。
安全性を確保することで、信頼されるトリマーになることができるでしょう。
動物を心から愛する
何よりも大切なのは、動物への深い愛情です。
動物が安心して施術を受けられるように配慮し、その健康や幸せを第一に考える姿勢が、飼い主からの信頼に繋がります。
たとえば、緊張している犬に優しく声をかけたり、不安そうな猫に無理をさせないよう気遣うことなど、動物を思いやる気持ちが大切です。
この心構えが、成功するトリマーに共通する特質といえるでしょう。
トリマーになりたい人のよくある疑問

トリマーを目指す人にとって、事前に気になることや不安はつきものです。
ここでは、トリマーについてよくある疑問を取り上げ、それに対する具体的な回答をお伝えします。
これからトリマーを目指す人にとって、より明確な道筋を示す内容となるでしょう。
- トリマーは離職率が高い?
- トリマーはうつ病になりやすい?
- トリマーはどんな資格が必要?
- トリマーが性格悪いと言われる理由は?
- トリマーは給料安くて生活できない?
トリマーは離職率が高い?
トリマーの仕事は、一般的に離職率が高いと言われます。
理由として、体力的な負担や収入面での課題が挙げられるからです。
たとえば、長時間の立ち仕事や、動物を抱える作業の繰り返しで体に負担がかかる場合があります。
また、初任給が低めであるため、生活に不安を感じる人も少なくありません。
ただし、経験を積んで技術を高めることで、収入や働きやすさが改善されるケースも多いです。
トリマーはうつ病になりやすい?
動物と触れ合う癒やしの仕事ではありますが、ストレスの多さからうつ病になるトリマーもいます。
飼い主からの厳しい要求や、仕事の忙しさ、動物の命を預かる責任の重さなどがあるからです。
たとえば、予想外のトラブルに対処し続けることで精神的な疲労が溜まることがあります。
しかし、職場環境を選ぶことや、ストレス発散の習慣を取り入れることで、心身の負担を軽減することが可能です。
トリマーはどんな資格が必要?
トリマーとして働くためには、必須の国家資格はありませんが、民間資格を取得していると就職や仕事の幅が広がります。
JKC(ジャパンケネルクラブ)の公認トリマー資格や、ペットトリマー検定などが一般的です。
資格は、技術力や知識の証明となり、飼い主や雇用主からの信頼を得やすくなります。
資格取得の際には、専門学校や養成講座で学ぶのが一般的なルートです。
トリマーが性格悪いと言われる理由は?
一部では「トリマーは性格が悪い」といった声も聞かれますが、それは誤解や偏見である場合がほとんどです。
このような意見が出る背景には、飼い主の要望に対して厳しく対応する場面があることや、忙しい現場で感情が表に出てしまう場合が挙げられます。
たとえば、動物の安全を優先するために、飼い主の要望を断ることがある場合です。
しかし、それはプロ意識の表れであり、性格とは無関係といえるでしょう。
トリマーは給料安くて生活できない?
トリマーの初任給は低い傾向にありますが、経験や技術次第で収入を増やすことは可能です。
たとえば、独立して自分のサロンを経営したり、高度な技術を習得して高級サロンで働くことで、年収を上げるケースがあります。
また、地域や職場によっても給料は大きく異なるため、自分の働き方に合った環境を選ぶことが重要です。
トリマーとして働く人の体験談
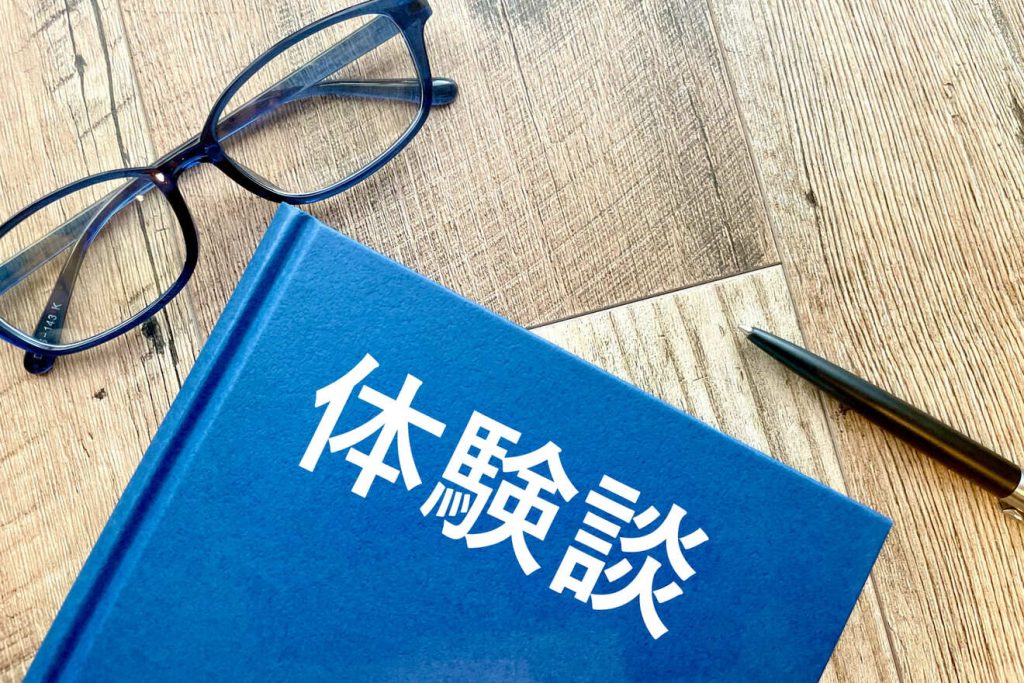
筆者は採用支援をしている中で、トリマーとして5年の経験があるSさん(仮名)に話を聞く機会がありました。
彼女は、動物が好きでトリマーの仕事を始めたものの、現実の厳しさに直面したと語ります。
「最初は楽しくて、毎日動物と触れ合えることにやりがいを感じていました。でも、仕事が長時間になったり、体力的に厳しくなる場面が増えてきました。特にシャンプーやカットでの手の負担が大きく、身体がきついと感じることも多かったですね。」
それでも、Sさんは仕事に対する情熱を失わなかったと言います。
「やりがいを感じる瞬間も多くて、お客様から『ありがとう』と言われると心が温かくなります。動物の健康を守る大切な仕事だと実感しています。」
現在、Sさんは職場でチームリーダーとして働き、後輩の指導にも力を入れているそうです。
「体力的にきついこともありますが、仲間と助け合いながらやっています。これからも技術を磨き、もっと多くの動物と関わりたいですね。」
彼女の話から、トリマーという仕事の魅力と同時に、課題にも向き合いながら成長していく姿勢が伝わってきました。
まとめ
トリマーは、動物が好きな人にとって夢のある仕事でありながら、体力的な負担や収入面の課題など、「やめとけ」と言われる理由も存在します。
しかし、トリマーとして働くことで動物と触れ合い、やりがいを感じ、独立や開業といったキャリアの可能性を広げられるのも事実です。
未経験からトリマーを目指すためには、動物との接点を増やし、専門学校や資格取得でスキルを磨き、現場経験を積むステップが重要です。
そして、成功するトリマーになるためには、専門知識を深め、技術を向上させ、動物を愛する気持ちを忘れないことが鍵です。
不安や疑問があっても、一つひとつ向き合いながら前に進むことで、自分に合った働き方を見つけられます。
トリマーとしての魅力や現実をしっかりと理解し、自分自身の選択に自信を持って進んでください。
動物とともに歩む素晴らしい未来を築けるよう、ぜひその一歩を踏み出しましょう。



